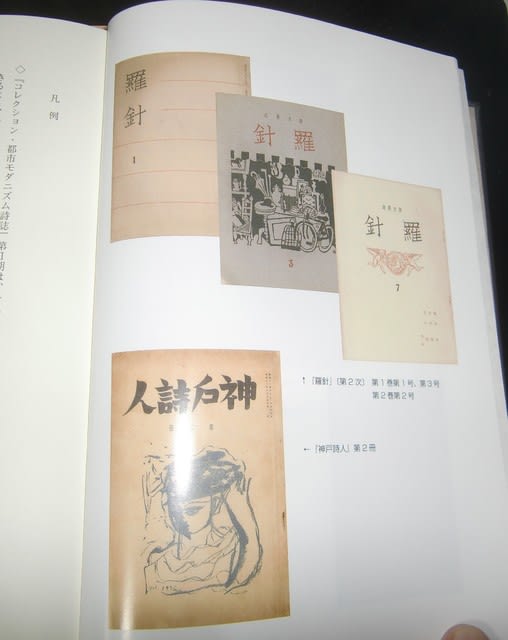『ねじとねじ回し』(ヴィトルト・リプチンスキ著)という本を読んでいて、「発明」ということに感心させられている。

51ページにこんなことが書かれている。
《寒さを防ぐ便利な道具であるにもかかわらず、人類は歴史のほとんどの期間を通じて、ボタンを知らずに過ごした。(略)日本人は着物を帯で締めていた。(略)13世紀に入ると、突如として北ヨーロッパでボタン――より正確にはボタンとボタン穴――が出現した。この、あまりにも単純かつ精巧な組み合わせがどのように発明されたのかは、謎である。》
この『ねじとねじ回し』という本、11月16日の神戸新聞「正平調」に紹介されていたもの。
《理化学研究所などが科学の名著を紹介するブックレット「科学道100冊2019」をつくった。大人になる前に出会ってほしい本を理研の全職員に尋ねたうえで選んだといい、ホームページからでも見られる。》とあり、『ねじとねじ回し』はその中の一冊。
わたしももっと若い日に読みたかった。
本はこう続く。
《このきわめて単純な仕掛けを作り出すのに必要とされた発想の一大飛躍たるや、たいへんなものである。ボタンを留めたりはずしたりするときの、指を動かしたりひねったりする動きを言葉で説明してみてほしい。きっと、その複雑さに驚くはずだ。ボタンのもう一つの謎は、それがいかにして見出されたか、である。だって、ボタンが徐々に発展していった様子など、とても想像できないではないか。つまり、ボタンは存在したか、しなかったかのどちらかしかないのだ。いったい誰がボタンとボタン穴を発明したのか知らないが、この人物――女性と考えるのが現実的だろう――は天才だったにちがいない。》

51ページにこんなことが書かれている。
《寒さを防ぐ便利な道具であるにもかかわらず、人類は歴史のほとんどの期間を通じて、ボタンを知らずに過ごした。(略)日本人は着物を帯で締めていた。(略)13世紀に入ると、突如として北ヨーロッパでボタン――より正確にはボタンとボタン穴――が出現した。この、あまりにも単純かつ精巧な組み合わせがどのように発明されたのかは、謎である。》
この『ねじとねじ回し』という本、11月16日の神戸新聞「正平調」に紹介されていたもの。
《理化学研究所などが科学の名著を紹介するブックレット「科学道100冊2019」をつくった。大人になる前に出会ってほしい本を理研の全職員に尋ねたうえで選んだといい、ホームページからでも見られる。》とあり、『ねじとねじ回し』はその中の一冊。
わたしももっと若い日に読みたかった。
本はこう続く。
《このきわめて単純な仕掛けを作り出すのに必要とされた発想の一大飛躍たるや、たいへんなものである。ボタンを留めたりはずしたりするときの、指を動かしたりひねったりする動きを言葉で説明してみてほしい。きっと、その複雑さに驚くはずだ。ボタンのもう一つの謎は、それがいかにして見出されたか、である。だって、ボタンが徐々に発展していった様子など、とても想像できないではないか。つまり、ボタンは存在したか、しなかったかのどちらかしかないのだ。いったい誰がボタンとボタン穴を発明したのか知らないが、この人物――女性と考えるのが現実的だろう――は天才だったにちがいない。》