【 車谷長吉展 】

姫路文学館から招待券をお送りいただきました。
車谷長吉展が6月22日まで開催されています。
明日から姫路文学館で「車谷長吉展」が開催されるとのこと。

車谷に関してのことが載っている本がある。
私家版なので目にした人は少ないであろう。図書館にも置かれていない。

著者の日高氏は車谷と12年間学窓を共にした人。
氏は車谷の小説にモデルとして登場している。
池田市の中尾さんから「大和通信」第129号をお贈りいただきました。

表裏に印刷された新聞仕立て。数人の文人がそれぞれ滋味のある文章を載せておられます。
すぐに読めてしまうのがありがたいです。
編集工房ノア社主の涸沢さんの「粟津謙太郎が残したもの」は興味深かったです。
先ず「私は大阪文学学校の小説コース、川崎彰彦クラスに入った」というのにちょっと驚きました。
そうでしたか。詩を書いておられたのかなと思ってましたが小説でしたか。
愉快だったのは当銘広子さんの「水仙」というエッセイ。何とも言えないユーモアが漂っています。
中尾さん、いつもありがとうございます。
imamuraさんの本。 『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。
短歌誌『六甲』に連載している「昭和文人の手蹟」がこの3月号で30回になりました。
わたしが所持している文人の直筆書簡を中心にご紹介しているのですが、これまでの登場人物を書いておきます。
堀口大学、三島由紀夫、竹中郁、永井龍男、吉井勇、江戸川乱歩、まど・みちお、椎名麟三、荻原井泉水、壷井栄、壷井繁治、石坂洋次郎、佐多稲子、田辺聖子、大佛次郎、菊田一夫、火野葦平、大下宇陀児、横溝正史、三好達治、志賀直哉、宮本顕治、津高和一、足立巻一、森田たま、舟橋聖一、杉本苑子、土岐善麿、青柳瑞穂、時実新子。
以上30人。
まだまだ有名文人の書簡があります。元気で紹介していきたいと思っています。
全部紹介するには、毎月一人なら、90歳を過ぎそうですが。
imamuraさんの本。 『完本・コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。
今朝の神戸新聞、文化欄に野元正さんの新刊が紹介されていました。

『こうべ文学逍遥 花と川をめぐる風景』(野元正著・神戸新聞総合出版センター・1980円)です。
野元さんは今、短歌誌「六甲」に「花を巡る文学逍遥」というのを連載されてます。
そのことこの前このブログでちょっと触れました。
9月末発売が待たれます。

『こうべ文学逍遥 花と川をめぐる風景』(野元正著・神戸新聞総合出版センター・1980円)です。
野元さんは今、短歌誌「六甲」に「花を巡る文学逍遥」というのを連載されてます。
そのことこの前このブログでちょっと触れました。
9月末発売が待たれます。
山口県の瀬戸みゆうさんからお贈りいただきました個人誌『半月 すおうおおしま』10+3号です。
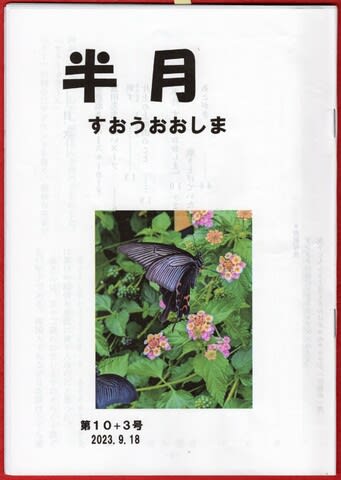
44ページの中に短編小説が4編。
瀬戸さんの著書は以前に『周防大島の青い海』(編集工房ノア刊)という小説集を読ませていただいたことがあり、感動を受けたのでした。
だからその実力のほどは知っております。
昨日須磨へ行くのに電車の中で読もうと携えて行きました。
車中往復一時間ほどですので、全部は読めませんでしたが、もう少しで乗り越しそうになりました。
帰ってから残りを読ませていただきました。
面白かったです。期待通りでした。
最初の「金恵淑さんのJスルーカード」のラスト二行《金さんからもらったJスルーカードは誰○○○○○ことがない。今も○○○○○してある。》
次の「鷲田先生の白いスーツ」のラスト一行。《何も知らない人は○○○だ。》
三作目「刺す」のラスト三行。《わたしたちは電話を切った。すでに真夜中の三時を回っていた。律子は今夜もきっと頭の中で彼を○○○のだ。今夜こそ、きっちりと○○○○。》
○○の部分はご想像ください。
みなそれぞれに趣の違ったスリルを味わわせていただきました。
そして最後の「片上の上の山のこと」は最も長い作品。
作者が今住んでおられる周防大島の中の小さな範囲の、昔からの風習因習などが、幼友達の口を通して事細かに語られる。
部外者には少し冗長な場面もありますが、この地の歴史の記録として貴重なものになる作品だと思いました。
瀬戸さん、貴重な一冊有難うございました。
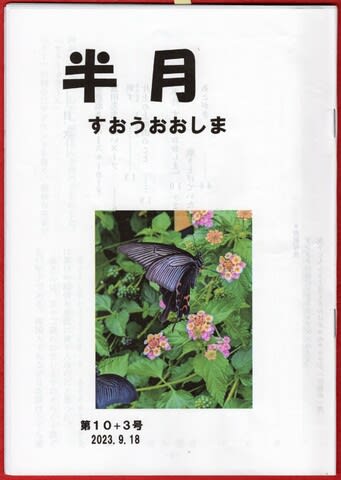
44ページの中に短編小説が4編。
瀬戸さんの著書は以前に『周防大島の青い海』(編集工房ノア刊)という小説集を読ませていただいたことがあり、感動を受けたのでした。
だからその実力のほどは知っております。
昨日須磨へ行くのに電車の中で読もうと携えて行きました。
車中往復一時間ほどですので、全部は読めませんでしたが、もう少しで乗り越しそうになりました。
帰ってから残りを読ませていただきました。
面白かったです。期待通りでした。
最初の「金恵淑さんのJスルーカード」のラスト二行《金さんからもらったJスルーカードは誰○○○○○ことがない。今も○○○○○してある。》
次の「鷲田先生の白いスーツ」のラスト一行。《何も知らない人は○○○だ。》
三作目「刺す」のラスト三行。《わたしたちは電話を切った。すでに真夜中の三時を回っていた。律子は今夜もきっと頭の中で彼を○○○のだ。今夜こそ、きっちりと○○○○。》
○○の部分はご想像ください。
みなそれぞれに趣の違ったスリルを味わわせていただきました。
そして最後の「片上の上の山のこと」は最も長い作品。
作者が今住んでおられる周防大島の中の小さな範囲の、昔からの風習因習などが、幼友達の口を通して事細かに語られる。
部外者には少し冗長な場面もありますが、この地の歴史の記録として貴重なものになる作品だと思いました。
瀬戸さん、貴重な一冊有難うございました。
もう随分前に読んだはずの本、『百貌百言』(出久根達郎著・文春新書・2001年刊)を読んでいる。

困ったもんです。みんな忘れています。
こんな面白い話も。
「井伏鱒二」の項。
《太宰治の「富嶽百景」に、井伏と一緒に三ツ峠にのぼるシーンが出て来る。「井伏氏は、濃い霧の底、岩に腰をおろし、ゆっくり煙草を吸ひながら、放屁をなされた。いかにも、つまらなさうであった」
君、嘘を書いてはいかん、と井伏は太宰を咎めた。放屁なぞしない、と言うと、太宰は笑って、いや、なさいました。一つではなく、二つ、なさいました、と弁明した。》
この、なんともいえない間。味わい。太宰治、見事なものです。
妻に読んでやりました。一瞬の間をおいて、大笑い。

困ったもんです。みんな忘れています。
こんな面白い話も。
「井伏鱒二」の項。
《太宰治の「富嶽百景」に、井伏と一緒に三ツ峠にのぼるシーンが出て来る。「井伏氏は、濃い霧の底、岩に腰をおろし、ゆっくり煙草を吸ひながら、放屁をなされた。いかにも、つまらなさうであった」
君、嘘を書いてはいかん、と井伏は太宰を咎めた。放屁なぞしない、と言うと、太宰は笑って、いや、なさいました。一つではなく、二つ、なさいました、と弁明した。》
この、なんともいえない間。味わい。太宰治、見事なものです。
妻に読んでやりました。一瞬の間をおいて、大笑い。
池田市の中尾務さんからお送りいただきました。
「大和通信」第123号。
今号は、文学に疎いわたしでも読みやすい(読んで楽しい)文章が載ってました。
特に巻頭の、フォークシンガー世田谷ピンポンズさんの「黄昏時に黄色紙を破る」は面白かった。
 ←クリック。
←クリック。
ピンポンズさん、拝借お許しください。
このように軽く仕上げた文章、好きです。
ほかにも、本千加子さん、「懐かしい日々」。当銘広子さん「寒波の日」なども楽しめました。
そして中尾勉さんの「小沢信男 1960年代前半のスランプ」に引用されている小沢の言葉が印象的。
《劣等感が優越感の裏がえしにすぎぬこと》
自戒しなければと思うが、「自戒する」という意識がすでに「優越感」なのかも。
「大和通信」第123号。
今号は、文学に疎いわたしでも読みやすい(読んで楽しい)文章が載ってました。
特に巻頭の、フォークシンガー世田谷ピンポンズさんの「黄昏時に黄色紙を破る」は面白かった。
 ←クリック。
←クリック。ピンポンズさん、拝借お許しください。
このように軽く仕上げた文章、好きです。
ほかにも、本千加子さん、「懐かしい日々」。当銘広子さん「寒波の日」なども楽しめました。
そして中尾勉さんの「小沢信男 1960年代前半のスランプ」に引用されている小沢の言葉が印象的。
《劣等感が優越感の裏がえしにすぎぬこと》
自戒しなければと思うが、「自戒する」という意識がすでに「優越感」なのかも。
神戸新聞、今朝の訃報欄。
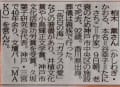
柏木薫さんがお亡くなりになったのだと。
お会いしたことはなかったが、電話をいただいたことがあり、丁寧なお便りもいただいたのだった。
その手紙、今もどこかにあるはずだが、すぐには見つからない。
「柏木薫さん」と題してブログにも書いたことがある。
ご冥福をお祈りいたします。
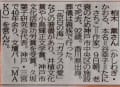
柏木薫さんがお亡くなりになったのだと。
お会いしたことはなかったが、電話をいただいたことがあり、丁寧なお便りもいただいたのだった。
その手紙、今もどこかにあるはずだが、すぐには見つからない。
「柏木薫さん」と題してブログにも書いたことがある。
ご冥福をお祈りいたします。
今朝の神戸新聞。
高島俊男さんを顕彰する石碑が建立されたと。
うれしく、慶賀なことです。機会があれば行ってみたい。
 ←クリック。
←クリック。
高島さんは、喫茶輪に二度ほどご来店いただきました。
一度は宮崎修二朗翁と鈴木漠さんもご一緒でした。


拙著『触媒のうた』にも登場いただいています。
 ←クリック。
←クリック。
日本文学史秘話の重要な件。
高島俊男さんを顕彰する石碑が建立されたと。
うれしく、慶賀なことです。機会があれば行ってみたい。
 ←クリック。
←クリック。高島さんは、喫茶輪に二度ほどご来店いただきました。
一度は宮崎修二朗翁と鈴木漠さんもご一緒でした。


拙著『触媒のうた』にも登場いただいています。
 ←クリック。
←クリック。日本文学史秘話の重要な件。
『流れる雲を友に 園井恵子の生涯』の著者、千和和之さんが名古屋からご来訪でした。
この本のことブログに書いてます。「千和和之さんと千村克子さん」と題して。
千和さんは今、次の本に向けて執筆中ですが、きっと素晴らしい本が出来上がることと思っております。
楽しみです。
今回は池田文庫まで取材に来られた(昨夜大阪に一泊)のですが、我が家まで足を伸ばして下さいました。
お忙しい中、顔を見せて下さりありがたいことです。
お陰で久しぶりに多岐にわたって本談義が楽しめました。
わたしにも大いに刺激になりました。
この本のことブログに書いてます。「千和和之さんと千村克子さん」と題して。
千和さんは今、次の本に向けて執筆中ですが、きっと素晴らしい本が出来上がることと思っております。
楽しみです。
今回は池田文庫まで取材に来られた(昨夜大阪に一泊)のですが、我が家まで足を伸ばして下さいました。
お忙しい中、顔を見せて下さりありがたいことです。
お陰で久しぶりに多岐にわたって本談義が楽しめました。
わたしにも大いに刺激になりました。


























