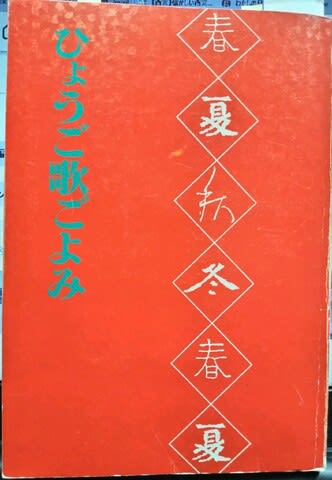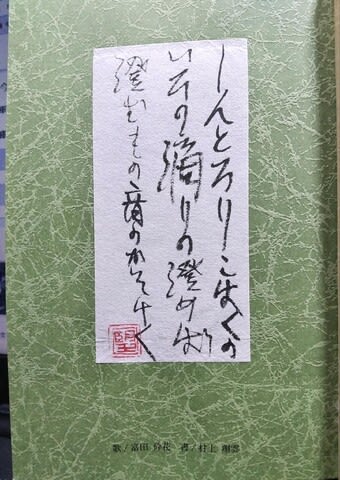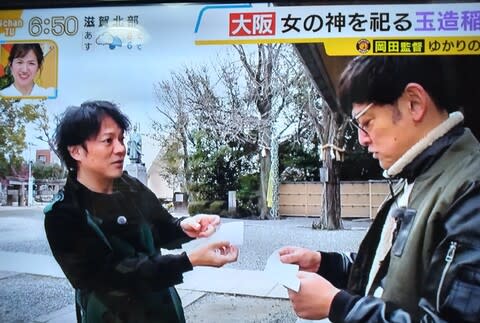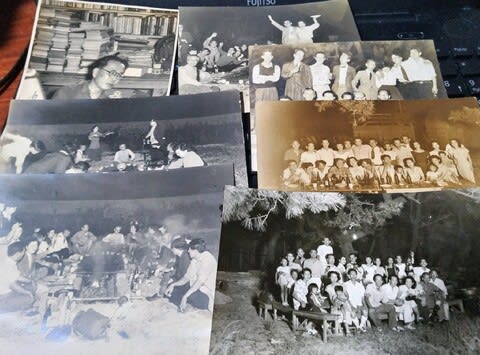今朝の神戸新聞「読書」欄に寺田匡宏さんの本が大きく紹介されています。
寺田さん、ますます立派な人になられて。
彼は一度、宮崎修二朗翁に伴われて「喫茶・輪」にお越しいただいたことがあります。
翁を尊敬しておられ、翁もまた彼を評価し、取材旅行のお供に連れて行かれたりされていました。
こうして次々と大きなお仕事をなしておられる。翁が期待された通りに。
比してわたしは・・・残念。
彼のことは、過去にも何度かこのブログで取り上げています。
今朝の神戸新聞「読書」欄に寺田匡宏さんの本が大きく紹介されています。
寺田さん、ますます立派な人になられて。
彼は一度、宮崎修二朗翁に伴われて「喫茶・輪」にお越しいただいたことがあります。
翁を尊敬しておられ、翁もまた彼を評価し、取材旅行のお供に連れて行かれたりされていました。
こうして次々と大きなお仕事をなしておられる。翁が期待された通りに。
比してわたしは・・・残念。
彼のことは、過去にも何度かこのブログで取り上げています。
今朝の神戸新聞文化欄に「大岡信展」のことが。
これ行きたいですけど、横浜ではちょっと。
私のところに大岡信の巻紙書状があります。
例によって宮崎翁宛のもの。大岡氏が宮崎翁に平身低頭されてます。
見事な文字。

宮崎修二朗翁宛。
この書状は日本の文学史に影響を与えたもの。わたしなんぞが持っていてはいけないものです。
他にも大岡氏からのハガキがあります。いずれしかるべき文学館に寄贈しようと思っています。
この手紙に関することも書いてます。 『触媒のうた』 (今村欣史著・神戸新聞総合出版センター刊) 楽しい文学史秘話が満載。
「先山鐘銘」のページです。
この村上翔雲さんの文章を読むと、拓本取りの苦労が解るというものです。
そしてこの本の値打ちも。
村上翔雲師と宮崎修二朗翁のお二人は、二年間かけて兵庫県を駆けずり回ってこの本を成されたのでした。
どの拓本も宮崎修二朗翁が翔雲師と共に採拓しておられますが、苦労が忍ばれます。
わたしも一度、翁の採拓するところを見せてもらったことがありますが、根気のいる仕事でした。
因みにその拓本は、足立巻一先生を語る講演で使われた後にわたしに授けられ、今も書斎に飾っています。
播磨中央公園に建つ足立巻一先生の文学碑からのもの。