
文芸春秋社刊「驚異への旅・古代日本七不思議」の中の金達寿(きむたるす)が書いている「法隆寺と聖徳太子の正体は何か」という文章を読んでみました。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
私がはじめて大和の法隆寺を訪ねたのは1949年春であった。
そのころはバスの中から、あるいは近鉄筒井駅からの徒歩で、そこに法隆寺の塔が見えてくると、わたしはそれだけで、もう胸がときめいたものである。
このような胸のときめきは、今もそう変わりはないが、しかし何度も行って、見ているうちに、それもだんだん薄れたものとなってくるのはやむをえない。
熱烈に愛した恋人に対するそれと同じなのであろうか?
その代わり、これも恋人に対するそれと同じように、少しは相手のことが分かってくる。
この場合の相手とは、もちろん法隆寺のことであるが、同時にまた、それまでは思ってもみなかったことで、分からないこともたくさん出てきたようだ。
今はむしろ、その分からないことの方が多い。
たとえば梅原猛氏の「隠された十字架」によると「法隆寺の建立の由来は、一族を皆殺しにされた聖徳太子の怨念を封じ込めるためだった」というのであるが、
あるいはそうであったかもしれないし、そうではなかったかもしれないと思う。
つまりそれよりも、私にとって興味があるのは、それはどちらにせよ、法隆寺と密接な関係にあることだけは確かな聖徳太子とは、そもそもどういう人であったのか、ということである。
古代史家としてもすぐれた仕事を残した坂口安吾によれば、「厩戸皇子(うまやどのみこ)」と呼ばれた聖徳太子は、百済、新羅とともに古代朝鮮三国の一国であった「高句麗系」の人であったらしく、高句麗と交通して文物を取り入れた」と言っている。
しかしこれも、私にはよく分からないところがある。
なるほど聖徳太子の師は、高句麗系の僧であったことがはっきりしているから、あるいは、も
しかすると、そうかもしれないとも思う。
それからまた止利仏子(とりぶっし)の作とされている、法隆寺の金堂の「釈迦三尊仏」であるが、これもよく見ると高句麗系のものではないかと思われる。
東京国立博物館・東洋館の朝鮮美術室にある「二仏並座像」は「高句麗・6世紀出土」と説明されているが、これが法隆寺の「三尊仏」と実によく似ている。
どう見ても、三仏の原型はこの二仏座像ではなかったかと思われる。
さらにまた、法隆寺となると決して忘れてはならないものに、中国の雲崗石仏や朝鮮の慶州石窟とともに、東洋三大芸術の一つと言われている「金堂の壁画」がある。
この壁画を画いたのは、今日の劇場などで見る壁画様の垂れ幕を「緞帳(どんちょう)」と言っているのも、その名からきているという「曇徴(どんちょう)」であったとされている。
広辞苑によると
「曇徴 高句麗の帰化僧。
推古天皇18年に来朝。
五経に通じ、彩色画をよくし、紙、墨、碾き臼などを造った。法隆寺の壁画を描いたという」
とある。
推古18年は、610年である。
しかし一方、聖徳太子は京都の太秦にある広隆寺を氏寺としていた新羅系の秦一族とも密接な関係にあった。
太子の愛妻であった橘大郎女(たちばなのおおいらつめ)は新羅の工神を祖としているいなべ橘王(たちばなのおおきみ)から出ている。
それだけではない。
上田正昭氏によると、「曽我氏の仏教が百済系であったのに対して、聖徳太子の方は新羅系だというのが僕の解釈です」と言っている。
ところが聖徳太子は一方でまた百済とも密接な関係にあった。
法隆寺そのものとしては、百済の要素が非常に強い。
法隆寺は百済様式の寺院であると言っても良いくらいである。
法隆寺には有名な「百済観音」というものがあるが、これの本来の名称は「観世音菩薩立像」である。
それがどうして「百済観音」と言われるようになったのか?
いろいろな説があるようだが、いずれにせよ、それが「百済」との関係によって生じたものであることは間違いない。
聖徳太子と百済との関係は、百済観音がそこにあるという、そんな形のみではない。
われわれが日常使用している旧5000円札や10000円札の太子像の元になっているのは、法隆寺にあった阿佐太子筆「聖徳太子御影」というものである。
阿佐太子は、597年・推古5年に日本へやってきた百済の王子であるので、これはただ単にその「御影」を描いたというだけではない。
阿佐太子によって、聖徳太子は、百済にだいぶ引き寄せられた。
そればかりか、聖徳太子は中国の隋に目を向けるようになった。
つまりそのような国際的視野をもつにいたったのも、阿佐太子によってであったとされている。
聖徳太子は、秦氏族との関係に見られるように、新羅とも結んだが、後には百済の阿佐太子とも結ぶことによって、中国の隋までその視野を広げた。
日本仏教文化の一大記念碑である法隆寺は、そのような聖徳太子の文化的・政治的思考の記念碑であるとも見られなくはない。
(引用ここまで)
*****
うーん、名文であります。
こういう文章を読むのは、快楽であります。
無理難題を解こうとする日ユ同祖論に辟易していたわたしには、一服の清涼剤でありました。。
 wikipedeia「阿佐太子」より
wikipedeia「阿佐太子」より阿佐太子(あさたいし、アジャテジャ、6世紀末 - 7世紀前半頃)は、百済の王族出身画家で、威徳王の息子。
『日本書紀』によれば、推古天皇5年(597年)4月に日本に渡って聖徳太子の肖像を描いたと言われる。
奈良の法隆寺に伝来し、明治以降は御物となっている『聖徳太子二王子像』と呼ばれる絵は、日本で一番古い肖像画とされている。
その形式は中央に太子が立ち、その左右に2人の王子(伝えられるところによれば、右側が山背大兄王、左側が殖栗王)を小さく配置した構成である。
この配置は、仏教の三尊仏形式の影響を受けたとも考えられ、あるいは閻立本の作とされる初唐の『歴代帝王図巻』に見られる人物配置に似ることから、その頃の構図法に起因したものと解釈されることがある。
日本学界でも論議が多いこの像は、製作時期においても太子の冠の様式や太子及び王子の服飾から見て、8世紀(奈良時代)の作品だと見る説と、平安時代以降の模本と見る説が概して多い。
このように現在伝えられる聖徳太子像の作者および制作時期は、様式上の問題点と同時に、阿佐太子に対する記録が韓国側資料にはないという事実によって、未解決の課題である。
ブログ内関連記事
 「日本の不思議(古代)」カテゴリー全般
「日本の不思議(古代)」カテゴリー全般












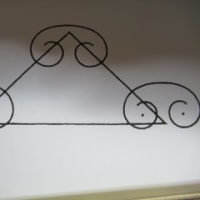


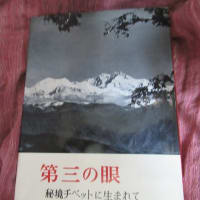







「新撰姓氏録」によると神武天皇の兄である稲氷命が新羅の祖(朴氏の始祖で初代王の赫居世居西干)
「三国史記」によると新羅の建国時に諸王に仕えた重臣である瓠公は日本人(倭人)
「三国遺事」によると「朴」は辰韓の語で瓠を意味する(朴氏の始祖である赫居世居西干と瓠公は同族とする説がある)
「古事記」「日本書紀」によると赫居世居西干の次男アメノヒボコが日本の但馬国に移住
「三国史記」によると昔氏の始祖で第4代王の脱解尼師今は日本人(多婆那国の出身。多婆那国の場所は日本の但馬あたりという見方がある)
「三国史記」によると新羅三王家の一つ金氏の始祖である金閼智を発掘したのは瓠公(朴氏昔氏瓠公も全て日本人なので金氏も…)
名無し 様
コメントをどうもありがとうございました。
お返事が大変遅くなり、申しわけございません。
貴重な記述をありがとうございます。
たいへん興味深く拝見しています。
このブログでも、朝鮮半島の文化と古代日本の文化の関係については、たくさん考察しているつもりですが、調べれば調べるほど、両者の関わりは深く、切っても切れない関係であるように思っております。
他にもたくさんありますが、以下でも、対馬の天道信仰と朝鮮半島の伝統と天照大神の関連について考えております。
「アマテルとアマテラス(1)・・日の神アマテラスと、月の神」
http://blog.goo.ne.jp/blue77341/e/6cab841c399746a18681d4a792f3e377
「アマテルとアマテラス(2)・・天道信仰とアメノヒボコ」
http://blog.goo.ne.jp/blue77341/e/4bd7916a0a24b7365a371da85f835baf
「太陽、舟、うずまき、円・・アマテルとアマテラス(3・終)」
http://blog.goo.ne.jp/blue77341/e/108285669368d16fee681d0468daf444