
ゾロアスター教の根本聖典「アヴェスター」(伊藤義教氏訳)を読んでみました。
この聖典は、世界最古の聖典と考えられ、紀元前から口承で伝えられてきたものが、ササン朝ペルシア時代に編纂されたものであるということです。
原本は本来の4分の1しか残っていないということですが、残された部分はアヴェスター語という古代ペルシア語で書かれ、ゾロアスター本人の言葉を含んでいると考えられています。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
始めに、登場する天使たちの説明をウィキペディア「ゾロアスター教」の項目から引用させていただきます。
・・・・・
(引用ここから)
アフラ・マズダーと“善神”群
アフラ・マズダーは、ゾロアスター教の主神で、みずからの属性を7つのアムシャ・スプンタ(七大天使、不滅なる利益者たち)という神々として実体化させ、天空、水、大地、植物、動物、人、火の順番で創成した、世界の創造者である。
アフラ・マズダーを補佐する善神(アムシャ・スプンタ)としては、次の7神がある。
•スプンタ・マンユ : 「聖霊」を意味する人類の守護神で、アフラ・マズダーと同一視されることもある。
•ウォフ・マナフ : 「善なる意思」を意味し、動物界の統治者でアフラ・マズダーのことばを人類に伝達する役割をになっている。
常に人間の行為を記録しており、やがて訪れる「最後の審判」でその記録を詠みあげるとされる。
•アシャ・ワヒシュタ(アシャ) : 「宇宙を正しく秩序づける正義」に由来し、天体の運行や季節の移り変わりをつかさどる。
「聖なる火」の守護神。虚偽の悪魔ドゥルジに対峙する。
•アールマティ : 代表的な女神(女性天使)。「献身」「敬虔」の名の通り、宗教的調和や信仰心の強さ、さらに信仰そのものを顕現する。
大地の守護神となっており、「背教」と「推測」の悪魔タローマティと対立する。
•クシャスラ(フシャスラ・ワルヤ) : 「理想的な領土ないし統治」に由来し、「天の王権」を象徴する。
アフラ・マズダーによる「善の王国」建設のために尽力する。
金属ないし鉱物の守護神。
•ハルワタート : 「完璧」を意味する女性の大天使。
アムルタートとは密接不可分とされる。水の守護神。
•アムルタート : 主神アフラ・マズダーの子で、名は「不死」に由る。
植物の守護天使で、ハルワタートと力を合わせて地上に降雨をもたらす。
また、善神の象徴は「炎」とされ、そこから「火の崇拝」が生まれている。
(引用ここまで)
・・・・・
次に、聖典「アヴェスター」から「ヤスナ」という、最も古い時代に書かれたと推定される祈祷書を少しだけ、ご紹介します。
カッコ内の属性は、わたしが加筆しました。
****
(引用ここから)
「ヤスナ第28章」
「スプンタ・マンユ(聖霊・人類の守護神)のこの御助けを、マズダーよ、、御身たちすべての方々に、私はうやうやしく手を伸ばし、天則に従い、行動をもって、まず第一に懇願いたします。」
「すなわち、ヴォフ・マナフ(善なる意思)の意思と牛の魂とを、私が満足させうるところの行動をもってです。」
「マズダー・アフラよ。」
「善思をもって御身たちをつつみまいらせようとする私に、天則に従って授けてください。」
「有象の世界と心霊の世界となる両世界の恩典を、その恩典によって、御身様が助力者たちを楽土に置き給うことのできんためです。」
「アールマティ(敬虔な女神)が国土を不壊に栄えさせてゆくのも、ヴォフ・マナフ(善なる意思)と始めなきマズダー・アフラとの御為ですが、この御身たちを、天則に従い讃頌しようとする私の下へ、呼び声に応じて、御身たちは助けに来てください。」
「ヴォフ・マナフ(善なる意思)と一体になって魂を覚醒させようと心に銘記し、またマズダー・アフラよ、アフラの下し給う行為の応報を知悉している者として、私は力あり、またよく成し得る限り、どこまでもアシャ(正義)を求めることに教化をおいていきましょう。」
「アシャ(正義)よ、御身を、献身者として私は、果たして見たてまつるでしょうか?」
「またヴォフ・マナフ(善なる意思)を、そして王座を、最も強きアフラ・マズダーの高諾をも、見たてまつるでしょうか?」
「あらゆるものの内にて最大なるその高諾へと、この祈呪によって、舌をもって、我らは仇なす輩を改宗させたいのです。」
「ヴォフ・マナフ(善なる意思)と共に、御身は来てください。」
「そして天則に従って授けてください、永劫の授けものを。」
「まことに崇高な御言葉をもって、マズダーよ、力強い御助力を、ツァラツストラなる私にです。」
信徒の唱和
「そして我らにも、アフラよ。
我らが敵人どもを克服するために。」
「御身は授けて下さい、アシャ(正義)よ、かのヴォフ・マナフ(善なる意思)の恩恵を。」
「御身はまことに授けて下さい、アールマティ(敬虔な女神)よ、強健さをウィーシュタースパに、そして私にも。」
「御身はまことに授けて下さい、アフラ・マズダーよ、そして自在に操って下さい、御身たちの預言者、ゾロアスターなる私が、よってもって人々の聞信を博するようになるところのものを。」
「最勝なるものを、御身最勝者、最勝なるよき天則と同心にまします御身、アフラ・マズダーに、私は懇願いたします。」
「私は望んできた者です。壮士のために、そして私のために、
かつまた、御身がかりそめにも恵み施されようとする人々のために、いつの日までもヴォフ・マナフ(善なる意思)のものたるその最勝なるものをです。」
「これらの懇願をもって、我らが怒らしめたくないのは、アフラ・マズダーよ、御身たち、御身と天則と最勝なるヴォフ・マナフ(善なる意思)と恩恵の王国とですが、
その我らは、讃嘆を御身たちに捧げるために着座している者、御身たちは最も迅速なる賦活者にましますのです。」
「では、人々にして、正信のゆえに正しいものと御身が認めたまい、また善思のゆえにふさわしい者と、アフラ・マズダーよ、御身が認めたまうなら、その者共の所願を果たさせて充たしてやってください。」
「そうすれば、御身たちへの聖歌、御身たちにとって得るところ多く、ふさわしい、称讃の聖歌を、私は知っているのです。」
「称讃の聖歌とともに、正信と善思をも永遠に留め置きたまう御身は、アフラ・マズダーよ、私が人々に説ききかすために、私に教えてください、御身のスプンタ・マンユ(聖霊)を通して、御身の口をもって、第一の世界がいかなるものになりゆくであろうかを。」
ヤスナ第28章終わり
(引用ここまで)
*****
編纂されたものとしては、世界最古の教典ということで、大変興味深く思いました。
翻訳者の伊藤義教氏は、ゾロアスター教の研究の第一人者でいらっしゃるようですが、同氏の論文集「ゾロアスター研究」には、さまざまなことが書かれていました。
「ゾロアスターは啓示を下した神の前に自身を低くして終生変わらなかった。
彼はあくまで「神の言葉」を述べ伝えるものとの立場から、「わたくしは語ろう」というときにも、「神の言葉を述べ伝えよう」という表現を用いた。」とあり、魔術師ゾロアスターというよりは、非常に倫理性の強い人格を感じました。
古代における倫理とは、どれほど精神の鍛錬が必要であっただろうかと思います。
宗教や疑似宗教があふれている世界で、どれが正しいかと考えるのと違って、「真理そのもの」を自分の力で探究し、掴まなくてはならないのですから。
世界の大宗教の原型と言われるだけのことはあると思いました。
 wikipedia「アヴェスター語」より
wikipedia「アヴェスター語」よりアヴェスター語とは、ゾロアスター教の聖典『アヴェスター』に用いられた言語。
インド・ヨーロッパ語族のサテム語派の代表的な言語であり、インド・イラン語派イラン語群東部方言に分類される。
実際に話されていた場所や時代は定かではないが、言語学その他による検証により、 紀元前7世紀頃のイラン東南部の言語とする説が有力。
現存する最古の史料はサーサーン朝ペルシア末期、6世紀頃の物で、それ以前は 口承伝持で伝えられてきたと考えられる。
分類
アヴェスター語は更に、開祖ザラスシュトラ自身の作と思われるガーサー(英語版) (Gāθā、詩)に用いられるガーサー語(Gathic Avestan, 古代アヴェスター語 - Old Avestanとも)と、後年弟子や信者達によって付け加えられた部分に用いられる新体アヴェスター語に分けられる。
ガーサー語はより古い言語、新体アヴェスター語はより新しい言語と思われ、音韻や文法などに若干の相違がある。
文字
表記にはアヴェスタ文字が用いられる。
これはパフラヴィー語と同じくアラム文字を元に、6世紀頃創作された文字で、母音や子音の微妙な相違まできちんと表記できる、イラン諸言語で用いられた文字としては唯一の例として知られる。
サンスクリットとの関係
インドのサンスクリット語とは極めて近縁の言語で、特にサンスクリットの最古層であるヴェーダ語(『リグ・ヴェーダ』などに用いられた言語)とは文法的にも酷似している。
そのため、俗に「アヴェスターをヴェーダ語に翻訳するには、一定の規則に従って個々の音を置き換えるだけで良い」と言われるほどである。
 関連記事
関連記事
「ブログ内検索」で
天使 12件
精霊 15件
牡牛 5件
ゾロアスター 15件
チャネリング 14件
などあります。(重複しています)
















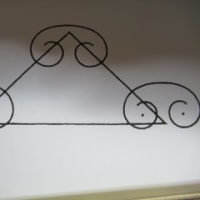







たしかリグ・ヴェーダ全訳とアヴェスタが収録されたお得な版だった気がします。
買っておけばよかったかなぁ
かがみん様
こんばんは。
コメント、どうもありがとうございました。
アヴェスターを、見かけておられたのですね。
わたしは、文庫版になっている、伊藤義教氏の翻訳本をはじめて読みました。
リグ・ヴェーダとアヴェスターがセットになっていた、ということですが、ヴェーダ語とアヴェスター語は非常に近い、ということをウィキペディアで知り、イランとインドの関係について、また思いをはせてしまいました。
西洋から見たら、どちらも東洋なのでしょうけれど、日本などから見ると、インドは東洋でイランは中東で、まったく別の文化のように思えますが、東洋と西洋はもっともっと深いところで、分かちがたくつながっているのではないか、と思わずにいられません。