京都新聞正月3日紙上に、京セラ名誉会長の稲盛和夫氏のインタビュー記事が載っていました。見出しは「歴史的な大転換期 欲望肥大化 修正必要」
この記事の最後で、稲盛氏は「歴史的転換期にどういう生き方をしないといけないか、理屈抜きに考えないといけない。わたし個人、今年は僧としてまた托鉢(たくはつ)を再開しようかと思っている」
托鉢は、僧侶が鉢をたずさえて町や村を歩き、食を乞うこと。古くは持鉢・棒鉢ともいい、乞食こつじきと称した。乞食のひとつの流れは、佛教にあります。
何も恥ずべき行為ではなく本来、僧侶が当然なすべき行いであったのです。「行き暮れて宿もなき時は、野にも伏し、山にも伏し、打飯切れますれば鉢もいたし、鉢ござらねばひだるき事を、度々こらへまする」<盤珪仏智弘済禅師御示聞書>。ひだるき事:非常なる空腹。こらへ:堪え。
お釈迦さん、わたしはいつも釈尊とよびますが、彼は衣食住のすべてにおいて、少欲知足の修業「頭陀行」ずだぎょうを定めました。
このなかの乞食行では、必ず托鉢によって得た食をとることと定めています。また托鉢先の貧富の別なく、順次に家を訪ねて托鉢すべし。このふたつが釈尊のいう乞食の意味です。彼は僧が守るべき基本に、布施の食を受ける乞食行を据えました。修業出家者は、比丘・比丘尼(びく・びくに)ですが、原語の語義は食べ物を乞う者だそうです。
佛教語「ピンダ・パータ」托鉢食、「ピンダ・パーティカ」施された食べ物を食べる人は、中国で「乞食」と漢訳されました。「乞丐」きつがい字も当てられています。
日本では古くから「乞食」こつじき、「乞者」こつしや、「乞丐」こつがい字を用いる。頭陀ズータとは、煩悩の損滅をいうとあります。
「乞者来たりて法華経の一品をよみて食を乞ふ」<三宝絵詞>
ところで、稲盛氏の托鉢は、上記同様であろうか。四国八十八箇所の巡礼・遍路かもしれぬと思う。四国では物乞いをもっぱらとした遍路を、「へんど」というそうです。辺土あるいは辺道でしょうか。
「われらが修業せし様は、忍辱(にんにく)袈裟をば肩に掛け、また笈(おひ)を負ひ、衣はいつとなくしほたれて、四国の辺道(へち)をぞ常に踏む」<梁塵秘抄>
<2010年1月4日 参考『岩波仏教辞典> [203]










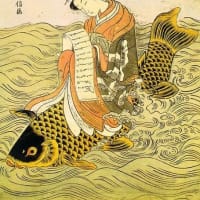



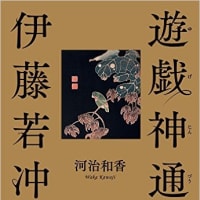






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます