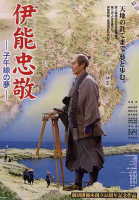今日(4月19日)は、「地図の日,最初の一歩の日」
1800(寛政12)年閏4月19日、伊能忠敬(いのうただたか)が蝦夷地(北海道)へ最初に測量に出発した日。
伊能忠敬(本名、神保三治郎)は1745(延享2)年、上総国に生まれ、佐原の伊能家の養子となり、忠敬と名を改め、造酒業、米穀の取引など家業に精を出すとともに名主として村政にも力をつくした。彼が伊能家に来た時、家業は衰え危機的な状態だったが、倹約を徹底すると共に、本業以外にも、薪問屋を江戸に設けたり、米穀取り引きの仲買をして、約10年程で完全に経営を立て直したという。又、1783年、彼が38歳の時、天明の大飢饉では、私財をなげうって地域の窮民を救済し、こうした功績が幕府の知るところとなり、彼は苗字・帯刀を許されたのだという。彼は、近代日本地図の始祖として有名だが、経営手腕もたいしたものだったのですね~。
その後、1795年(寛政7年)50歳で、家督を長男に譲り、幼い頃から興味を持っていた天文学を本格的に勉強する為に江戸深川に移り住み、19歳も年下の幕府天文方・暦学者の高橋至時(たかはし よしとき)の門下に入り、そこで天文学の知識を学んだ。
1800(寛政12)年閏4月19日、忠敬56歳を数える頃、彼は3人の若い弟子と2人の従者を引き連れ、蝦夷地へ測量に出発するのであるが、この時期、幕府は、北方からの脅威に神経を尖らせていた。何故なら、17世紀以来、アジア進出を開始していたロシアが、このころ、その船を千島や日本海に出現させ、かつ、蝦夷地に来て通商を求めるような事件すら起こっていたのである。そして、幕府は、ロシアの進出を食い止めようと、北辺の防備を強化する一方、年は若いが、優れた天文方であった高橋至時の提案を入れて、地図作成の測量を、至時の老弟子伊能忠敬に命じたのである。ところが、その時、伊能忠敬を送り出した、至時の主目的は、別のところにあった。彼は、子午線上の一度の距離、つまり、緯度一度の距離を実測することで地球の大きさを計算し、それによって、正確な暦を作ろうとしたのである。忠敬もよくこのことを承知していたため、忠敬一行は、江戸から、海路で蝦夷地へ向かうようにとの幕府の提案を、忠敬は測量や地図製作の費用を自費でまかなうという条件で、説得し、多額の自費を注ぎ込み、往復ともに陸路、つまり、南北に長い奥州街道を北へ直行して蝦夷地に渡ったのである。
至時が期待したのは、主に、天文学上の必要からの測量行であったが、幕府へ上程した蝦夷地南岸の地図はその巧妙さで幕府役人たちを感心させ、一応の成功を収めた。
忠敬はこの蝦夷地に行って実測を始めたときに、全国図の完成を考え始めたのであろう。その後、72歳まで、18年間を費やして、日本全国の測量を敢行。実測による日本初の全国図「大日本沿海輿地全図」の作成に取り組むも1818年に死去。地図の完成は彼の没後3年を経て、1821(文政4)年、門弟らの手によってなる。この地図は、明治から大正に掛けて、教育用、産業用、軍事用に使われ大いに真価を発揮した。
経営面でもやり手の忠敬は、50歳になると、さっさと隠居し、長男に家督を譲り、自分のしたいことの為に没頭した。今時、よく、サラリーマンなどに、定年後、何をしてよいか判らないなどと言って、余り、自分の望みでもないような職業について、老後を過ごしている人も多いのではないだろうか。折角、長い間、自分のしたいことも出来ないまま、家族の為に一生懸命働いてきたのだから、定年後の余生くらいは、自分のしたいことをして過ごせば良いのにと思うが・・・。その意味でも、伊能忠敬という人は、サラリーマンなどのモデルにしても良い人だね~。
忠敬の測量の基本は、歩測と磁石と三角法。自分で一歩一歩地面を踏みしめながら、その一歩一歩が地図作りの貴重なデータを生み出していく。伊能忠敬の一歩は69cmだったという。江戸以前の人々の履き物は「下駄」にしても「草履」にしても踵がない。ある人が実験した結果、これらの履物で、フラット着地で歩くと、歩幅は狭くなり、踵をつかず一定のスピ-ドを保って歩ける最大歩幅を探しながら歩いた歩幅は69cm弱になった。自分の記録75cm(通常歩行)、72cm(なんば歩行・踵着地)ではなく、伊能忠敬の歩幅と云われる69cmにほとんどぴったりと重なってしまったという。(以下参考の「nanba なんば歩行 」を参照。)
私も、色々な仕事をしてきたが、ある仕事で、デパーなどの売り場や駐車場の敷地面積を、自分の歩幅で調べたことがある。よく床にピータイルといわれるものが貼られている場合、それは30cm四角のものが多く、その枚数を数えれば判るのだが、それが貼られていないときなど、その倍の60cmを基本に歩く練習をした上で、現地で歩数を数えるのである。同じところを2度歩いて、同じ歩数で歩いていれば、ほぼ正確である。2度歩くのは検算のようなもの。人間て、訓練するとほぼ同じ歩幅で歩くことが出来る。歩数で距離は計算出来るのだ。しかし、そのため、伊能忠敬ですら一日に10kmほどしか測量できなかったと言われている。
そして、曲がり角では方位を計測し、坂道では傾斜角を計測する。こうして集めた数値データを集計することで、きわめて正確な地図を作り出していく。測量方法そのものに新しさや独創性はないそうだが、忠敬のすごさは測量地点を多く取って測量の正確を期したこと。測量自体は小さな地味な仕事だが、それが積もり積もるとこんな大きなことが出来上がる。正に、根気と努力の賜物といえるだろう。
日本で最初の近代測量地図を作った伊能忠敬の伝記映画「伊能忠敬子午線の夢-」は、劇団俳優座創立55周年記念作品として製作され、映画では、このねばり強さを、忠敬の身体に流れる“農民の血”から生まれたものとして描き、主演・加藤剛が好演している。
(画像は映画「伊能忠敬」-子午線の夢-東映。ポスター)
参考:
神戸市立博物館:伊能忠敬の日本地図展
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/57/museum/tokuten/2004/01_ino.html
伊能忠敬記念館
http://www.sawara.com/tadataka/
伊能忠敬の略年譜
http://www2s.biglobe.ne.jp/~auto/nenpu.html
nanba なんば歩行
http://www.isone-sekkei.com/hosaka/hosaka2/nanba/nanba.htm
1800(寛政12)年閏4月19日、伊能忠敬(いのうただたか)が蝦夷地(北海道)へ最初に測量に出発した日。
伊能忠敬(本名、神保三治郎)は1745(延享2)年、上総国に生まれ、佐原の伊能家の養子となり、忠敬と名を改め、造酒業、米穀の取引など家業に精を出すとともに名主として村政にも力をつくした。彼が伊能家に来た時、家業は衰え危機的な状態だったが、倹約を徹底すると共に、本業以外にも、薪問屋を江戸に設けたり、米穀取り引きの仲買をして、約10年程で完全に経営を立て直したという。又、1783年、彼が38歳の時、天明の大飢饉では、私財をなげうって地域の窮民を救済し、こうした功績が幕府の知るところとなり、彼は苗字・帯刀を許されたのだという。彼は、近代日本地図の始祖として有名だが、経営手腕もたいしたものだったのですね~。
その後、1795年(寛政7年)50歳で、家督を長男に譲り、幼い頃から興味を持っていた天文学を本格的に勉強する為に江戸深川に移り住み、19歳も年下の幕府天文方・暦学者の高橋至時(たかはし よしとき)の門下に入り、そこで天文学の知識を学んだ。
1800(寛政12)年閏4月19日、忠敬56歳を数える頃、彼は3人の若い弟子と2人の従者を引き連れ、蝦夷地へ測量に出発するのであるが、この時期、幕府は、北方からの脅威に神経を尖らせていた。何故なら、17世紀以来、アジア進出を開始していたロシアが、このころ、その船を千島や日本海に出現させ、かつ、蝦夷地に来て通商を求めるような事件すら起こっていたのである。そして、幕府は、ロシアの進出を食い止めようと、北辺の防備を強化する一方、年は若いが、優れた天文方であった高橋至時の提案を入れて、地図作成の測量を、至時の老弟子伊能忠敬に命じたのである。ところが、その時、伊能忠敬を送り出した、至時の主目的は、別のところにあった。彼は、子午線上の一度の距離、つまり、緯度一度の距離を実測することで地球の大きさを計算し、それによって、正確な暦を作ろうとしたのである。忠敬もよくこのことを承知していたため、忠敬一行は、江戸から、海路で蝦夷地へ向かうようにとの幕府の提案を、忠敬は測量や地図製作の費用を自費でまかなうという条件で、説得し、多額の自費を注ぎ込み、往復ともに陸路、つまり、南北に長い奥州街道を北へ直行して蝦夷地に渡ったのである。
至時が期待したのは、主に、天文学上の必要からの測量行であったが、幕府へ上程した蝦夷地南岸の地図はその巧妙さで幕府役人たちを感心させ、一応の成功を収めた。
忠敬はこの蝦夷地に行って実測を始めたときに、全国図の完成を考え始めたのであろう。その後、72歳まで、18年間を費やして、日本全国の測量を敢行。実測による日本初の全国図「大日本沿海輿地全図」の作成に取り組むも1818年に死去。地図の完成は彼の没後3年を経て、1821(文政4)年、門弟らの手によってなる。この地図は、明治から大正に掛けて、教育用、産業用、軍事用に使われ大いに真価を発揮した。
経営面でもやり手の忠敬は、50歳になると、さっさと隠居し、長男に家督を譲り、自分のしたいことの為に没頭した。今時、よく、サラリーマンなどに、定年後、何をしてよいか判らないなどと言って、余り、自分の望みでもないような職業について、老後を過ごしている人も多いのではないだろうか。折角、長い間、自分のしたいことも出来ないまま、家族の為に一生懸命働いてきたのだから、定年後の余生くらいは、自分のしたいことをして過ごせば良いのにと思うが・・・。その意味でも、伊能忠敬という人は、サラリーマンなどのモデルにしても良い人だね~。
忠敬の測量の基本は、歩測と磁石と三角法。自分で一歩一歩地面を踏みしめながら、その一歩一歩が地図作りの貴重なデータを生み出していく。伊能忠敬の一歩は69cmだったという。江戸以前の人々の履き物は「下駄」にしても「草履」にしても踵がない。ある人が実験した結果、これらの履物で、フラット着地で歩くと、歩幅は狭くなり、踵をつかず一定のスピ-ドを保って歩ける最大歩幅を探しながら歩いた歩幅は69cm弱になった。自分の記録75cm(通常歩行)、72cm(なんば歩行・踵着地)ではなく、伊能忠敬の歩幅と云われる69cmにほとんどぴったりと重なってしまったという。(以下参考の「nanba なんば歩行 」を参照。)
私も、色々な仕事をしてきたが、ある仕事で、デパーなどの売り場や駐車場の敷地面積を、自分の歩幅で調べたことがある。よく床にピータイルといわれるものが貼られている場合、それは30cm四角のものが多く、その枚数を数えれば判るのだが、それが貼られていないときなど、その倍の60cmを基本に歩く練習をした上で、現地で歩数を数えるのである。同じところを2度歩いて、同じ歩数で歩いていれば、ほぼ正確である。2度歩くのは検算のようなもの。人間て、訓練するとほぼ同じ歩幅で歩くことが出来る。歩数で距離は計算出来るのだ。しかし、そのため、伊能忠敬ですら一日に10kmほどしか測量できなかったと言われている。
そして、曲がり角では方位を計測し、坂道では傾斜角を計測する。こうして集めた数値データを集計することで、きわめて正確な地図を作り出していく。測量方法そのものに新しさや独創性はないそうだが、忠敬のすごさは測量地点を多く取って測量の正確を期したこと。測量自体は小さな地味な仕事だが、それが積もり積もるとこんな大きなことが出来上がる。正に、根気と努力の賜物といえるだろう。
日本で最初の近代測量地図を作った伊能忠敬の伝記映画「伊能忠敬子午線の夢-」は、劇団俳優座創立55周年記念作品として製作され、映画では、このねばり強さを、忠敬の身体に流れる“農民の血”から生まれたものとして描き、主演・加藤剛が好演している。
(画像は映画「伊能忠敬」-子午線の夢-東映。ポスター)
参考:
神戸市立博物館:伊能忠敬の日本地図展
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/57/museum/tokuten/2004/01_ino.html
伊能忠敬記念館
http://www.sawara.com/tadataka/
伊能忠敬の略年譜
http://www2s.biglobe.ne.jp/~auto/nenpu.html
nanba なんば歩行
http://www.isone-sekkei.com/hosaka/hosaka2/nanba/nanba.htm