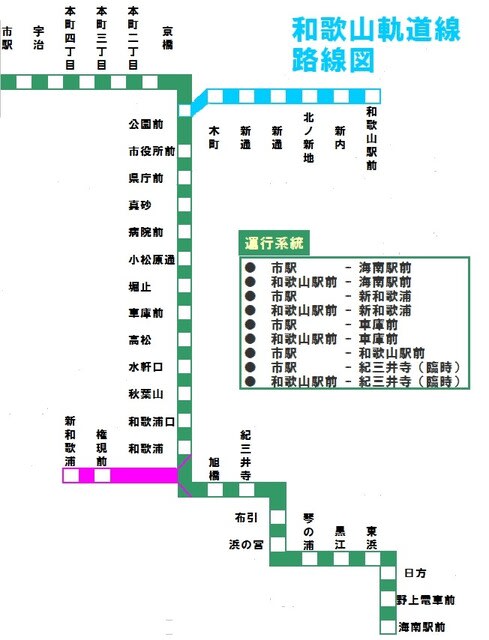【地下鉄なしで成功】拠点駅が多くて、逆に機能する広島の鉄軌道【120万人都市では珍しい多拠点型ネットワーク】
@naoyasano8695
6:47 大阪も、京阪の天満橋や、(今でも一部、ターミナル機能を維持してはいるが)近鉄の上本町といった、「中途半端」な場所をターミナルとしていたことがあったが、これはひとえに、市電との連絡の利便性を図るため。市電の廃止機運が高まった1960年代以降、京阪は淀屋橋、近鉄は難波へと、それぞれ延伸した。東京にしても、上野が長らくターミナル機能を維持していたのは、市電(→都電)や国電の乗り換えに便利だったから。広島は、昭和時代の大都市に見られた公共交通分散機能を今でも維持している点において、注目に値するといえる。