

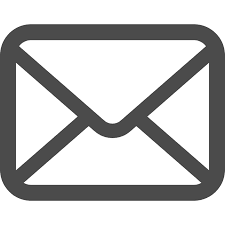
何かしらやたらと多忙に感じられる日があるものだ。
最近ではそんな日がだんだん少なくなっていたのに、今日に限っては珍しく色んな事が重なった。単なる偶然なのだろうが、色々あったね~。
カレンダーの予定欄には1件だけの予定が書かれている。それは午後1時前の、近くの小学校の学習サポートだけであった。
のんびり新聞に目を通して、まだパジャマを着替えていないうちにピンポーン、来客である。
地域活動の中でも今一番力を入れている大切な用件の打合せであった。カレンダーに書き入れるのを忘れていたのと、訪問時刻の確たる約束をこちらがいい加減に思っていて、午後からだろうくらいに軽く考えていた。いや~な話だが、最近こんなウッカリがよくあるようになった。気を付けなくっちゃ。
社会福祉協議会当地区担当の若い女性職員さんで、きわめて前向きな姿勢が見えることもあって応援したり、色んな質問に答える形で結構長話になった。朝イチの対応がこうなってくると、その日一日の要件がどれも似たように長くなるという連鎖反応を起こすようだ。なんでそうなるのか分からないが得てしてそういった傾向にある。
午前中がほぼつぶれてしまったので午後は少しゆっくり出来るかな・・・などと思ったのは大きな間違い。今度は訪問ではないが電話がかかった。これは長かった。スマホを耳に当てる腕が苦るほどである。高齢者ゆえの病があるので、あまり性急な会話にもならず、ゆっくり聞いてゆっくり答えを導いて、やんわり納得させる。これも地域活動の延長である一種のボランティみたいなものだ。
そして今日の締めくくりもやはり電話であった。こちらは、久しぶりに声の交換となる昔のPTA仲間のお一人であった。ある人からこの「やぶにらみブログの話を聞いたので開き方を教えて」という、小っ恥ずかしいご依頼であった。これもお断りするのも大人げないという判断から、見てもらうことを承諾し、少しの思い出話や昔の仲間でのOB会が開けるといいね。など他愛ない話を楽しんだ。
これで終わりか。いやまだ他に、返答を求められるメールも入っていた。
何にもすることがなくて時間を持て余すことにはあまり慣れていないのは確かだが、あり過ぎるのもね~。でも考えてみれば、一日の回転がうまくいって、いろんな人と色んな話をして、気持ちが和んだり考えたりさせられることもまた、生きていることの証なのだ。ある意味、贅沢な一日であったのかも。
































