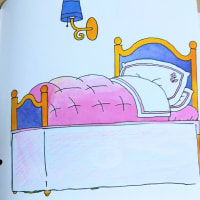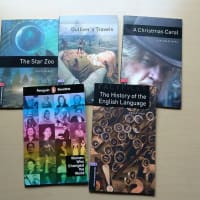先日、高校の同級生たちとの同窓会がありました。
ありがたいことに子育てについてのご相談をしてくださる友人も多く、色々なお話を聞きながら改めて子育てについて考えさせられました。
それについては、また次回の子育てブログで書きたいと思います(個別のご相談内容についてはもちろん書きませんが、そこから考えたことを書かせていただく予定です)。
さて、今回は前回までの子育て話の続きの「得意科目を伸ばすための塾の活用法②」、文字や数字の習得、幼児用教材の使い始め時期、そして塾を活用し始める時期についてです。
毎日読み聞かせをしていたり、生活の中で時計を見ながら時間を言っていたりすると(ちなみに、家に置く時計は、デジタルではなく、視覚で図として認識できる円形の時計がおすすめです)、お子さんは自然に文字や数字に興味を持ち始めると思います。
一緒に文字(平仮名だけではなく、カタカナや漢字も含みます)を読んだり、数字を読んだりしていると、自然に文字を覚えていきます。そのとき大切なことは、お子さんが質問してきたときは、必ず答えることです。
忙しくしていると、ついつい「あとでね」と言って、後回しにしてしまいそうになるかもしれませんが、どーーーーしても答えられないときを除いて、答えてあげてください。ご飯を作りながらでも、口で答えることはできますよね。
そして、すぐに答えられる質問(文字や数字の読み方など、親が答えを知っているもの)については、もちろんすぐ答えればいいのですが、答えが分からない質問については一緒に考えてあげてください。今は、昔と違ってスマホなど簡単に調べられるツールがたくさんあります。「分からないことは自分で調べる」という姿勢を、親が率先して見せましょう。
ちなみに、質問されたときに「あとでね」と言って、あとで答えようとしても、その時には子供自身が興味を失っていることが多く、「え?そんなこと言ったっけ?」という状態になってしまうこともあります。そして、「あとでね」という対応を続けていると、子供は親に質問しなくなっていきます。すると、だんだん会話自体が減っていき、親子のコミュニケーション量が物理的に減ります。お子さんと密に関われる時期は意外と少ないので、是非、お子さんからアクションがあったら答えてあげてください。
さて、話題を元に戻して……、文字や数字が読めるようになり、簡単な絵が描けるようになったら、文字や数字を書く練習をしてみましょう。今はタブレット教材が多いですが、私はあえて紙をおすすめします。
タブレットからの光の刺激が幼い子供の目の成長に与える影響が未知数ということもありますし、つるつるした画面のタブレットに書くよりも、紙に書く方が適度な摩擦があって「書いた!」という感覚を得やすいと思うからです。
お子さんと一緒に書店に行き、おもちゃを選ぶ感覚で文字の練習帳を一緒に選んで、楽しく練習してみると良いと思います。うまくできたら花丸を書いたり、お気に入りのシールを貼ってあげたりすると、お子さんは大喜びしますよ!
ちなみに、文字を練習するタイミングは、早くても全く問題ないと思います。
今は、小学校に上がるときには、幼稚園・保育園などで文字の書き方を既に練習して身につけているお子さんが多いです。「周りの子はできているのに、自分はできていない」と感じると、お子さん自身の自己肯定感が下がってしまいます。比較する必要はないのですが、無意識のうちに比較してしまうのが人間です。新しいことを知る「学ぶ」という作業は、本来は楽しいことですので、できるだけ楽しい気分で学びを進めていっていただきたいと思います。
私は、市販教材をどんどん進められるお子さんであれば、年齢学年にかかわらず、書店で売られている教材を活用して、どんどん先のことを学べばよいと思っています。
しばらくは保護者の方が先生役でご家庭で勉強できると思いますが、保護者の方が教えることを専門にしていない場合は、「これを教えるのは難しいな~」と感じる時期がくると思います。その時が塾の出番です。
塾には色々な種類があり、学年を問わず先のことまで教える塾もありますので、「中学受験塾」「中学受験はしないけれど先の勉強まで取り組みたい」など、目的に合わせて塾選びをしてみてはいかがでしょうか。
塾選びに際しては、無料体験がある塾を選んで、塾の方針や先生との相性を確かめてくださいね!
にほんブログ村 ←いつも読んでくださりありがとうございます!ランキングに参加しています。クリックしていただけると嬉しいです!
塾教育ランキング ←こちらもクリックしていただけると嬉しいです!