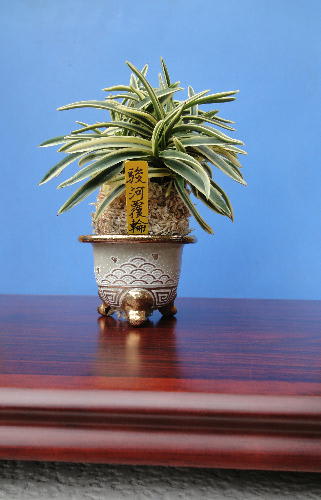7月2日(火)~7日(日) 花の文化園イベントホールで初夏の展示会、
7月2日(火)~7日(日) 花の文化園イベントホールで初夏の展示会、
第24回「富貴蘭、春蘭・寒蘭の柄物と野生蘭の展示会」を開催する。
第1回(平成2年)から昨年までは「富貴蘭とウチョウラン展」を実施して
きたが、近年ウチョウランを栽培=出展する会員が少なくなってきたため、
本年度より「富貴蘭」中心に変更し、会期も「富貴蘭」の開花する7月初めに
変更した。また一人でも多くの会員の出展を促すため展示会の運営細則を
改正し、富貴蘭については一人当たり出展鉢数の上限を15鉢に制限した。
私も本年は15鉢と山採りフウランの木枠付1点を出展する。
花の咲き終わった品種、咲かない品種もあり、品種選びも手間がかかる。

11

<青星> あおぼし 紀州産の6弁花。天咲きの距のない花は、
花火が夜空に開いたようで鑑賞価値が高い。
9

<巨翆> おおみどり

04w

24w

<唐錦> からにしき
虎斑の代表品種。泉州の産。
緩やかに弧を描く姫葉で、白黄色の虎斑が切れよく入り、
その斑は葉裏まで抜ける。日の採り具合で柄出しが決まる。
その日の加減が問題で、採り過ぎれば葉全体が黄金色となり、
作落ちの原因ともなりかねない。
蔭作りだと虎斑がうまく出ず、鑑賞価値が落ちる。
美術株に仕上げるには、経験が必要である。
13

02w

<旭昇> きょくしょう
産地は奄美徳之島。上芸品は虎斑もよく残り、
根先の色もルビー根に近くなるので人気が高い。
18

<金甲覆輪>きんかぶとふくりん
記録では母種の<金兜>から変化したものとされている。
07

<金広錦> きんこうにしき 岡山県の産。
葉幅の広さでは<大江丸縞>に匹敵するボリュームがある。
29

30

<翆華殿> すいかでん
肉厚の豆葉で、小型ながらボリューム満点の
葉姿で人気が高い。また花変わりとしての評価も高い緑花である。
16

17

<青海>せいかい
これほど葉姿と銘がぴったり当てはまる品種も少ない。
肉厚で丸みのある葉が軸元から半円を描くように湾曲する。
その葉が重なった姿は、まさに江戸文様の青海波そのものである。
産地不詳で、昔は<青海波>と呼ばれた。
花もピンク色の強い大輪の変わり花で人気が高い。
20

≪天恵覆輪> てんけいふくりん
白覆輪の<御城覆輪>が黄色の覆輪に変化したもの。
黄色が強いほど上芸とされる。
06

<花纏> はなまとい
中型の細葉で三蝶咲きと呼ばれる花変わりである。
花は花弁が舌化したものである。舌が3枚になり、
舌に付随している距も3本出て、ちょうど錨のような
花型となった。
フウランとしては初めての三蝶咲きで、
1本でも目立つ距が3本も出るので、
にぎやかで豪華な花である。そのにぎやかな花に、
火消しの纏を連想して、<花纏>と命名したそうである。
現在も鉢数は少なく、増殖が望まれる。人気が高い。
8

<飛翔天> ひしょうてん
21

25

<富貴殿> ふうきでん
葉幅広く、ゆったりとした姫葉で風格がある。
富貴蘭を代表する人気品種で、常に銘鑑の上位中央に
その座を保っている。万延年間(1860~1861)に豊後国で
発見された。
28

<満月> まんげつ
がっしりとよくできた株は<富貴殿>とそっくりで、
天葉が後冴えか天冴えかの違いと、
下葉が黄色か乳白色かの違いがあるだけで、
葉姿はよく似ている。産地不詳。
14

<紫式部> むらさきしきぶ
襟合わせの良い整った中型種である。
本種の特徴は、青軸・青根で、ピンク花を咲かせるという
フウランの常識では考えられないものである。
12

<羅紗王> らしゃおう







 19wx
19wx 18wx
18wx 20wx
20wx 21wx
21wx
 03k
03k
 x
x 9wx
9wx 8wx
8wx 7wx
7wx 6wx
6wx 5wx
5wx 4wx
4wx 3wx
3wx