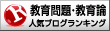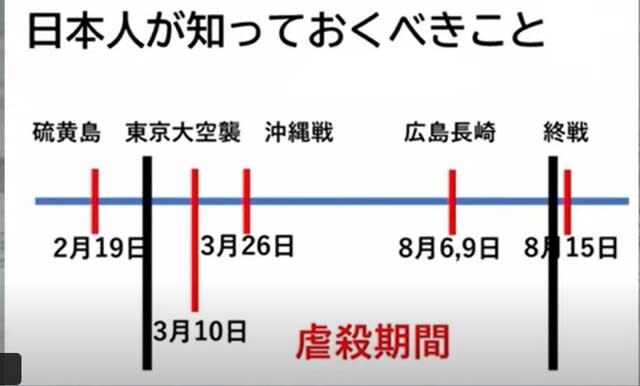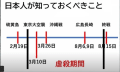元戦隊長側が上告/「集団自決」訴訟【社会】
太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍が「集団自決(強制集団死)」を命じたとする作家大江健三郎さんの「沖縄ノート」などの記述をめぐり、慶良間諸島の当時の戦隊長らが出版差し止めなどを求めた訴訟で、元隊長ら側は十一日、一審に続き訴えを退けた大阪高裁判決を不服として上告した。
上告について、元隊長ら側弁護団は「控訴審判決は一定評価できるものの、名誉棄損の最高裁判例を変え、人格権を著しく後退させた」と説明した。
一方、大江さんは弁護士を通じて「この訴訟が、高校教科書から『軍の強制』が削除されるきっかけとなった。最高裁判決が元に戻す力となることを信じる」とのコメントを出した。
◇
大阪高裁の小田裁判長は、「老い先短い元戦隊長の人権侵害は我慢せよ!」
としてノーベル賞作家と大手出版社の人権蹂躙を看過し、表現の自由を認めた。
被告の一人であるノーベル賞作家大江健三郎が、いかにいかがわしい人物であるか。
以下、評論家渡辺望氏の「大江批判」の続編です。
'08.10.18 ●渡辺 望氏 「ノーベル賞作家」という虚構 -大江健三郎への再批判-
(承前)
文学賞というのは、どんな国のどんな文学賞であっても、選考委員会の文学観によって、意外な受賞者や候補者を生む。たとえば純文学に対しての我が国最大の文学賞である芥川賞は、選考委員の作家の文学観の対立が、選考委員会上の激しい議論や選考委員の辞任といったエピソードをさまざまに生んできた。石原慎太郎や田中康夫の受賞をめぐっての選考委員会の荒れぶりは特によく知られている(後者は受賞に至らなかった)。だが、徳岡が伝えるところによるノーベル文学賞委員会の日本文学に対しての状況は、委員どうしの対立を生む以前の状態にあったことを示している。対立もなにも、日本文学への文学観そのものが、選考委員会に存在していないのである。
このエピソードはノーベル文学賞受賞に近づくために、まず、翻訳された小説が委員たちの身近になければならない、という条件が存在している、ということを意味している。しかしこのことは、日本文学が国際的・普遍的に読まれているのか、ということとはまったく無縁である。アメリカや中国、アフリカで大ベストセラーになっても、スウェーデンあるいは北欧という限られた地域で翻訳されていなければノーベル文学賞としては話にならないからである。
受賞候補になった後の大江が急にいたるところの国内・海外講演会で、スウェーデンの文化・文学を褒め称える「おべっか」をつかったということは、大江がこのノーベル文学賞というものが、日本の世評に反して、おそるべきダークゾーンを抱えていることに大江が気づき、彼の戦略を実行に移した、ということに他ならない。そして大江は、川端や三島や安部がおこなわなかったような範囲の行為に及ぶ。単にスウェーデンの書店に並ぶだけでなく、スウェーデン人の日本人への無知を逆手にとって、「自分は日本において数少ない、これほどスウェーデン文化の精通者であるのですよ」という巧みな営業行為をおこなう。
しかもこのノーベル文学賞選考委員会の日本への無知は、21世紀になった現在もまったく変わっていないのである。たとえば現在、日本人作家で毎年のようにノーベル文学賞候補になり、受賞にもっとも近いポジションにいるのは村上春樹である。作品内容的に、村上春樹とノーベル賞の結びつきを意外に思う日本人も多いだろうが、しかし、海外翻訳ということからすれば、村上の小説は日本人作家でもっとも外国語に訳されている小説家なのである。村上自身も外国語で執筆したり翻訳する能力を兼ね備えている作家である。当然、村上の小説はスウェーデン語でも多く読まれている。すなわち、ノーベル文学賞受賞のための重要な第一段階を楽々クリアしているのだ。「翻訳が多い」ということがただちにその作品がインターナショナルであることを意味 するわけではもちろんないはずである。しかし、こんなことだけが、候補作になる重要な理由の一つである。もちろん村上は大江のように営業をしているわけではないのであるが。
それではこの問題多きノーベル文学賞の選考委員会とは、いったいどのような背景をもつ組織なのであろうか?
漫画や演劇を通じてよく知られている『ベルサイユのばら』の物語の中で、マリー・アントワネットと、ヴェルサイユ宮に出入りするスウェーデンの貴族フェルセン(フェルゼン)との間の不倫のロマンスに胸をときめかした日本人は少なくないであろう。フェルセンは実在の人物で、マリー・アントワネットとの情事も歴史上の実話である。彼はスウェーデン国王グスタフ3世の命令を受けて、フランス革命の妨害工作を託された政治的スパイであり、アントワネットとの情事も、グスタフ3世の意図命令によるものだった。
このグスタフ3世という人物は、このフェルセンの派遣にみられるように、当時、ヨーロッパに高まりつつあった民衆革命の風潮に対して激しく反発し、その殲滅をはかった絶対専制君主の一人である。対外的にも、フランス、オーストリア、ロシアと肩を並べるスウェーデンの強国化を目指し、ロシア・エカチェリーナ2世と、フィンランドその他の領有を巡り、激しい戦争を繰り返した。グスタフ3世はデンマークにも触手を伸ばし領有化を目論んでいる。フランス革命潰しの政治的謀略といい、大国化への志向といい、グスタフ3世という国王は現在のスウェーデンのイメージと異なる方向性を導こうとした人物であったと言えよう。彼はその強引な絶対君主主義・大国化路線に反発する政治勢力の策謀により、46歳で暗殺の憂き目に遭うが、彼こそ、ノーベル文学賞にたいへんゆかりのある人物なのである。
ノーベル賞という賞はそもそも、スウェーデンの公的機関が複雑に絡み合いながら存在する、スウェーデンという国の対外的な文化勲章という性格を有する賞である。受賞賞金をはじめとする資金面を提供するのは周知のように基本的にノーベル財団であるが(経済学賞だけ別)選考その他、受賞の実権を握っているのは主にスウェーデンの公的機関の幾つかである。ただし、平和賞についての決定権限はスウェーデンの隣国ノルウェー国会が有している。その他の賞については、物理学・化学・経済学賞についてはスウェーデン科学アカデミー、医学・生理学賞についてはカロンリスカ医科大学が決定権限を有している。
このスウェーデン科学アカデミーとは別個にスウェーデンアカデミーという学士院的機関が存在しているのだが、このスウェーデンアカデミーが文学賞についての全権をもっているのである。スウェーデンアカデミーは18人の終身身分の委員の文化人によって構成されているのであるが、このスウェーデンアカデミーを創設した人物がグスタフ3世である。
このスウェーデンアカデミーは、グスタフ3世の創設の精神の国語方面からの維持、すなわちスウェーデン語の徹底的な明確化、国民教育化ということをこなすことをそもそもの目的としている。文学についての機関でなく、国語についての機関なのである。スウェーデンアカデミーのこの目的は現代においても継続しており、スウェーデン国内の文学にかかわる出版や宣伝でさえ、スウェーデン語に関係する事業に比べれば二次的な仕事とされている。しかし様々な事情を経由してノーベル賞の設定と同時に、ノーベル文学賞についての権限をあたえられることになった。
すなわち、スウェーデンアカデミーという組織は、ノーベル文学賞のために設置された組織でもなければ、現実的にノーベル文学賞に携わることを第一義にしている組織でもない。絶対専制君主によって創立された王立組織ということ、スウェーデンの国民国家化をスウェーデンの国語の確立という面から推進維持する組織であるということがその大きな性格なのである。こうしたことを考えれば、スウェーデンアカデミーに、日本文化や日本文学に精通している人間がほとんどいないのは至極当然のことであろう。
あれほど日本の皇室や日本の対外戦争について喧しい発言を続けてきた大江は、こうしたスウェーデンおよびスウェーデンアカデミーの背景については、批判的発言はただの一言もない。グスタフ3世と昭和天皇を比較して、どちらが「民主主義」的で、どちらが「反民主主義」的かは、誰が考えてもあまりにも明白なことであるというべきであるにもかかわらず、である。
しかし、そもそも大江という人間はこうした公平な歴史的判断ができる人間ではない。大江の言葉の世界の観念構造は、公平を志向するようにはできていない。私は前回人形町サロンに寄稿した論文で、大江の言葉の世界とは、「選ばれた読者」を絶えず見極め、その「読者」に巧みに媚びることである、と言った。大江にとっては、現実的に存在したグスタフ3世も昭和天皇も二の次の問題なのである。つまり大江は彼にとってはごく自然に、「選ばれた読者」を、スウェーデンアカデミーおよびスウェーデンというものに定め、その「選ばれた読者」との一体化を実践していくという彼の本領を如何なく発揮していくのだ。大江にしてみれば、ノーベル文学賞を巡ってのさまざまな営業は、彼にとって得意中の得意のゲームを演じるといいような認識であったに違いない。
ここでスウェーデンアカデミーをはじめ、スウェーデンの諸氏にむかっての大江のノーベル賞受賞講演『あいまいな日本の私』の、「戦後民主主義」者としての大江の自覚にあたると思われる箇所を引いてみよう。
1)日本近代の文学において、もっとも自覚的で、かつ誠実だった「戦後文学者」、つまりあの大戦直後の、破壊に傷つきつつも、新生への希求を抱いて現れた作家たちの努力は、西欧先進国のみならず、アフリカ、
ラテン・アメリカとの深い溝を埋め、アジアにおいて日本の軍隊が犯した非人間的な行為を痛苦とともに償
い、その上での和解を、心貧しくもとめることでした。かれらの記憶されるべき表現の姿勢の最後尾につら
なることを、私は志願し続けてきたのです。
2)現在、日本という国家が、国連をつうじての軍事的役割で、世界の平和の維持と回復のため積極的でない」という、国際的な批判があります。それはわれわれの耳に、痛みとともに届いています。しかし日本は、再出発のための憲法の核心に、不戦の誓いをおく必要があったのです。痛苦とともに、日本人は新生のモラルの基本として、不戦の原理を選んだのです。それは、良心的徴兵拒否者の寛容において、永い伝統をもつ、西欧において、もっともよく理解されうる思想ではないでしょうか?(続く)
◆












 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします