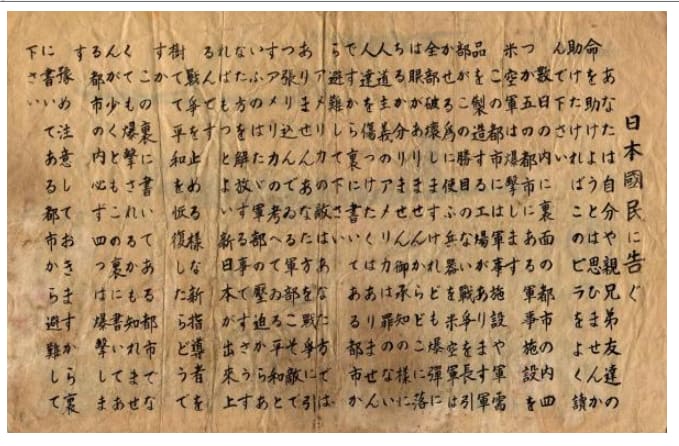【8月15日を過ぎてもボクは敗戦を知らなかった】
*ボクの見た戦中戦後(34)
昭和20年8月15日、国民学校2年生のボクは函館から秋田の親戚の家に疎開していた。
6人きょうだいの内、末の2歳の妹と乳飲み子の弟は父母と函館の鉄道官舎に残り、ボクと6年生の姉と5歳と3歳の妹の4人は叔母の家に預けられていたのである。
8月14日の深夜、秋田市(土崎)が空襲を受け、山の向こうが赤く見えた。
翌15日は空が青く晴れ渡った日だった。
お昼頃、ボクは近くの羽後岩谷駅へ遊びに出かけた。
すると、駅前で大人たちが直立し、頭を垂れていた。
駅舎から流れるラジオの放送を聞いているようだった。
ボクには何のことか分からないけれど、大人の間を走り抜けてはいけないように思い、しばらく、大人たちの真似をして、気をつけの姿勢で頭を下げていた。
しかし、誰が何を放送しているか分からず、窮屈な思いなので、そっとその場を離れた。
これが敗戦を告げる放送とは、その後もしばらく知らないでいた。
姉は誰からか重大放送があることを知り、友達のいる駅長さんの官舎に出かけ、ひざまずいて天皇陛下の放送を聞いていたと言う。
姉は天皇陛下のお言葉を理解できなかったのか、戦争に負けたことをボクには知らせてくれなかった。
疎開先の家でも、敗戦の話は一言もなかったので、ボクはまだ戦争を続けているものと思っていた。
そのため、学校へ行くときも包帯や赤チンキを入れた救急袋を肩にかけていた。
空襲で怪我をした時の応急手当をするためのものであった。
救急袋を函館の学校(亀田小学校)では生徒全員が持って登校していたが、疎開先の学校では誰も持っていなかった。
敗戦後も、肩にかけているバッグに先生が気づき、それは何かと尋ねられたので、「救急袋です」と応えた。
この時も先生は日本が戦争に負けたことを教えてくださらなかった。
戦争中、大人たちも先生も「日本は必ず勝つ」と、言っていたので、子どもたちへ敗戦をどう説明したらよいか戸惑ったことだろう。
疎開していた家は茅葺の大きな農家だった。
函館の鉄道官舎の何倍もあった。
家の前にいたとき、ゴ~と爆音が聞こえた。
敵機だ! しかし、空を見上げたが何も見えなかった。
疎開先の家には防空壕がなかった。
ボクは急いで家の中に飛び込んだ。
すると、この音は以外にも家の奥から聞こえてきた。
覗いてみると、親戚の人が石臼で米の粉を挽いているところだった。
石臼を挽く音は飛行機の爆音に似ていた。
戦争が終わったことを知らないボクは、函館で空襲に遭ったことを思いだし、いつも敵機の空襲に備えて身構えていたのだった。
終戦になっても、父母はなかなか迎えに来なかった。
11月になってから母は弟を背負い、妹の手をひいてボクが疎開している秋田の親戚の家を訪ねてきた。
連絡船は全滅していたから、津軽海峡を貨物船で渡ったとのことであった。
後に母親に8月15日のことを尋ねると、その日の朝、ラジオで正午に重大放送があることが知らされた。
このとき、日本は戦争に負けたことを悟ったという。
もう空襲は無くなるから、ほっと安心したとのことであった。
正直な気持ちを他人に話せば非国民と言われ、罰を受けそうなので、黙っていたとのことだ。
毎年、8月15日になると、これらのことが思い出される。