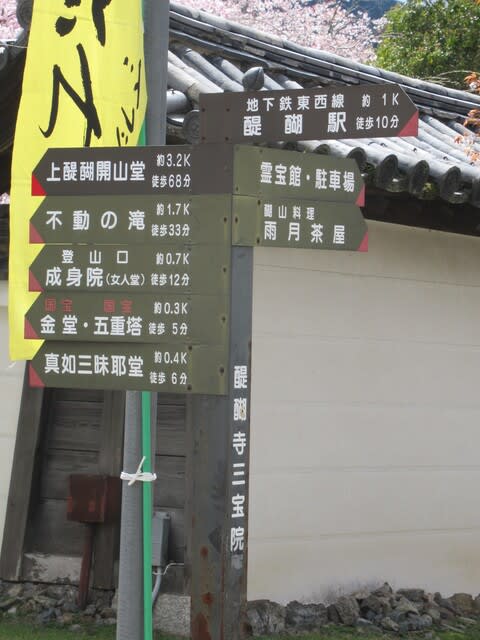2014-11-17付ブログを参照してください。

浄土宗大本山くろ谷金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)全景図。
境内は広く一山といった感じで山の中腹にあり高低がある。
一番高いところからは京都中心部が見え眺めがとても良い。

法然上人の幼名勢至丸(せいしまる)の像。
承安5年(1175年)春、浄土宗の開宗を決めた法然が比叡山の黒谷を下った。
岡を歩くと大きな石があり、法然はそこに腰掛けた。
するとその石から紫の雲が立ち上がり、大空を覆い西の空には金色の光が旅たれた。
そこで法然はうたた寝をすると夢の中で紫雲がたなびき、
下半身がまるで仏のように金色に輝き善導が表れ対面を果たした。(二祖対面)
これにより法然はますます浄土宗開宗の意思を強固にした。


これは御影堂(大殿)。
左京区黒谷町にある浄土宗の大本山。
山号は紫雲山。
本尊は阿弥陀如来。
通称をくろ谷さん(くろだにさん)と呼ぶ。
知恩院と並ぶ格式を誇る浄土宗の七丈本山の1つであり、
京都四箇本山(他に知恩院、百万遍知恩院、清浄華院)の1つでもある。


一番下部の方にある門(高麗門)。
この門の柱には会津藩松平肥前守京都守護職本陣旧蹟の木版が掛けられている。
また、大きな石碑には会津藩殉難者墓地と書かれている。
詳しくは後述します。



この山門(楼門)は応仁の乱で焼失。
万延元年(1860年)再建された。
掛けられている扁額「浄土真宗最初門」は後小松天皇の自筆である。
早朝の朝日が山門周辺の桜にあたり、心が洗われるような美しさであった。

納骨堂(旧経堂)元禄2年(1689年)再建。
現在は当寺に納骨されたお骨で造立された「骨仏」と呼ばれる阿弥陀如来座像が安置されている。

慶長10年(1612年)に豊臣秀頼により再建された阿弥陀堂。
祀られている阿弥陀如来像は恵心僧都源信が仏像の彫刻に必要な「のみ」を体内に収めて、
以後の仏像彫刻を止めたことから「のみおさめの如来」「お止めの如来」と呼ばれる。

平安時代末期の武将・熊谷次郎直実が出家し、
法力房蓮生となったという蓮池に架かる極楽橋。


実はホテルオークラ岡崎別邸と岡崎神社の間に狭い道があり、
それを上っていくと金戒光明寺の南門に出た。
この門はいわゆる裏門で、ここを登っていくと法然上人御廟をはじめ、
山の頂上まで墓地がつながっている。

階段を登った正面には三重塔(文殊塔)重要文化財がある。
寛永10年(1633年)の建立だ。

文殊塔(三重塔)に登る石段の左に位置している独特の頭髪の形状から
「アフロ阿弥陀」と通称されている「五却思惟阿弥陀如来石像」。

墓地の中腹から山門に向けて撮った1枚。
これを見ても山と谷(くろ谷)との高低差がわかると思う。
この階段の左右は墓地、供養地になっている。
ここには清和天皇火葬塚、熊谷一族墓地、熊谷次郎直実の供養塔。
平敦盛の供養塔、八橋検校の墓(菓子八ツ橋の語源)。
第2代将軍・徳川秀忠の正室で家光の母、浅井長政の娘「お江」の供養塔。
斉藤利三の娘、春日局の墓(家光の乳母)。
山中鹿之助幸盛の五輪塔などがある。


さぁここからさらに登って一番高いところにある会津藩殉難者墓所に向かいましょう。



幕末の京都は暗殺や強奪が日常化し、徳川幕府は常に新しい職制を作り、
京都の治安維持に当たらせることとなった。
これが京都守護職である。
文久2年(1862年)8月、会津藩主・松平容保公は14代将軍・徳川家茂から京都守護職に任ぜられ、
同12月24日、家臣1,000名を率いて京都に到着。
京都所司代・京都町奉行所の出迎えを受けて、
本陣の黒谷金戒光明寺に威風堂々と入陣した。
黒谷金戒光明寺は自然の要塞になっており、
御所や粟田口にも近く軍事的要塞の地であった。
また大きな寺域により1,000名の軍隊も駐屯することができた。
時の京都は尊壌激派による暗殺の坩堝と化していたが、
守護職となった会津藩の活動には目を見張るものがあり、
元治元年(1864年)6月には守護職配下の新選組による「池田屋騒動」、
7月18日、19日の「禁門の変」の勝利などで治安は回復されてきた。
しかしながら会津藩の犠牲は大きく、藩士や仲間小者などで戦死、戦病死するものが続出した。
そこで本陣の金戒光明寺の山上に300坪の墓地が整備され葬られた。
その数は文久2年から慶応3年までの6ヶ年に237霊をかぞえ、
後に慰霊碑を建立し、鳥羽伏見の戦いの115霊を合祀した。

松平容保公は孝明天皇の御信任厚く、禁裏洛中を挙藩一致して大義を明らかにし、
会津軍の忠誠に歴史にその名を残した。


会津墓地からはご覧のように平安神宮の大鳥居、そして遠くに京都タワー、
ホテルオークラ本館の雄姿もよく見えた。