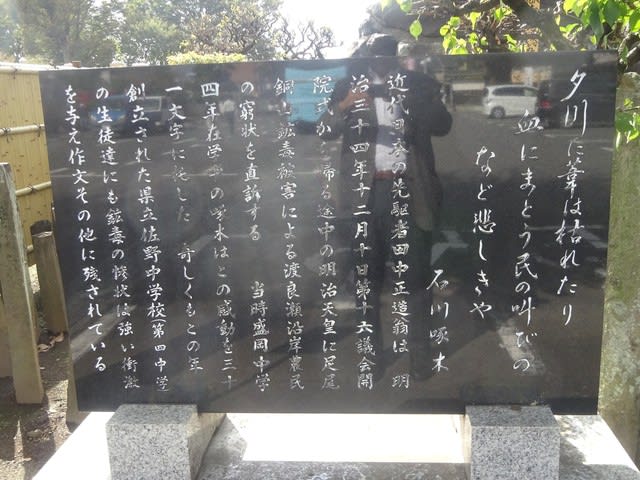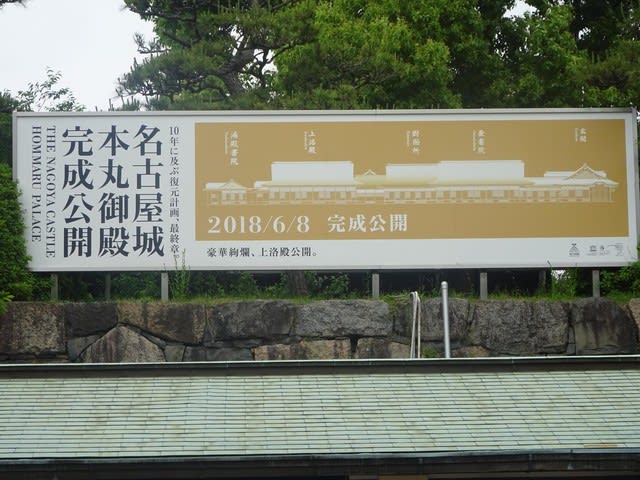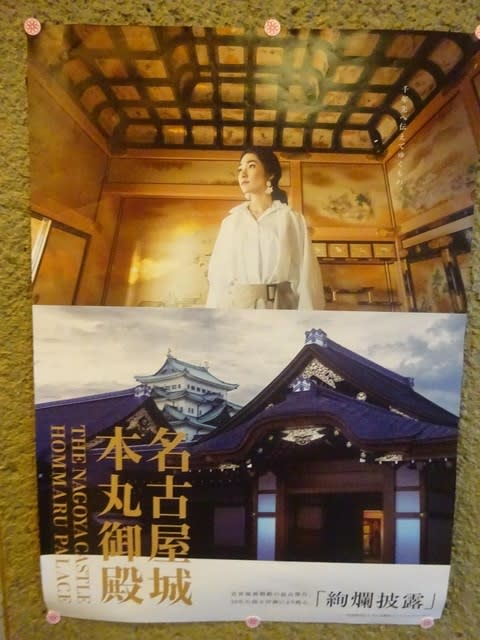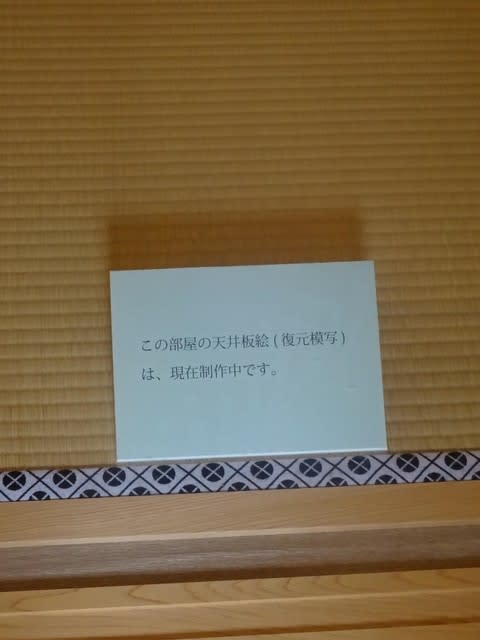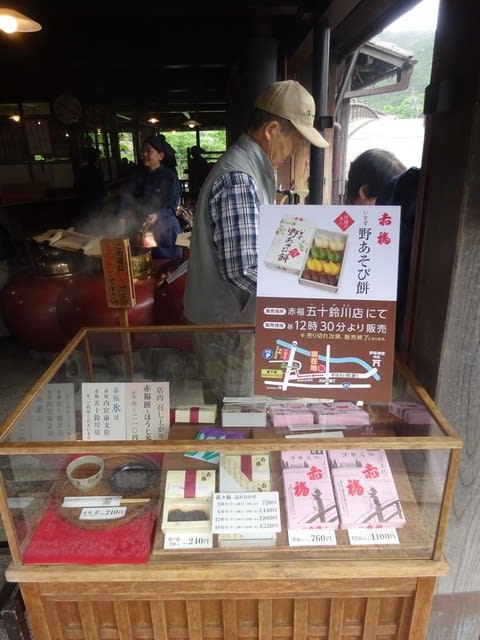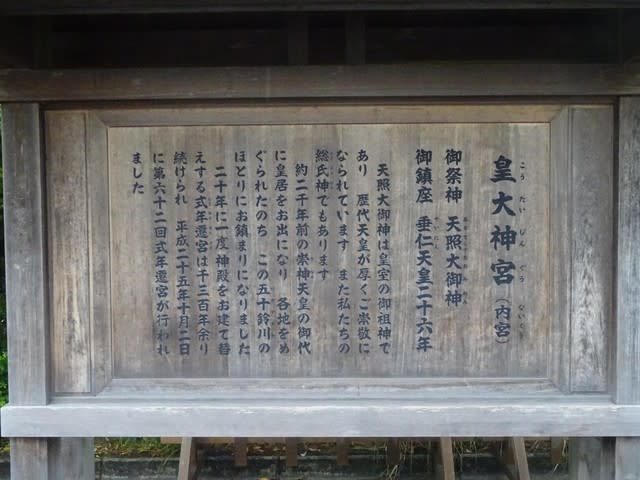秋田新幹線こまちに乗ってみちのくの秋を訪ねてみました。
E6系の愛称こまちのラインカラーはピンク。
今から20年以上前の1997年3月22日に開業しました。

田沢湖駅のプラットホームには「たざわ湖龍神まつり」で登場する
辰子姫の龍が展示してありました。
永遠の美と命を求め龍の姿を得た辰子姫の伝説によって田沢湖は
「縁結びの湖」「出会いの湖」として知られています。
さいたま竜神祭がスタートしたばかりの頃、
このたざわ湖の龍神が来てくれたことをきのうの様に思い出します。


田沢湖駅の歴史は大正12年の開業。
現代の近代的な駅舎は平成9年秋田新幹線の開業によって建て替えられました。
この駅舎の設計は現在注目されている坂 茂氏。
集成材が耐火被覆と仕上げ(美観)を兼ねる工夫がされ
グッドデザイン賞を受賞しました。

これが田沢湖周辺の地図。
田沢湖駅、田沢湖は平成の大合併によって
田沢湖町、角館町などが合併して仙北市となりました。


田沢湖湖畔にある広い広いドライブイン。
紅葉の季節というのに人気があまりなくさびしい所でした。
先日BSTVでここを放映していたがそのいくつかを紹介しましょう。

このドライブインに来訪予定の団体名が書かれた札を見ていると
つくづく時代は変わったと思います。
確かに秋田新幹線に乗ればわけなくここに来ることができますが、
日本の中ではそれ程ここはメジャーな観光地ではない。
それなのに台湾の団体が3グループ、
香港のグループが1つと4割を占めています。



秋田といえば薩摩地鶏、名古屋コーチンと並んで
日本三大地鶏の1つに考えられている比内地鶏が有名です。
比内鶏の特徴は歯ごたえがあるが、
加熱しても硬くなり過ぎず、肉の味が濃い。
濃厚な脂の旨みなどがあげられています。
秋田名物料理のきりたんぽ鍋と相性が良く、よく使われています。


現在、比内地鶏より評判になっているのがロシアの女子フィギュアスケーター、
アリーナ・ザギトワの愛犬マサルで有名になった秋田犬です。
ここにいる天空(そら)という秋田犬もTV放映ですっかり有名犬になってしまいました。



お客がほとんどいないのに日本三大うどんのひとつ、
稲庭うどんの手延べ製法の実演をやっていました。
稲庭うどんはひやむぎより太く、やや黄色味かかった色をしています。
製法としては、うどんというより、そうめんに近い。
打ち粉としてデンプンを使う点や、平べったい形状が特徴です。

ドライブインのレストハウスを下りた所からいよいよ遊覧船に乗って田沢湖巡りだ。
この遊覧船は4月から11月まで営業しています。

遊覧船乗り場の近くは浜辺になっていて、湖水浴場として認められている。
海水浴場と同様の利用ができます。


田沢湖にはクニマスなど数種の魚が生息していましたが、
強酸性の源泉を含んだ水を湖に導入する水路が作られた為、
ほとんどの魚類が姿を消しました。
現在は水質を改良したため、ご覧の様な沢山のウグイを中心に復活しました。
船着場で販売されていた餌をあげたら、気持ち悪い程食べに来ました。

この遊覧船は羽後交通興業が運営しています。
前述のレストハウスも同じ会社が経営しているそうだ。


田沢湖は直径約6kmの円形カルデラ湖で国内で19番目の大きさの湖だ。
この湖が有名なのは最大深度423.4mと日本で最も深い湖ということ。
因みに第二位は支笏湖、第三位は十和田湖、
そして世界一深い湖はバイカル湖だ。
田沢湖は世界では17番目の深さで日本のバイカル湖と呼ばれています。




丁度行った時(11月9日)は紅葉の季節で田沢湖を囲む山々も
よい感じだったので多くアップしてみました。
緑濃く見えるのが有名な秋田杉。
赤・黄・緑のグラディエーションの美しさに暫し船上から見とれてしまった。
田沢湖は日本百景にも選ばれている景勝地だ。


湖の北岸にある御座右神社。
ここには辰子が竜になるきっかけとなった水を飲んだと言われる泉がある。
太陽の光の具合もあるのだろうが、
このあたりの湖水の色は特に美しく、
ペルシャンブルーと言われているとか。
本当に美しい紺碧の色でした。


田沢湖でもう一つ有名なものがこの「辰子姫像」。
舟越保武作の像だ。
田沢湖には民間伝承に基づく辰子伝説がある。
イワナを食い水をがぶ飲みし、龍の体になった辰子が
八郎(八郎潟)とやがてめぐりあって夫婦となったという辰子伝説だ。

たつこ像の近くに湖に張り出す形になっている小さな神社「漢槎宮」。

この山の紅葉した姿を見ると浦和出身の画家で点描画で知られている
高田誠画伯の絵を思い浮かべる。
田沢湖の豊富な水量は湖底の湧水が支えていると考えられています。



田沢湖から乳頭温泉に向かう途中に燃えるように紅葉した
カエデの木が数本あったので途中下車してしばし記念撮影会となった。
まさにこれが紅葉だと言った風景に感激!!




田沢湖周辺では、はちみつが採れるらしい。
昭和52年に開業した「山のはちみつ屋」さん。
当店の建物は蜂の巣を模したのだろう。
天井もハニカム的形態の構造になっています。
ここは、はちみつ、はちみつジャム、はちみつフルーツ酢、
はちみつだらけの甘~い店だ。