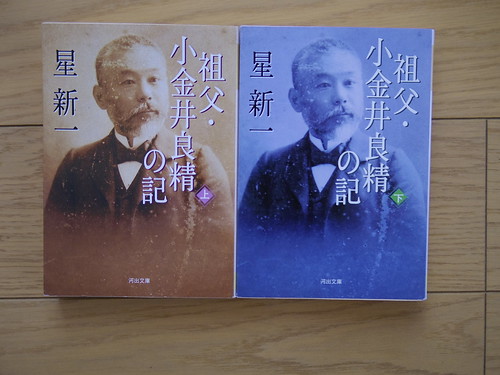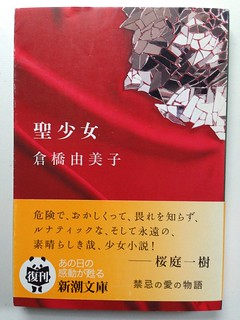本書「峠」同様これまた「祖父・小金井良精の記」を読んで読みたくなりました。
(序盤に本書が引用されています。)
小金井良精は本作の主人公小林虎三郎の甥にあたります。
最初に「祖父・小金井良精の記」を読んだ小学・中学生頃は本書を読もうと思っても絶版で入手できず、未読でした。
(図書館でも探したのですが当時の私では見つけられませんでした。)
ただし「米百俵」で名前を知った、山本有三にはその頃はまって「路傍の石」「心に太陽を持て」「生きとし生けるもの」などの少年向きな作品や小品の「無事の人」などを読んでいました。
特に「無事の人」はいまでも名作だと思っております。
なお「真実一路」「女の一生」はちょっと手が出ず未読。
山本有三、日本文学ではどの辺に位置付けられているんでしょう?
純文学…という感じでもないし、大衆文学でもない。
独特ですね。
小泉さんが首相の時に「米百俵の精神で…」なる話が出て2001年の流行語になったときに復刊されたものをブックフで見つけて入手していたのですが未読でした。

なお現在本書はまた絶版のようです、残念。
オリジナルは1943年発刊。
内容(裏表紙記載)
戊辰戦争で焦土と化した城下町・長岡。その窮状を見かねた支藩より見舞いの米百俵が届けられた。だが、配分を心待ちにする藩士が手にしたのは「米を売り学校を立てる」との通達。いきり立つ藩士を前に、大参事小林虎三郎は「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる」と論す。「米百俵の精神」を広く知らしめた傑作戯曲。著者の講演も収録。
「祖父・小金井良精の記」で星新一が書いていましたが、太平洋戦争真っただ中の1943年によくまぁ敗戦後の心構えを書いた作品を出せたものです。
そういう意味だけでもすごい作品です。
(解説によると本作に時の政府から圧力がかかった形跡があるようなことを書いていました)
本作「小品」かつ戯曲ですのですらっと読めてしまいましたが…。
私は「名作」と感じました。
司馬遼太郎の「峠」の後に読んだのが大きいのでしょうが、戦いに負けてもとにかく人は生きなければいけないし、それもただ生きるだけでなく「よりよく」生きなければならない….。
河井継之助のように華々しく戦うのは目立ちますが、小林虎三郎のような地道な行き方をする人は実際にはとても大切ですよねぇ。
山本有三の少年向け小説にあるような「きれいごと」的なものも感じますが、真摯さがストレートに伝わってきました。
(とにかく「峠」を読んでから読むのがお薦めです)
戯曲の後に収録の著者の小林虎三郎に関する講演も興味深かったですです。
「河井継之助の名前は有名だが、小林虎三郎は無名で残念」と話しています、戦前からすでにそんな傾向だったんですねぇ。
「小金井良精」の名前も小林虎之助の甥ということでこの講演中たびたび登場します。
良精博士当時はけっこうな有名人だったようですね。
司馬遼太郎も絶対本作読んでいたでしょうに「峠」で小林虎三郎の出番はほんの少ししかありません。
あまり出すと継之助の英雄譚としての物語が成り立たなくなると思ったのでしょうか…残念ですね。
ネット上で見たら「本作が河井継之助を非難している」という評価も見受けましたが、作中直接非難はしていないように思うのですが…。
どうしようもない状況を引き受け文句もいわず最善を尽くす小林虎三郎の姿を穿ちすぎて観るとそういう気分になるんでしょうかねぇ。
そんな姿に感銘を受ける名作と感じました。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
(序盤に本書が引用されています。)
小金井良精は本作の主人公小林虎三郎の甥にあたります。
最初に「祖父・小金井良精の記」を読んだ小学・中学生頃は本書を読もうと思っても絶版で入手できず、未読でした。
(図書館でも探したのですが当時の私では見つけられませんでした。)
ただし「米百俵」で名前を知った、山本有三にはその頃はまって「路傍の石」「心に太陽を持て」「生きとし生けるもの」などの少年向きな作品や小品の「無事の人」などを読んでいました。
特に「無事の人」はいまでも名作だと思っております。
なお「真実一路」「女の一生」はちょっと手が出ず未読。
山本有三、日本文学ではどの辺に位置付けられているんでしょう?
純文学…という感じでもないし、大衆文学でもない。
独特ですね。
小泉さんが首相の時に「米百俵の精神で…」なる話が出て2001年の流行語になったときに復刊されたものをブックフで見つけて入手していたのですが未読でした。

なお現在本書はまた絶版のようです、残念。
オリジナルは1943年発刊。
内容(裏表紙記載)
戊辰戦争で焦土と化した城下町・長岡。その窮状を見かねた支藩より見舞いの米百俵が届けられた。だが、配分を心待ちにする藩士が手にしたのは「米を売り学校を立てる」との通達。いきり立つ藩士を前に、大参事小林虎三郎は「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる」と論す。「米百俵の精神」を広く知らしめた傑作戯曲。著者の講演も収録。
「祖父・小金井良精の記」で星新一が書いていましたが、太平洋戦争真っただ中の1943年によくまぁ敗戦後の心構えを書いた作品を出せたものです。
そういう意味だけでもすごい作品です。
(解説によると本作に時の政府から圧力がかかった形跡があるようなことを書いていました)
本作「小品」かつ戯曲ですのですらっと読めてしまいましたが…。
私は「名作」と感じました。
司馬遼太郎の「峠」の後に読んだのが大きいのでしょうが、戦いに負けてもとにかく人は生きなければいけないし、それもただ生きるだけでなく「よりよく」生きなければならない….。
河井継之助のように華々しく戦うのは目立ちますが、小林虎三郎のような地道な行き方をする人は実際にはとても大切ですよねぇ。
山本有三の少年向け小説にあるような「きれいごと」的なものも感じますが、真摯さがストレートに伝わってきました。
(とにかく「峠」を読んでから読むのがお薦めです)
戯曲の後に収録の著者の小林虎三郎に関する講演も興味深かったですです。
「河井継之助の名前は有名だが、小林虎三郎は無名で残念」と話しています、戦前からすでにそんな傾向だったんですねぇ。
「小金井良精」の名前も小林虎之助の甥ということでこの講演中たびたび登場します。
良精博士当時はけっこうな有名人だったようですね。
司馬遼太郎も絶対本作読んでいたでしょうに「峠」で小林虎三郎の出番はほんの少ししかありません。
あまり出すと継之助の英雄譚としての物語が成り立たなくなると思ったのでしょうか…残念ですね。
ネット上で見たら「本作が河井継之助を非難している」という評価も見受けましたが、作中直接非難はしていないように思うのですが…。
どうしようもない状況を引き受け文句もいわず最善を尽くす小林虎三郎の姿を穿ちすぎて観るとそういう気分になるんでしょうかねぇ。
そんな姿に感銘を受ける名作と感じました。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。