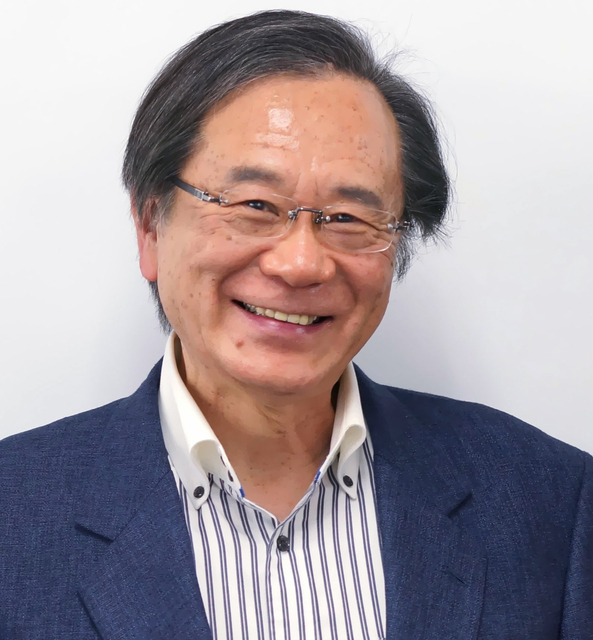以下は、30数年以上自民党国会議員の政策秘書を勤めた小城正克 さんのfbからです。ぜひ、お読みください。拡散もお願いします。
まず私は自由と民主主義の社会に身を置き、10年前まで30数年間自民党所属の国会議員の政策秘書の身分で国会を職場とし政務を行っていた人間である。安倍晋三は彼が父安倍晋太郎代議士の秘書で支えていたころから知っている。その愚鈍ぶりは昔から有名であったが、今でも尚その気色悪い安倍晋三を信奉する人たちが、政権批判をする人たちを反日...とか左翼主義者と決めつけたりする輩が多いことに悪寒を感じて止まない。己の思考力で考える力を失っているとしか見えない。歴代総理の中でも戦後最悪の知能程度の低さを露呈して憚らない安倍晋三を一生懸命擁護したり心酔する気持ちが全く理解できない。その中でも目立つのがマスコミの偏向報道だと宣う言葉に見識を疑う。現在のマスコミと称する報道機関にどこに正常な情報を国民に流している新聞社やテレビ局があるというのだろう。所詮一介のサラリーマンでしかないマスコミに携わるものの中にジャーナリストとしての気概を持っている人間たちがどれ程いるというのだろう。国際ジャーナリスト協会における日本の報道の自由度は先進国の中でも一番低い68番目だと言うことが分かっているのだろうか。
国際政治社会の中で先進国首脳が安倍晋三に対してどのような評価を下している現実を知っているのだろうか。まずトランプは大統領予備選挙のときに安倍晋三が民主党候補のヒラリー・クリントンのところだけ激励に行ったことを『私は終生忘れない。安倍は信用ならない男だ。』と口にしており、自分が在職中は日本からは精一杯搾り取ってやると豪語していることすら知らないのだろう。今回も足元を見透かされ高い買い物をしてきたが地上イージスシステムも現実的には無用の長物でしかない。何故ならば大陸間弾道弾ロケットはマッハ25の超高速で撃ち込まれるものであり対する迎撃ミサイルは精々マッハ7でしかない。まず打ち落とせるものではないということだ。
驚異としている中国の人民解放軍は、軍縮の流れで一年間で三十万人のリストラを行っている。中国共産党が一番恐れているのは人民の政府離れなのだ。そもそも共産党員は全人口の6%しかいない。最近では経済力をつけた富裕中間層も今や六億もおり、海外渡航する人たちも増え海外の政治情勢を知る人も増え、海外移住希望がとてつもなく増えていることを知ることだ。
ロシアのプーチンに至っては、この前の平和友好条約の締結に向けての提案に何の反論もなかったのにも拘わらず自国日本へ帰って平気で嘘を公共電波放送で述べたことに対してロシアの報道官が抗議したが今もって、その反論は成されていない。要は安倍晋三では北方領土問題は議論も出来なくなった現実だけが残ってしまった。
欧州に至ってはドイツはじめ先進国首脳たちは低レベルな知能を持ち合わせた安倍晋三とまともに付き合っていると自らの政治生命まで脅かされてしまうと考えている。つい最近の国連での演説もトランプやフランスのマクロンの演説が終わると席を立つものが目立ち、安倍晋三が小学生さえ知っている『背後』という言葉さえ知らなかった演説原稿を読むだけの演説の時には、3割も聴衆者がいなかった現実をどのように評価するのだろうか。
これから世界は、温暖化の影響で大きな自然災害が至るところでますます増えていくであろう。その災害援助と救助は、平和国家日本の使命であり義務であることを日本政府は真剣に受け止めなければならない。これから異常とも思える気候変動で穀倉地帯も大干ばつに陥り世界的食糧危機を迎えると思われる。
今日本が、世界に先駆けてやらなければならないことは、平和国家としての相互扶助の精神を世界に牽引いくことである。それが不幸な戦争を経験し奇跡的な経済復興を成し遂げた先人たちからの絶対的継承だと私は考えている。
《抜粋》
「私たちの同盟を“希望の同盟”と呼びましょう。希望の同盟、一緒ならきっとできます」
──先日、米議会での演説で、国民の同意もなくアメリカの戦争に協力できるように安全保障法制の整備を夏までに実現することを勝手に約束してしまった安倍晋三首相。本人はいかにも満足げな表情を浮かべていたが、いよいよ世界公認でアメリカの犬に成り下がった瞬間でもあった。
その演説を聞きながら、“あの小説”のことが頭に浮かんだ人もいるだろう。本サイトでも以前紹介した、芥川賞作家・田中慎弥が安倍首相をモデルに書いた小説『宰相A』(新潮社)だ。同作で描かれる“アメリカによって統治される日本”という世界のなかで「戦争こそ平和の何よりの基盤であります」と演説をぶつ宰相Aの姿は、まさに現実の安倍首相とぴったり重なり合うようだった。
そんな田中が、先月号にあたる「新潮」(新潮社)5月号で、作家・中村文則と対談。じつはこのなかで、今度は中村が、現在安倍政権によって粛々と広げられている「全体主義」の空気に対し、異議の声を上げている。
中村といえば、2005年に『土の中の子供』(新潮社)で芥川賞を受賞。海外での評価も非常に高く、昨年にはアメリカの文学賞「デイヴィッド・グーディス賞」も日本人ではじめて受賞している。昨年末には、カルト教団の暴走を描いた長編小説『教団X』(集英社)を発表し、“いまもっとも影響力のある作家”である又吉直樹が絶賛したことでも話題を呼んだ。
その中村は、この対談で田中の『宰相A』を、“日本人を名乗るアメリカ人と、彼らに差別される旧日本人”という「親米保守 対 保守」の構図になっている点を挙げ、「支配側の「日本人」を全部アメリカ人にしちゃったという極端さがとても面白いと思いました」と評価。そこから話は政治をテーマにするときの“書き方”へと移るのだが、中村はこう切り出すのだ。
「現実の世の中が少しずつ全体主義の方向に傾きつつあると認識していて、そういう世界の中でどんな政治的な言葉を言えばよいのかって考えると、もしかしたら従来の方法では伝わりにくくなってるんじゃないかとも思ったんです。もっと剥き出しの言葉が要るんじゃないか?と」
「僕は今の日本の流れに対して危機感を持っていて。全体主義的傾向がもっとはっきり出てきた時にはもう遅い。そうなったら、誰も聞く耳を持たなくなる。だから「今のうちに」と思ってやってるところがあって」
現在の日本は全体主義に傾きつつある──。この指摘はまさしくその通りだろう。今年1月に起こった「イスラム国」による邦人人質事件では、安倍首相は救出責任を放棄したにもかかわらず「テロに屈しない」と息巻き、批判をシャットアウトした。それに呼応するかのように、殺害された湯川遥菜さんと後藤健二さんに対しても自己責任論が噴出。「国に世話をかけた奴が悪い」という、恐ろしい全体主義思想が蔓延していることが露わになった。
そして、中村が抱いている危機感は、いまの日本に漂う全体主義の空気によって、表現が制限されるのではないか?ということにも及ぶ。
「これはあくまで僕なりの定義ですが、表現の自由というのはそもそも、時の権力・強大なものに対して言いたいことを言えることだと考えています。だから表現の自由のもとで、踏み込んでもよい範囲がどこまでなのかと考えること自体が、まず間違っているんじゃないかなと」
踏み込んではいけない、許されない表現の範囲とは何か。その問題を考える上でまず頭をよぎるのは、サザンオールスターズ・桑田佳祐による“不敬”問題だ。昨年末の紅白歌合戦で披露したパフォーマンスが、「歌詞の内容が安倍政権批判だ」「日の丸にバツ印をつけるとは何事か」「ちょび髭姿はヒトラーを連想させる。安倍首相をヒトラーに準えるとは不敬極まりない」と批判が集中。ついには所属事務所前で抗議活動を行う者までが登場し、結果、桑田は謝罪コメントを発表するまでに追い込まれた件である。
それだけではない。先日の憲法記念日に開かれた集会で作家の大江健三郎が「安倍」と呼び捨てにしただけで、「品位がない」「これでは議論にならない」と非難を浴びた。同じように、爆笑問題の太田光がラジオ番組で「安倍っていうバカ野郎」「私は個人的に(安倍首相を)バカだと思ってますけど」と“安倍はバカ”を連発したときも、「名誉毀損発言だ!」と怒り出す者が続出。本サイトでも、思想家・内田樹と政治学者・白井聡のふたりが対談本『日本戦後史論』(徳間書店)のなかで“安倍首相は人格乖離、マッチョなのにインポなレイプ魔”と批評したことを紹介すると、「ゲスすぎる」「ネトウヨと同レベルのヘイト」だと抗議が殺到した。
このように、政権への批判に対して抑圧的な声が上がるのは“表現には踏み込んでもよい範囲、踏み込んではいけない範囲がある”と多くの人が考えているからだろう。人を口汚く罵ってはいけない、下品な言葉を使えばそれは批評ではなくたんなる悪口だ──そう思っているのかもしれないが、だが、中村が述べているように、権力に対してはどんな表現も許されるというのが、本来の「表現の自由」という権利なのだ。それは、わたしたちがもち得る、大きなものに抗う唯一の手段だからだ。
だが、こうした自由さえも、現在は制限されつつある。政権は批判を受けつけず、そればかりかテレビ局に圧力をかける。さらには、先日、安倍首相のTwitterの“中の人”が山本一太議員だと露呈した際、山本議員はブログで「あまりに悪質な誹謗中傷のツイート」について「投稿した人物を(正規の手続きを踏んで)特定させてもらう。公に抗議するためだ」と宣言した。罵詈雑言だとしても、権力側はそれを容認しなくてはいけないのだが、権力者が甘んじて受けるべき批判さえ脅しをかけて封殺しようとする。こうした政権の勘違いも甚だしい態度に国民はもっと怒るべきなのに、むしろ自主的に「批判をするときは正々堂々と」などと言論に“範囲”を設け、自由を制限している。
このような現状に、中村は文学者として並々ならぬ危機感を抱いているのだろう。「僕は、この日本という国に、僕が言う意味での表現の自由が制限される、戦前・戦中のような時代がやってきたときのことを想像してみたんです」と言い、「そのときに発禁に一番近い本は何だろう? と思うと、まずは『はだしのゲン』。その次が『宰相A』だと感じました。『はだしのゲン』は、もう実際チクチクいじめられている」とシミュレート結果を述べている。そして、田中が『宰相A』をいま書いた理由を、このように考察するのだ。
「もしかしたら、書けるものが書けなくなるっていう危機感じゃないですか? 小説を書く自分を邪魔する存在が現れるかもしれないという危機感。今じゃなきゃ『宰相A』みたいな小説は書けないと無意識に判断したのかもしれませんよ。事実、五年後だったらこの小説は攻撃を受けたかもしれないし。今だって、山口の図書館から消されるってことが絶対に起こり得ないわけじゃないですよ? 表面的には「善」のような理由で」
「戦時中にナチスが色々な本を燃やしたんですけど、そういうのって僕らからすると、「ナチスだから、それぐらいやるだろ」と思っちゃうじゃないですか。でも、当時の人たちは中世のおとぎ話のようなことが目の前で行われていることにとても驚いたらしいんですよ。今もそうした驚きが起こり得るかもしれない流れのなかにあって、作家としての脳が今じゃないとこの小説は出せないと判断したところもあったのかもしれないですよ」
中村は「僕はね、窮屈な時代が完全にスタートする前にいろんなことを言う必要を感じているんです」と言う。もちろん、中村は権力から制限をかけられることだけを危険視しているわけではない。「「空気」は本当に怖くて、誰も聞く耳をもたなくなる」と、大衆の姿勢をも憂虞しているのだ。
哲学者であるハンナ・アーレントは、『全体主義の起源』のなかで、〈全体主義運動は大衆運動であり、それは今日までに現代の大衆が見出し自分たちにふさわしいと考えた唯一の組織形態である〉と書いている。全体主義とは、権力側の発動だけではなく、大衆が迎合して生まれるものだ、と。
だからこそ、わたしたちは口をつぐんではいけない。言いたいことを言いつづけること。言いたいことを言えない状況に抗い、批判しつづけること。それをやめたとき、この社会からはほんとうに自由が消えるだろう。「(いまは)けっこうギリギリの時かなって」という中村の警鐘が、重く響く。
(水井多賀子)
(※太字・色字などの強調と写真は、武田による)