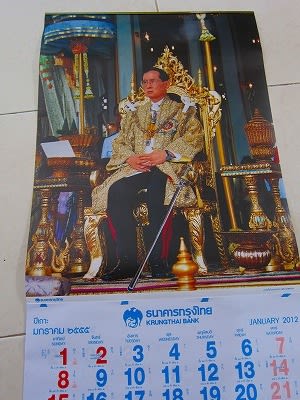朝、カウンターパートのビュウがあせっている。
「さちえ、だめ、今日はここでガイドブックを完成させてちょうだい。」
ちょうどつい先日近所に住んでいると分かった日本人女性が
配属先、第9特別教育センターに見学に来たところで、タイ人のご主人と子ども一緒。
センター長や副センター長たちは歓迎ムードになり、
私にセンター内を案内するようにといったところだった。
今日は午前中は授業をしっかりやりたいと、念入りに準備したところだったので、
そ、そんな!
子どもたちと一緒に活動に参加してもらえればいいなと思っていた私のもくろみが変わり、
案内する時間はさすがにない!と私もあせっていた。
そこに、カウンターパートの一言。
会議室に腰を落ち着けて、午前中にガイドブックを完成させるようにという。
「ガイドブックが完成しないと日本に帰ってはだめ!」
というビュウに、
「それはうれしい!帰らなくてもいいの?」なんて言ったら、
いつも怒らないタイ人のビュウでも怒るんじゃないかと思うくらいにカッカしている。
「今日の午後には印刷屋に持って行かなくちゃ。
さちえ、トンジャイローン!(あせってちょうだい!)」
こんなことを言われるとは意外で、今まで頼んだ翻訳作業が遅れに遅れてひやひやして
相談したときにも
「そうなの。 でもマイペンライ(大丈夫)」
と一言ですまされ、あせるのは私ばかり、
だけど、ここに来てカウンターパートのビュウがあせりやきもきしている。
私が自分でできることは全て昨日までで終わっているのだ、と伝えると
センター長の息子のトノが呼ばれ、推敲と手直し作業に入る。
そこからは、見学に来てくれた日本人女性も申し訳ないけどほったらかしで
会議室にこもる。

授業にも行かず、一緒に目次を作ったり、表紙を作ったり。
センター長もちょくちょく来て、「どうだ進み具合は?」と尋ねる。

ビュウは切羽詰まった感じで真剣そのもの。
トノはすいすいとパソコンを操り、それはそれは見事に次々仕事をやってのける。

この会議室では今まで先生達がなにやら会議をしたり、作業をしたりしてきた。
いつもそれを見ながら、私には入れない分野なのだろうなと、少し寂しく思っていた。
それが、今はプロジェクトと名うって一緒に作業をしている。
センター長の差し入れるスムージーを飲みながら、一緒に話しながら。
ビュウの必死さとは裏腹に不謹慎かもしれないけれど、
やっと私は一緒に仕事できる同僚になれた気がして、少し嬉しい。

ものすごいスピードで文章の体裁をタイ風にととのえ、
「はじめに」「おわりに」「目次」そして表紙と裏表紙をつくってしまう2人。

「はじめに」は二人であれこれ話し合いながらこんなに長く書いた。

内容は
「この本は日本の国際協力機構JICAとの連携をもとに作ったものです。
自閉症の子どもをもつ親と教師のためのガイドとして、コンケン第9特別教育センターから提供します。
日本で実践され、わかりやすく書かれた本で、自閉症を知りたい人たちにとってとても役に立つものです。」
と、おおざっぱに言うとこのようなこと。
最後に私の写真を入れると昨日も言っていたが、 (→ 過去ブログ
「ガイドブック作りの夕べ」)
写真には詳しい経歴もつけて、最後にどどーんと載せるのがタイ式。
名前に、チューレン(あだ名)の「サーイ」もしっかりと書かれ、誕生日まで表記する。

真剣な作業がおわって、昼ご飯も
「今日は急いで食べて!」
とせかされ、午後、印刷屋へ向かう。
一軒目の印刷屋では、今は仕事が多くてとても引き受けられないと断られ

二軒目の印刷屋へ向かう。

「ダイカー」(できます)の言葉に安心する私たち。
データを渡すと文字や絵がすっかりずれてしまっている。
これでいいの?修正しなきゃ、と言うけれど、この修正は印刷屋がやってくれるのだという。
原本も見たことがない印刷屋がやってくれる?
そんなこと可能なの?
と思うが、可能なのがタイなのだろうと思う。

ポケットブック風に作ってほしい、急いでいるので最速でと頼む。

できあがりは、3月10日。
コンケンを出てバンコクに上がるのが15日。
スムーズに行けば間に合うが、何があるか分からないのがタイなので安心はできないなと思う。
印刷屋から出て車まで歩くとき、ビュウが固かった表情を崩し
「あああー! リアップローイ! サバーイレーオ!」
(できたー! ほっとしたー!)
と大きな声で言う。
トノに 「ありがとうありがとう」とお礼を言うビュウ。
そして、「ディージャイ(うれしい)」とつぶやくように言った。
その時、私の心配をいつも「マイペンライ(大丈夫)」で一蹴していたビュウが
いつからだったのか、昨日今日からか、もっとずっと以前からかわからないけれど、
このガイドブック作りで、とてもとても気苦労していて、負担をおっていたのだと気づいた。
原稿がおおかた完成した時点で、先生達との話し合いもできてほぼ目的達成の私としては
そこでホッと焦りを解いた。
ビュウは私とは逆にそこからが、私の帰国までに間に合うかどうかと焦った。
私たち二人はちょっとかみ合わなかったけれど、
ビュウのもらした「ディージャイ(うれしい)」の一言が、
ビュウの負担と一生懸命さを表していて、
私はそこではじめて、本当に完成を願ってくれている気持ちを感じとった。
車の中でもホッとした顔で、今までにない笑顔。

配属先に戻ると副センター長やセンター長たちが「どうだった?」と聞く。
ガッツポーズをして、喜びを見せるビュウ。
「トンジャイローン!(あせってちょうだい)」と言われたのは
ええ?今までさんざん私焦ってたのに!?と、正直心外だったのだけど、
ビュウから見れば、もっとあせってよ、といいたくなるほど私は涼しげに見えたのだろう。
うれしい、楽しい、好き! という感情の表出は抵抗なくできるが、
苦しい、大変だ、こんなことで困っている、という表出が下手な所がある私。
言い訳や説明をすることで関係が悪化するのをおそれて、何も言わずに黙ってしまうときもよくあり、
誤解されたままでいても、それならそれでもいいかとあきらめてしまう性格。
でも、言わないと分からないこともある、表出しないと分かってもらえないこともある。
なんだか、今日は
さちえはちっとも焦ってないんだから、もう!
という感じになってしまったけど、これはどうしようか、言うべきか言わざるべきか。
ビュウの嬉しそうな顔を見ていると、私も笑ってしまって、今さらもういいか、という気になる。
これがいけないのかな。
タイ人の最後のラストスパート力はすごい、とはよく聞いていたけど、
本当にタイ人のこの底力、能力の高さには驚かされた。
表と裏の表紙には 第9特別教育センターのマークとJICAのマーク。
人と人がつながって一緒に仕事をして、ひとつのものをつくり、
その人が背負っているバックグラウンドである国同士もつながっていると
そんな気になる。


ふう、終わった終わったと一息ついていると、
「さちえの写真を30枚くらいちょうだい。」
「さよなら ってどう書くの?」
と、先生達がやってくる。

センター長がきて、
「さちえ、2日は送別会だ、忘れるなよ。忘れたら日本に返さないぞ。 ワハハ」と笑う。
写真でスライドショーを作るとか、横断幕を作るとか、
私のすぐそばで話し合っている。
私一人の送別会って、ものすごく照れるし、恥ずかしいし、なにより
別れを実感して、いやだー と思うのだけど、
皆さんの好意をありがたくいただきます。

「さよなら」はもう会えないようなニュアンスがあって、好きじゃない、だから
「さよなら」じゃなく「またね」にしてください。
とお願いする。
「またね」の言葉はいったい 何に使われるのかな。
2日のお楽しみ。

やっとのことでここまできた ガイドブック。
10日に完成、さて、予定通りになるか。