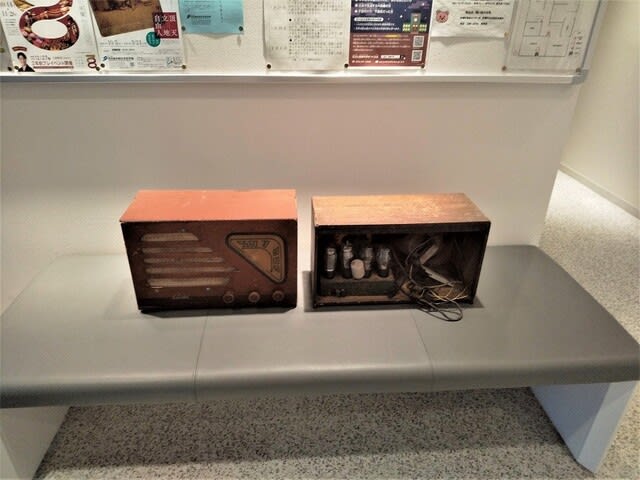【パーソナリティー(personality)】を辞書で引くと複数の解説がある。
その1つが【ディスクジョッキーなどの番組担当者】。
つまりパーソナリティは、主に【ラジオの喋り手】として認知されている。
訓練で培った明瞭な発音と発声のスキルを備え、
私情を挟まず原稿を正確に読む「アナウンサー」とは、ちと違う。
状況や制作側の意図、聞き手の求めなどに即応し、
個性を交えた豊かな表現で魅了するのが「パーソナリティ」。
--- となるだろうか。
日本のラジオ業界に於けるパーソナリティの黎明は、
深夜放送が人気を博し始めたあたり。
昭和30年代末~40年代初頭頃に登場したとするのが一般的。
だが、そのプロトタイプは大戦末期に遡る。
--- というのが僕の推測だ。
ほんの手すさび 手慰み。
不定期イラスト連載 第二百七弾「東京ローズ」。
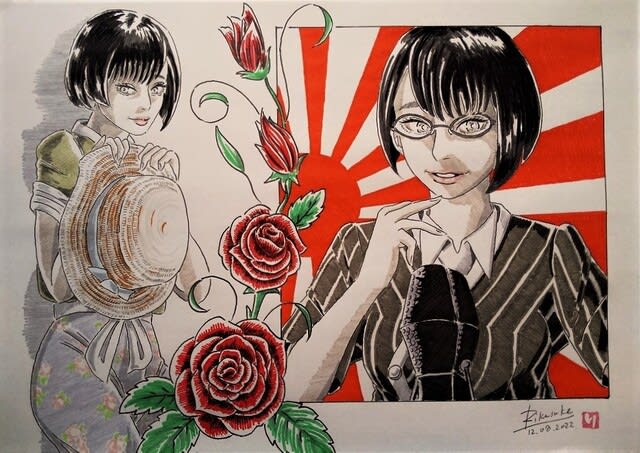
[ This is “ZERO HOUR” from TOKYO.
トーキョーから平和と愛をこめてお届けします。
アメリカの坊やたち、いかがお過ごしですか?
作戦は順調かしら?
目指す硫黄島の守備隊は準備完了。
カミカゼアタックも沢山待ち構えているわ。
一体何人の兵隊さんが命を落とすことになるのかしらね。
ところで、本国にいるあなたの恋人や奥様はお元気?
今頃、他の殿方に抱かれているかもね。]
物言いは上品ながら、なかなかの毒舌。
ラジオ番組「ゼロ・アワー」は、狙い通り、リスナー(米兵)の心をかき乱す。
ある時は、手強い敵軍に戦慄し、
ある時は、郷愁を掻き立てられ、
ある時は、恐怖に身を震わせた。
そして、バズった。
死と隣り合わせの緊張感の中に身を置く男たちの多くが、
その棘のある甘いハスキーボイスに魅了されたという。
いつしか彼女は「東京ローズ」と呼ばれ、
オンエアを待ちわびる米軍のラジオスターになった。
戦後、来日した従軍記者は、躍起になって「東京ローズ」を探し求めた。
ロサンゼルス出身の日系2世が名乗り出るも、確信には至らず。
そもそも「ゼロ・アワー」に係わった女性は複数いたとされ、
その正体は迷宮入りした。
声以外は全くの謎。
ミステリアスなパーソナリティは、歴史の霧の彼方に消えた。
確かなのは「ゼロ・アワー」が、当時、他に類のないプログラムだったということ。
選曲は洋楽ヒットナンバーやポピュラーソング。
喋り手の個性を前面に押し出し、囁くように語りかける全編英語のトーク。
20年後の未来を彷彿とさせる斬新な構成は、
魁(さきがけ)と言える。
だが、終戦を機にぷっつりと途切れてしまった訳だから、
やはり「戦時下の謀略放送」という特異な状況に咲いた、
徒花(あだばな)なのかもしれない。