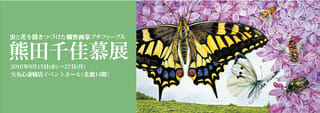毎年楽しみにしている「伝統工芸展」
今年も見てきました
(写真は協会HPからお借りいたしました)

受賞作品の中で特に印象に残っているのがこの3作品
「縄文」というタイトルの花かご
透け感のある竹細工なのに、縄文土器のようなおおらかさ
力強さがかんじられます
沈金の飾箱「緑風」
夏の強い日差しを避けて日影で羽を休める糸トンボ
シルエットなのに生き生きとしていました


一番好きな作品
截金飾箱「皓華」(きりかね飾り箱・こうげ)
細く細く切ったプラチナ箔を使って雪を表現されてます
作者は、なんと、4人のお子さんのママさんです
アトリエはリビングのテーブルだそうです。
截金細工の人間国宝でいらしたお母様の技を受け継いで
いかれることでしょう

どれもこれも素晴らしくて、気がついたら2時間以上
過ぎていました。
毎年、会期が短いので残念です。
アトリエ・ラ・ヴィータ
今年も見てきました
(写真は協会HPからお借りいたしました)

受賞作品の中で特に印象に残っているのがこの3作品
「縄文」というタイトルの花かご
透け感のある竹細工なのに、縄文土器のようなおおらかさ
力強さがかんじられます
沈金の飾箱「緑風」
夏の強い日差しを避けて日影で羽を休める糸トンボ
シルエットなのに生き生きとしていました


一番好きな作品
截金飾箱「皓華」(きりかね飾り箱・こうげ)
細く細く切ったプラチナ箔を使って雪を表現されてます
作者は、なんと、4人のお子さんのママさんです
アトリエはリビングのテーブルだそうです。
截金細工の人間国宝でいらしたお母様の技を受け継いで
いかれることでしょう

どれもこれも素晴らしくて、気がついたら2時間以上
過ぎていました。
毎年、会期が短いので残念です。
アトリエ・ラ・ヴィータ