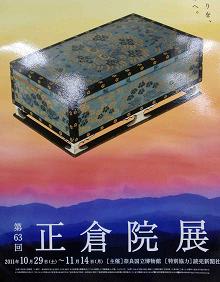山で出会った虫達
クヌギの樹液に集まる虫を狙うチビカマちゃん
待ち伏せてます
樹液にはアルコール成分が入っているので、酔っ払って動きが鈍くなった
虫がいるのです
でも、この後、子供に捕まえられてしまいました・・・
今頃、元気でいるかな?

玉虫
榎や欅の葉を食べます
捕まえるのは簡単なので、この日も手にとって観察。
お腹や足まで全身くまなく、玉虫色できれいです。
観察が終わるのを待ちかねたように飛んで行きました。

夏の虫たちは、そろそろ次の世代に命を繋いで、役目を終えようと
しています。
また、来年!!
HP アトリエ・ラ・ヴィータ はこちらから
クヌギの樹液に集まる虫を狙うチビカマちゃん
待ち伏せてます
樹液にはアルコール成分が入っているので、酔っ払って動きが鈍くなった
虫がいるのです
でも、この後、子供に捕まえられてしまいました・・・
今頃、元気でいるかな?

玉虫
榎や欅の葉を食べます
捕まえるのは簡単なので、この日も手にとって観察。
お腹や足まで全身くまなく、玉虫色できれいです。
観察が終わるのを待ちかねたように飛んで行きました。

夏の虫たちは、そろそろ次の世代に命を繋いで、役目を終えようと
しています。
また、来年!!
HP アトリエ・ラ・ヴィータ はこちらから