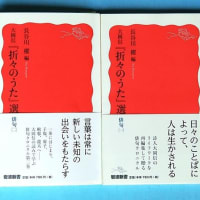前回のレビューで少し書いたのでパスしようとかんがえていた。
しかし・・・しかしわたし的に面白すぎたので、簡単に感想を綴っておく気になった。
司馬遼太郎は私小説はまったく書かなかったが、己を露出しないのではない。
本編には、ためらったり、あせったり、気をもんだり、ひとをからかったりからかわれたり、そばに舌鼓を打ったり、書物の山を探索したり、インタビューしたり、バスに揺られたり、ベッドに横たわって叡山の眺望を愉しんだり。
普段着の司馬さんが、じつに生きいきと躍動しているのが、文面からぴりり、ぴりりとつたわってくる(*^。^*)
“歴史を紀行する”司馬遼太郎の面目躍如なのである。
司馬さんファンはもちろん、そうでない読者も、きっとしびれるに違いない。とくに中高齢者はそうだろう、と思われる。
まずは内容紹介。
《「法華大会」を知人がうけることで、20代のころから見たいと思いつづけてきた、その天台宗の宗教行事を拝見する機会を得る。まず坂本の街並み、赤山禅院、曼殊院門跡と、ほうぼうの登山口を周到にも訪ね直した著者は、“包囲網”を絞るかのように比叡山上へのみちをたどる。半生をかけて理解した最澄や天台の真髄をわかりやすく呈示し、いまなお人を惹きつける叡山の魅力を描く。》BOOKデータベースから
叡山という存在が歴史的にどんなものであったか、ラフなスケッチとともに、大要が徐々に明らかにされてくる。
着流しの随筆に近い味わいがある。ところがそうかんがえてのんびりしていると、司馬さんのシナイが、真っ向からビシリと面を撃つ。
叡山というのは1300年にも渡る、仏教の受容の崇高と堕落のシンボルであったのだ。いうまでもないが庶民大衆を中心に布教した、あの鎌倉仏教を生み出したのが、比叡山延暦寺である。
その歴史と現在をこんなふうに書いたものを、恥ずかしながらわたしはこれまで読んだ経験がない。
円仁ならともかく、元三大師良源なんてはじめて聞いた。叡山でお大師といえば、伝教大師最澄のことではなくて、この良源のことをいうそうである。
《大書院を辞し、小書院の「黄昏の間」の軒下から片流れだけの屋根をつけた茶室にすわってみた。
有名な八窓軒(はっそうけん)である。
(中略)
その窓にはむろん紙障子が貼られている。外光は紙障子によってなまの光線のもつけばけばしさが殺され、寂光という思想的な明度に変化させられる。
この時代のひとびとの感覚に、カラーテレビの輝度の高い色彩に馴らされたわれわれは、とうてい及びそうにない。》(136ページ「ギヤマンの茶碗」)
《僧でありながら、俗権から栄爵を受けるのが叡山の風であった。道元は、これを愛名(あいみょう)といった。俗な名誉を愛するという意味である。
「正法眼蔵」のなかで愛名について述べ、
「愛名は犯禁(はんきん)よりも悪し」
と、はげしく規定している。理由は犯禁は一時の非だが、愛名は一生の累であるからだ、という。道元は、行持という言葉をよくつかった。行持とは仏道を修行する者が努めるべき生き方をいう。愛名を捨てるのが行持だという。
「うけざるは行持なり、すつるは行持なり」
と、激烈にいう。道元はついには、愛名の徒のことを「魔党」とさえいっている。》(166ページ タクワンの歴史)
《空海の私寺にちかかった高野山の場合、民衆との接触が容易であった。
「高野聖」
という奇妙な非僧非俗の布教者の活躍が、鎌倉・室町期という「平安仏教」の危機のなかで、高野山をどれほど救ったかわからず、こんにちなお高野山が、多分に世俗的ながら、土くさい信仰にむすびついているのは、そのおかげである。
鎌倉・室町期の高野山にあっては、正規の僧はただ学問をしていればよかった。非正規の存在である聖(ひじり)という半ば乞食の存在が教義の販売を請けおって、常時数千人という人数でもって諸国を歩いていた。
空海―弘法大師―の超人的な神秘譚を創作しては諸国に撒きちらして歩いたのは、この聖たちであった。
叡山がもつ品のよさとはちがい、高野山には土俗がもつたくましさが、多少のまがまがしい色彩とともに残っている。空海の性格というよりも、空海よりもはるかな後世に出現して、何世紀ものあいだに、延十数万人も諸国を歩いていたかとおもえる聖たちの体臭がそれであろう。》(168ページ タクワンの歴史)
まだまだ引用を重ねたいのだけれど、きりがないのでやめておく。司馬遼太郎という卓越した知性が、見たり、かんがえたり、歩いたりして、そのいわば上澄みが、この歴史紀行の臨機応変で、しかも繊細な文体によって掬い採られている。
司馬さんの手の中には、にごりもあるし、木の葉やわずかなゴミも浮いている。単なる観光地巡りではまったくないし、写真をたっぷり使ったパンフレットの軽薄さもない。
司馬遼太郎の憂い顔が、ページの向こうに透けて見える。
それは感動的な、じつに感動的な光景である。
わたしなど、司馬さんが感動していることに感動する( -ω-)
愛読者とは、そういうものなのだろう。読む前から予測はしていたが、その予測を上回る出来映えである。
・黒谷別所
・鬱金色の世界
・問答
・法眼さん
最後のこの4章から、司馬さんのときめきと感動がダイレクトに伝わってくる。「法華大会」の模様を現場中継なみに詳しく、手を変え品を変えて叙するあたりは、筆が躍っているのが、わたしにもわかる。
そのことに、心底感動させられた。

(こういう関連本も拾い読みした。しかし・・・つまらないなあ)

(左が新、右が旧版)

(こんなカバーがついていた時代があった)

(準備してある朝日文庫のうち2冊)
評価:☆☆☆☆☆
※街道をゆく公式ホームページ
https://publications.asahi.com/kaidou/index.shtml
(43冊すべて読むのはムリだろうなあ、きっと)
しかし・・・しかしわたし的に面白すぎたので、簡単に感想を綴っておく気になった。
司馬遼太郎は私小説はまったく書かなかったが、己を露出しないのではない。
本編には、ためらったり、あせったり、気をもんだり、ひとをからかったりからかわれたり、そばに舌鼓を打ったり、書物の山を探索したり、インタビューしたり、バスに揺られたり、ベッドに横たわって叡山の眺望を愉しんだり。
普段着の司馬さんが、じつに生きいきと躍動しているのが、文面からぴりり、ぴりりとつたわってくる(*^。^*)
“歴史を紀行する”司馬遼太郎の面目躍如なのである。
司馬さんファンはもちろん、そうでない読者も、きっとしびれるに違いない。とくに中高齢者はそうだろう、と思われる。
まずは内容紹介。
《「法華大会」を知人がうけることで、20代のころから見たいと思いつづけてきた、その天台宗の宗教行事を拝見する機会を得る。まず坂本の街並み、赤山禅院、曼殊院門跡と、ほうぼうの登山口を周到にも訪ね直した著者は、“包囲網”を絞るかのように比叡山上へのみちをたどる。半生をかけて理解した最澄や天台の真髄をわかりやすく呈示し、いまなお人を惹きつける叡山の魅力を描く。》BOOKデータベースから
叡山という存在が歴史的にどんなものであったか、ラフなスケッチとともに、大要が徐々に明らかにされてくる。
着流しの随筆に近い味わいがある。ところがそうかんがえてのんびりしていると、司馬さんのシナイが、真っ向からビシリと面を撃つ。
叡山というのは1300年にも渡る、仏教の受容の崇高と堕落のシンボルであったのだ。いうまでもないが庶民大衆を中心に布教した、あの鎌倉仏教を生み出したのが、比叡山延暦寺である。
その歴史と現在をこんなふうに書いたものを、恥ずかしながらわたしはこれまで読んだ経験がない。
円仁ならともかく、元三大師良源なんてはじめて聞いた。叡山でお大師といえば、伝教大師最澄のことではなくて、この良源のことをいうそうである。
《大書院を辞し、小書院の「黄昏の間」の軒下から片流れだけの屋根をつけた茶室にすわってみた。
有名な八窓軒(はっそうけん)である。
(中略)
その窓にはむろん紙障子が貼られている。外光は紙障子によってなまの光線のもつけばけばしさが殺され、寂光という思想的な明度に変化させられる。
この時代のひとびとの感覚に、カラーテレビの輝度の高い色彩に馴らされたわれわれは、とうてい及びそうにない。》(136ページ「ギヤマンの茶碗」)
《僧でありながら、俗権から栄爵を受けるのが叡山の風であった。道元は、これを愛名(あいみょう)といった。俗な名誉を愛するという意味である。
「正法眼蔵」のなかで愛名について述べ、
「愛名は犯禁(はんきん)よりも悪し」
と、はげしく規定している。理由は犯禁は一時の非だが、愛名は一生の累であるからだ、という。道元は、行持という言葉をよくつかった。行持とは仏道を修行する者が努めるべき生き方をいう。愛名を捨てるのが行持だという。
「うけざるは行持なり、すつるは行持なり」
と、激烈にいう。道元はついには、愛名の徒のことを「魔党」とさえいっている。》(166ページ タクワンの歴史)
《空海の私寺にちかかった高野山の場合、民衆との接触が容易であった。
「高野聖」
という奇妙な非僧非俗の布教者の活躍が、鎌倉・室町期という「平安仏教」の危機のなかで、高野山をどれほど救ったかわからず、こんにちなお高野山が、多分に世俗的ながら、土くさい信仰にむすびついているのは、そのおかげである。
鎌倉・室町期の高野山にあっては、正規の僧はただ学問をしていればよかった。非正規の存在である聖(ひじり)という半ば乞食の存在が教義の販売を請けおって、常時数千人という人数でもって諸国を歩いていた。
空海―弘法大師―の超人的な神秘譚を創作しては諸国に撒きちらして歩いたのは、この聖たちであった。
叡山がもつ品のよさとはちがい、高野山には土俗がもつたくましさが、多少のまがまがしい色彩とともに残っている。空海の性格というよりも、空海よりもはるかな後世に出現して、何世紀ものあいだに、延十数万人も諸国を歩いていたかとおもえる聖たちの体臭がそれであろう。》(168ページ タクワンの歴史)
まだまだ引用を重ねたいのだけれど、きりがないのでやめておく。司馬遼太郎という卓越した知性が、見たり、かんがえたり、歩いたりして、そのいわば上澄みが、この歴史紀行の臨機応変で、しかも繊細な文体によって掬い採られている。
司馬さんの手の中には、にごりもあるし、木の葉やわずかなゴミも浮いている。単なる観光地巡りではまったくないし、写真をたっぷり使ったパンフレットの軽薄さもない。
司馬遼太郎の憂い顔が、ページの向こうに透けて見える。
それは感動的な、じつに感動的な光景である。
わたしなど、司馬さんが感動していることに感動する( -ω-)
愛読者とは、そういうものなのだろう。読む前から予測はしていたが、その予測を上回る出来映えである。
・黒谷別所
・鬱金色の世界
・問答
・法眼さん
最後のこの4章から、司馬さんのときめきと感動がダイレクトに伝わってくる。「法華大会」の模様を現場中継なみに詳しく、手を変え品を変えて叙するあたりは、筆が躍っているのが、わたしにもわかる。
そのことに、心底感動させられた。

(こういう関連本も拾い読みした。しかし・・・つまらないなあ)

(左が新、右が旧版)

(こんなカバーがついていた時代があった)

(準備してある朝日文庫のうち2冊)
評価:☆☆☆☆☆
※街道をゆく公式ホームページ
https://publications.asahi.com/kaidou/index.shtml
(43冊すべて読むのはムリだろうなあ、きっと)