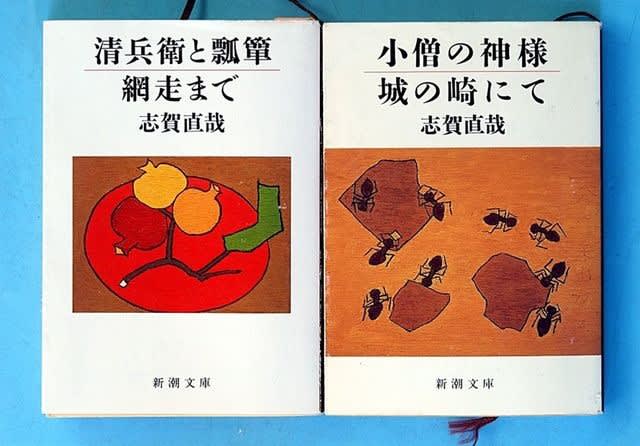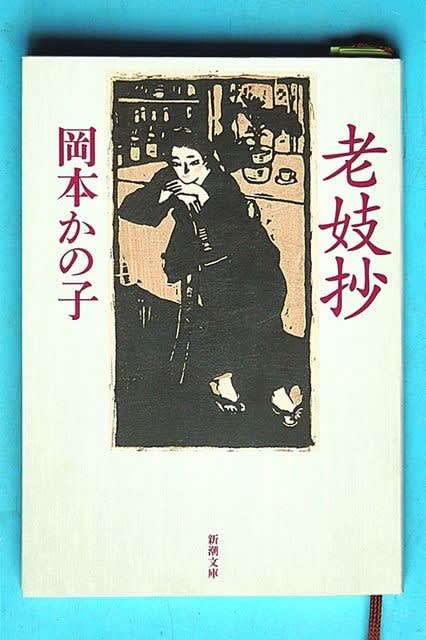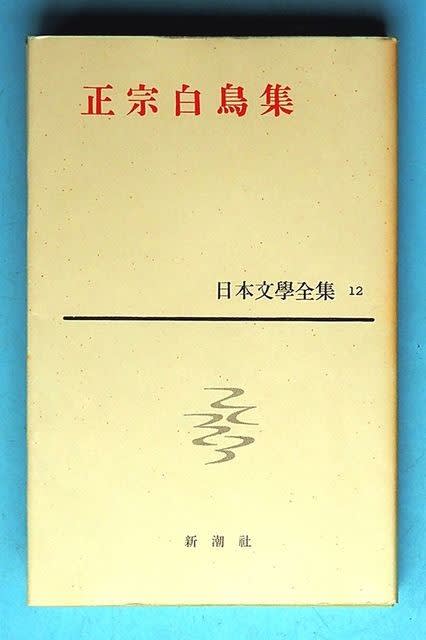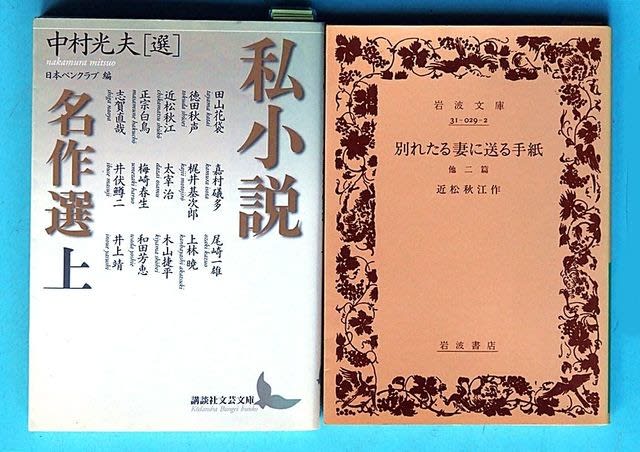(「芥川龍之介」ちくま日本文学全集 1991年刊 「戯れに」が収録されている文庫本はこれだけ)
たしか吉本隆明さんにうながされてだったと思うけど、芥川の“通奏低音”に耳をましたことがあった。
《戯れに(1)
汝(な)と住むべくは下町の
水(み)どろは青き溝(みぞ)づたい
汝が洗湯の往き来には
昼も泣きつる蚊を聞かん》
《戯れに(2)
汝と住むべくは下町の
昼は寂しき路地の奥
古簾(ふ . . . 本文を読む
(こんなアンソロジーが宝島社から刊行れている)
名作短篇と見なされているものを列挙してみよう。
・羅生門
・鼻
・芋粥
・藪の中
・地獄変
・蜘蛛の糸
・杜子春
・戯作三昧
・玄鶴山房
・枯野抄
・河童
・歯車
・侏儒の言葉
ざっと数えても短篇に限ってこれだけあるのは、他の作家を圧倒している。つまり純文学作家、作品として。
大正時代は、芥川龍之介の時代であったのだ。「第四次新思潮」の . . . 本文を読む
(豪華版日本文学全集16 芥川龍之介 66.12.11のゴム印が押してある)
どこの書店へいっても、彼の本は必ず棚の在庫がある。それだけ現役作家のごとき人気作家なのである。オビ広告から引用させてもらう。
《知性と懐疑の芸術。豪華版日本文学全集第4回配本 定価480円。
理知派とか新技巧派とよばれた芥川の文学の本質は、その豊かな教養と知的な技巧の冴えにある。特に新鮮な短篇小説に芸術至上 . . . 本文を読む
■「芥川龍之介」関口安義(岩波新書 1995年刊その後アンコール復刊2007年)
オビ広告に《ご要望にお応えしてアンコール復刊》とある。また、《清新作家像を描く必携の本格的評伝》とも。
評伝はいたってまじめで、古色をおびているが、おもしろくないわけではない( -ω-)
いままで関口安義さんのお名前は存じあげなかった。都留文科大学の名誉教授で芥川とその周辺人物の評伝をずいぶん書いておられる。(2 . . . 本文を読む
「網走まで」「灰色の月」は志賀直哉の代表作として、ご存じの方が多いだろう。これまで3-4回は読んでいる。そしてまた、読み返した。“読み返すことができる”というのが、名作の条件であるのは、当然だと思える。
以前、こうに書いたことがあった。
《たとえば、堀辰雄の「辛夷の花」(「大和路・信濃路」の一編)と「網走まで」を、以前読み比べたとき「ああ、そうか。踏み込みの鋭さがまるで違う」と思ったものだ。
ど . . . 本文を読む
(なぜか2冊ある講談社学芸文庫の「抹香町・路傍」)
■「抹香町・路傍」川崎長太郎(講談社文芸文庫 1997年刊)
川崎長太郎はとても地味な存在だと思われる。
私小説家のうちにあって、太宰治のような破滅型とも、尾崎一雄のような調和型ともことなっている。消えそうで消えない熾火でもあるかのように、しんしんと燃えつづける作家魂は、
正宗白鳥、徳田秋声、宇野浩二につらなる小説家と一般的には . . . 本文を読む
■「忍び草」中央公論社 昭和47年刊(単行本)
■「鳳仙花」講談社文芸文庫 1998年刊(文庫本)
昭和47年=1972年
1998年=平成10年
「忍び草」 301ページ
1.うろこの記録 新潮 昭和41年
2.ある女流作家の一生 新潮 昭和38年
3.海のほとり 早稲田文学 昭和45年
4.路傍 群像 昭和47年
5.忍び草 群像 昭和 . . . 本文を読む
困ったことではあるが、老化現象が頭や体を衰えさせ、この1-2年、何百ページもある長篇小説が読めなくなってしまった。いずれはこうなるとはかんがえていた。しかし、老化のペースは、予想より4-5年はやくやってきた(´ω`*)
何度となく書いてはいるが、晩酌をやめれば、多少は持ち直すかな、わからんけど。
・・・というわけで、短篇小説のありがたさが、ぐ~んと身に沁みてくる(笑)。
アルコールを断てばいいとは . . . 本文を読む
■「正宗白鳥集」日本文學全集第12巻(新潮社 昭和38年刊)
正宗白鳥を最初に意識したのはいつだったろう。
たぶん、深沢七郎の「楢山節考」(新潮文庫)に収められた「白鳥の死」を読んでからだと、ぼんやり思い出す。20代で読んだ「楢山節考」は、当時はじめて接したフランツ・カフカの短篇にも通じるショックをあたえられた・・・と思う。
「白鳥の死」はこの新潮文庫に入っている。
(現行の新潮文庫 . . . 本文を読む
■「私小説名作選 上」中村光夫選
近松秋江「黒髪」
《近代日本文学において独特の位置を占める「私小説」は、現代に至るまで、脈々と息づいている。文芸評論家・中村光夫により精選された、文学史を飾る作家十五人の珠玉の「私小説」の競演。》三省堂書店BOOKデータベースより
中村光夫といえば、私小説を排撃した批評家として名高いが、その中村光夫に、私小説のアンソロジーを編集させたところがミソ(*^。^* . . . 本文を読む