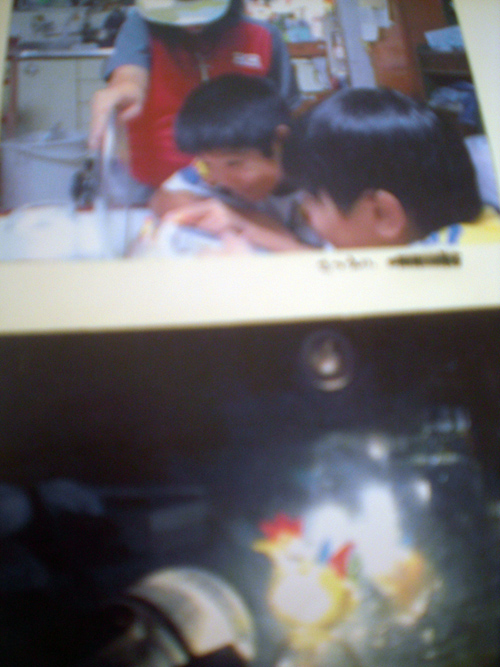
コメント欄で、
ブログで書いていらした、「ハイスコープ教育」について、
参考となる書籍をご紹介いただけないでしょうか?
という質問をいただいています。
ハイスコープ教育についてだけで1冊にまとめられた本が、
日本で出版されているのか、私はよく知らないのです。
私がハイスコープ教育について知ったのは、
『ナチュラルな子ども時代』という著書の中で、紹介されていたからです。
とても共感できる内容で、
私の自分の子たちにしていた教育法ととても近いものがあったため、
ネット等で論文を調べたりしながら情報を収集してきました。
勝手にリンクしても良いのかわからないので、
検索法を紹介しますね。
HIGH/SCOPE 学習
で論文等が検索できると思います。
計画ー実行ー再考
というサイクルで子どもに始めさせれる子ども主導の学習は、
わが子が小学生のころに、
かなりゆるゆるの関わり~から、
(遊びの場面で、子どもが材料やアイデアで相談ごとをしてきたら、それに乗り、
実行し、し終えて自分がしたことをおしゃべりしたがるのにゆっくり耳を傾ける)
計画ー実行ー再考のかかわりを記録に残す関わり~まで、
(子どもが工作や自由研究のコンテストに応募していました)
いろんな形で関わっていました。
全体で言うと、ゆるゆる8~9割、しっかり学習は、1割くらいです。
遊びが十分でないと、しっかりするときにエネルギーや創造性が溢れてこないです。
写真は小学4年生のときに息子が友だちといっしょに自由研究した『ホログラフィー』についての
調べていたときの写真です。
4年生なので、計画段階で、作文を書いていました。(低学年のうちは、言葉で私にやりたいことを相談するだけでした)

ハイスコープの学習をどのように家庭でしていたのか、わかりやすくなるかと思いますので、
4年生の頃の息子の計画段階の作文を載せますね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーマ『光の性質を利用して、ホログラフィーがつくりたい』
きっかけ
ある夜ぼくは、お姉ちゃんのへやにいって、
「映画がはじまりまーす」と電気を消した。
ビニールぶくろにマジックで絵をかいて、
うしろから懐中電灯でてらしたら、かべに映画みたいなのが、うつる。
お母さんに見せたら、「子どものころ、小学生向けの雑誌のふろくに、
映写機がついていたの。
アニメのフィルムをこんなふうにみたわ」といった。
映写機のことをいろいろ聞いているうちに、光をつかった実験がいろいろしたくなった。
ぼくは夏休み中、自由研究のテーマがなかなか思いつかなかった。
夕ごはんのとき「光の研究がしたいけど、もう2学期がはじまっちゃったから、
終わりだね」とがっかりしていったら、
「公募の本で、科学コンクールの募集を見たけど、まだだいじょうぶだったと思うわよ」
といった。
「じゃ、ホログラフィーを作りたい」と
急に思いついていった。
「ホログラフィーって何?」とお母さんが聞いた。
「立体の空中に浮かぶやつ」
「ああ、SF映画とかに出てくるあれね」
「それは無理じゃないかなぁ」
お父さんもお母さんも首をかしげた。
ぼくはいろいろやったらできるかもしれないと思うんだけどな。
「特別な条件の下なら、そう見えるかもしれないし、自分がやりたいテーマで
研究したらいい」とお母さんも賛成してくれた。
ぼくにはひとつアイデアがあった。
さばくにうかぶしん気ろうは、機械がないのに立体映像が見られる。
しん気ろうができるしくみを
探って、ホログラフィーの作り方がわからないだろうか?
ぼくの持っている『ドラえもん 不思議サイエンス』という本に、
「しん気ろうは、地面近くに
密度のちがう空気の層ができたときに起こる現象です。
下層に密度の大きい冷たい空気、上層に密度の小さいあたたかい空気があるときは、
得にある実際の像は、浮いて見えます。
反対に下層にあたたかい空気、上層に冷たい空気があるときは、像は沈んで見えます」と書いてある。
密度が均一でない空気中で光が曲がって見えるから、しん気ろうは見える。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これは、自由研究に応募するために書いた「きっかけ」にあたる作文なので、
計画
の時点で、作文にして書いています。
でも、普段は、とにかく、「こういうことがしたい!!」と子どもが言うときに、
親としては「えっ……」と迷う内容でも
よりくわしく聞くことが中心でした。
うちの子だけでなく、近所の子も、それから今の教室の子も
子どもは自分のアイデア、計画を話すことが大好きです。
それと、喧嘩したときの言い分もしっかり聞いてあげると、原稿用紙1枚分はしゃべります。
2、3歳の子も自分のやりたいことには、言いたいことや壮大な計画(外にバケツで水をまきたいとか…
部屋を真っ暗にして宇宙に行きたいとか……)を持っていますから、
とにかくそうした計画に、少し言葉を添えてあげながら
耳を傾け、実行につないであげていると、いつのまにかそれは文章にして書く行為に変わっていきます。
話を息子の自由研究に戻しますが……
ホログラフィーなんて、本当にできたのでしょうか?
なんと……できたのです!!
ガラスの屈折と目の錯覚を利用したもので、本当にホログラフィーと呼べるものかはわからないのですが、
いろいろ実験をやっているうちに、
空中に浮かぶ像を作ることができました。
できたときは、うれしかったですよ~!!
材料は、2記事前の写真……ガラスのコップ ガラス細工人形 ガラスの鍋蓋 懐中電灯です。



















