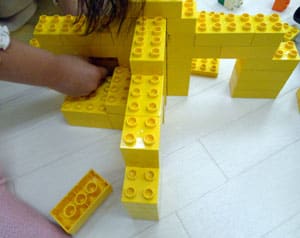今日は、自閉症スペクトラムの子と工作 で
2010年12月~2011年7月までのレッスンの様子を記事にしている
広汎性発達障がいの4歳半★くんのレッスン日でした。
幼稚園を一日お休みして通ってくれています。
ささいなことなのですが、上の文の「レッスンの様子」という言葉は、
最初、「成長」という言葉にしていたものを書きなおしたものです。
こうして、レッスンの記事を時間で整理して眺めると、
「★くん、すごく成長したな~。あんなこともできるようになった。
こんなこともできるようになった」と感激するのです。
でも、どうして「成長」という言葉を避けて、書きなおしたのかというと、
「成長」とか「発達」といった目に見える成果にこだわりはじめると、
結果的には、むしろ子どもの育ちを妨害することにしかならないからです。
なら、わざわざ教室に通ってもらって何を目指しているのかというと、
「子どもの世界を広げる」ということ、つまり縦に上方に「伸ばす」のではなくて、
その子を中心に球形のボールが膨張していくようなイメージで、
「広がる」ことを大事にしているのです。
ですから、
「わがままが言えなかった子が自分の要求をはっきり出すようになる」とか、
「隣のおばあちゃんに声をかけられると微笑むようになった」とか、
「散歩中、観察する動物や虫の数が増えた」とか、
能力アップとは無関係に思われるようなものも、「広がり」のひとつひとつとして
大切に育んでいるのです。
そうする中で、「あれっ?いつの間に?」という縦の上方向の伸びも確認できるのは
うれしいことです。
でも、最初から、それを意識して子どもと関わり始めたり、子どもを観察し始めると、
大きく丸く成長しようとしている畑の野菜を、いびつな型に押し込めて引き延ばそうと
するような不毛な努力に終わってしまう気がするのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お父さんとお母さんといっしょに虹色教室に来た★くんは、
プラズマプレイトというプラズマ光が指先にそって動く科学グッズと
お茶犬のドールハウスで、遊び始めました。
カミナリがピカピカ光っているとき、お人形がトイレに行くという設定で
ごっこ遊び(もどき)を始めました。
今日の★くんは、レッスン開始時から、私と目が合うたびに、
顔いっぱいに笑顔を浮かべて今からすることが楽しみでたまらないという様子でした。
よほど、前回会った時のユースホステルでの体験が楽しかったようなのです。
これまで★くんは、一本調子の、
ちょっと相手を責めるような口調で話をする癖がありました。
「何か嫌なことが起こりそうで怖いので、先に怒っておく」と言ったらいいような
防御が行き過ぎた身構えた物の言い方です。
それが、今日の★くんは、ちょっとおませな女の子がしなを作って笑顔を振りまくように、
小首をかしげた格好で、何ともいえないかわいらしい笑顔を、
何度も何度も、私や両親に向けていました。
★くんは、トイレネタが大好きで、
お母さんにも「便器を描いて!」とねだることが多いそうで、
お茶犬のドールハウスを取ってきたときも、遊ぶ前から、人形たちをトイレに
行かせる気満々、私がいっしょにトイレ遊びで盛り上がってくれるだろうという
期待でいっぱい……という様子でした。
前回までは、お茶犬ドールハウスといえば、
「トイレ、トイレ」と、あわただしくトイレにかけこむストーリーが
延々と続いていたのですが、
今回の★くんは、プラズマプレイトを持ってきてちょっとだけ新しい趣向を
取り入れる気らしく、
「カミナリだよ。ひとりでトイレに行ったらねぇ、怖いかもしれないよぉ!」と
怪談話でもするような口調で遊びをスタートしました。
私がマイメロディーの人形をトイレに入れると、
「じゃぁ、ぼくは、階段のぼろう」と、先生だけトイレの話で遊んでてね……
とでも言うように、アンパンマンやミニーちゃんの人形を2階に上げだしました。
そこで、私が、「私も2階に行きたいわ。上でいっしょに遊ぼ」と言うと、
「いいよ~」と調子がいい返事が返ってきました。
これまで★くんは、人形に会話をさせる形で遊びが続いたことはなかったのですが、
「でも、はしごがないから上に上がれない」と言うと、
手のひらをエレベーターのようにして降ろしてきて、
「さっ、これに乗って!上に行かせてあげる」と言いました。
その後、はしごを取ってきてかけたり、上の階で遊ぶなどのストーリーが展開しました。
広汎性発達障がいの子たちとお人形遊びを楽しむようにしていると、
遊びの幅が広がることはもちろん、ソーシャルスキルを教えたり、
双方向の会話のより自然で豊かなものに変えたりするときも、
とても伝えやすいツールになります。
ただ、シルバニアファミリーのお家やシンプルな木製のドールハウスは、
自閉症スペクトラムの子に、白い画用紙を与えたときのような不安を与えることが
多いようです。
トイレ、台所、玄関、階段、お風呂……など、具体的な何をすればよいのかわかる
閉ざされた空間があるもので、ひとつは、子どもがこだわっている好きなものが
含まれているようにすると、遊びがスタートしやすいように思います。
たとえば、子どもが玄関の靴箱を開け閉めするのが好きなら、
ドールハウスの玄関に、開け閉めできる靴箱(手作りOK)を置きます。
電気をつけたり消したりするのが好きなら、プッシュライトを天井に貼り付けます。
最初は、「もう夜だね。暗いから電気つけよ。パチ。」
「まぶしいまぶしい!電気消してー!電気消してー!パチ」の繰り返しで
遊びは、十分だと思います。
子どもは今の状態をしっかり受容していると、それを踏み台にして
自分から次のステップに進みます。
私のマイメロ人形をトイレに残して、自分の人形たちを2階に上げ出した★くんのように。
★くん、広汎性発達障がいの多くの子どもたちと同じように
他人の指示に従うのが苦手です。
でも、私の誘う遊びに、これまで面白かった体験からか信頼は寄せてくれているようで、
「★くん、見て!こんなのどう?」というと、気乗りしない様子で、
「それはいいんだよ」と、即座に却下することはよくあるものの、
少しすると★くんが、私の提案に似た遊び方をしてみせて、
「見て、見て。面白いよ。奈緒美先生も遊ぼうよ」と
自分発信の案に変えて、こちらを遊びに誘うということがよくありました。
私は、こうした広汎性発達障がいの子の対応を、
「いったん、拒否して、受け入れる」態度として大切に扱っていて、
その微妙な差異を調節して、バリエーションを豊かにすることで、
困った行動が減って、お友だちと遊ぶのもずいぶん上手になってくるな、と
感じています。
広汎性発達障がいのの子というのは、たいてい新しい展開を嫌がります。
でも、
そこに、いったん拒否することをOKとする受容的なまなざしがあって、
それを周囲にサラッと流してもらっていて、
(広汎性発達障がいのの子は他人の感情の変化に敏感なので、
子どもの拒否におろおろする大人の態度や、「やりなさい」と強制したり、
「やったら?」としつこく誘う態度で接すると、
頑なに拒否にしがみつくようになる子が多いです)
自分の気もちを新しい展開にならしていく静かな時間があると、
少し前の提案を受け入れたんだな……とわかる自分発信の提案が返ってくるのです。
そうやって、「いったん、拒否して、受け入れる」ことを何度も体験するうちに、
だんだん切り替えがうまくなって、拒否の言葉を口にせずに、
少しの間、首をかしげて考えている態度を取る程度で、
「じゃぁ、する」と取り組めるようにもなってきます。
広汎性発達障がいの子と心と心が通じ合う人間関係を作っていくことで、
「人への信頼感」が、「新しい挑戦への不安」を超えて、
素直に場に自分をゆだねることができるようになってくるのを実感しています。
広汎性発達障がいの子がそのように一度パターンとして形を学ぶと、
きちんと指示や提案に従えるようになってくる能力を利用して、
大人が次々と自分のさせたいカリキュラムや指導に子どもを乗せる目的で
大人の望む形に態度を変化させることを続けるとしたら、
一時期はうまくいっていたとしても、最終的には、破綻するように感じています。
それは、広汎性発達障がいの子が「いや」を乗り越えて指示に従えているのではなく、
「いや」を感じられないよう、「いや」が言えないように
しつけているだけの場合があるからです。
広汎性発達障がいの子が自分の好きなことを自由に繰り返し行うことを認めて、
その子の世界に大人の側が降りていって
いっしょにその子のファンタジーの庭で戯れる時間がたっぷりあってはじめて、
苦手なこちら側の指示に従ったり、提案に乗ったりすることも、
本人の達成感や満足感を満たす行動になっていくのだと思っています。

上の写真は、ユースホステルで「エレベーター作りが楽しかった」という★くんと、
教室内でエレベーターということにしたかごを
天井に付けているフックに引っかけて、吊りあげる遊びをしているところです。
 ←ユースホステルでエレベーター遊びをする★くん。
←ユースホステルでエレベーター遊びをする★くん。


私はエレベーターの一方の端を椅子に引っ掛けて、その先を車のおもちゃに結びました。
こうすると、車を移動させる力で、エレベーターを上に上げることができるのです。
これを見た★くんは、「ダメだよ。そんなの取って!」と繰り返し、しまいにひもを
工作で使っていたはさみで切ってしまいました。
そうして、しばらく手動で引っぱりあげたり、降ろしたりして遊んでいた★くん。

先ほどまで遊んでいたドールハウス(こうしたシンプルなドールハウスは、
取ってもらいたがっただけで遊んでいません)にひもを引っ掛けて、
後ろずさりしながら、「見て、見て。奈緒美先生。
こうすると、エレベーターがあがるんだよ」と得意満面で言いました。
★くんは、自分で運動の方向が変えられたことがうれしくてたまらない様子で、
引っぱったり、手を緩めたりして、満面の笑顔でした。
また、こんなこともありました。

★くんは、お片付けがきらいです。
さあ、「自分で出したものを片付けてね」と言っても、聞こえないふりをして
遊んでいます。
その態度そのものが、「いったん、拒否して」という態度なのですが、
そこで、少しすれば「受け入れるだろう」と捉えつつ、
指示は出しつつも、こちらの要求する態度を★くんの呼吸に合わせていって、
ちょっと気持ちが切り替わるような声かけをして、
外側から、そっと包み込んでこちらが望んでいる活動の流れに乗せるようにしていくと
ちゃんと最初の指示に従って片付けをしはじめるようになってきました。
「えっ? 外側から、そっと包み込んでこちらが望んでいる活動の流れに
乗せるようにしていくってどういうこと?」と感じた方もいらっしゃいますよね。
★くんは、いったんひとつの考えにこだわりだすと、
なかなか頭を切り替えることができないところがあります。
先日も、こんなことがあったそうです。
★くんのお父さんが、★くんを幼稚園に送っていく途中、
ちょうど駅の階段を下りかけたところで、突然、「幼稚園、行かない」と
言い始めたのだとか。どんな理由があるのかはわからないけれど、
★くんが「行かない」と構えた物言いになるときは、
無理強いしたり、説得したり、なだめたりすると、火に油を注ぐようなもので、
かえって頑なに「行かない」と言い張るようになります。
そこでお父さんは、これまでもだいたい20分もあれば、興奮状態が鎮まってきて、
気持ちを切り替えることができていた……と考えて、
★くんのイライラした表情が少しなごむを待って、
「ふみきりを見に行こうか?」と誘いました。
★くんは、ふみきりが上がったり下がったりするところと、
電車の往来を眺めるのが大好きなのです。
その誘いに素直に従った★くんは、ふみきりを見ているうちに優しい表情に
なっていきました。
お父さんが、「ふみきりを見たら、幼稚園に行こう」と誘うと、
★くんは納得した様子で園に向かうことができたそうです。
大人の誘いというより、当然の日々の行為である幼稚園に向かうということに、
「いったん、拒否する」をしてみた★くんが、「幼稚園に行く」という行為を
受け入れて、再び幼稚園に向い出したという出来事。
このエピソードからは、終始、無声映画のような静けさが伝わってきます。
いったんは拒否してみたものの、
★くんの中には幼稚園に行きたい思いや、行ってあれもこれも楽しかったという
記憶があって、お父さんもそれがわかっていて、
★くんの気持ちが切り替わるのを信頼して待っています。
すると、★くんの心は静けさの中で、
自分に求められていることを受容する方向に向かっていったのです。

前回の記事のお片付けでは、「★くん、自分で出したものを片付けてね」と言っても、
「ほら、このおもちゃをこの箱に入れて」と言っても、
「イージーチター(楽器)を戸棚にしまってきてね」と言っても
聞く耳持たなかった★くん。
けれども、知らんふりしてこちらに背を向けている態度で、
「いったん、拒否して」いるのを、そっとしておいて、それでいて無視したり、
あきらめるのではなく、
★くんの周囲の物が、黙って静かに、少しずつ片付けられていき、
(少し、オーバーに★くんに見せるように片付けています)
★くんの目にも自分に期待されていることが身体でわかるような雰囲気を作りました。
ひとつひとつの物がかっちりと元の場所に収まっていく様子に
惹きつけられていた★くんは、私が楽しそうだけど小さなつぶやくような口調で
「こうして、こうして入れるのよ」とおもちゃをひとつひとつ入れながら言うと、
決心したようにイージーチターを手にすると、戸棚に片付けに行きました。



★くんが比較的、短い時間で、「片付けはいやだ」という気持ちを克服して、
私の指示に従いだしたのは、
この日私が、「手動のえんぴつけずりを使ってみたい」
「えんぴつけずりのけずりかすがどうやって落ちるのか興味がある」
「ベイブレードを自分で回したい」「レストランのメニューを読み取る機械が作りたい」
という★くんの思いが思った通りの形で実現するように、
ゆっくり付き合っていたからでもあります。
そのように自分の気持ちを十二分に受け止めてもらっていると、
シングルフォーカスに陥って頑なになっていても、
自分の力でそれを乗り越えようとする意志がみえてきます。
期待されていることをわかりやすく目に見える形で提示してもらって、
後は静かに待っていてもらうか、少し落ち着いて、別の切り口から声をかけてもらうと、
自分から「する!」という決意を固めるようです。

帰り際、★くんは、ヘリコプターの羽根の部分を回しながら、
「奈緒美先生、ヘリコプターが行くよ。奈緒美先生のところに来たよ」と言いながら、
私の近くにあった箱の上に着陸させました。
この言葉は、★くんなりの私への親愛の情の表現のようです。
「はい、バナナと牛丼を届けてくれたんですか?ありがとう」と言うと、
「待っててください。また届けます」と言って、ヘリコプターを飛び立たせると、
今度は2台で戻ってきて、「はい、バナナ。はい、牛丼」とニコニコしながら
何かを差し出す真似をします。
★くんは、こうしたおもちゃを介して会話を継続させていくのが
うれしくてたまらないようでした。
★くんは、虹色教室で工作をするようになってから、
物のしくみについて説明したり、うまくいかない原因について、ていねいに観察しながら
解説したり、どんなことがしてみたいのか順序立てて表現することなどは
とても上手になっていました。
ひとりで一方的にしゃべるのなら、4歳の子とは思えないほど
しっかりした物言いをするようになっていたのです。
しかし、自然な会話のキャッチボールはかなり苦手で、
途中で会話が途切れてしまうことがほとんどでした。
が、今回は、ごっこ遊びを通して、会話のキャッチボールを自分から望んでくる
★くんの姿があって、とてもうれしく感じました。