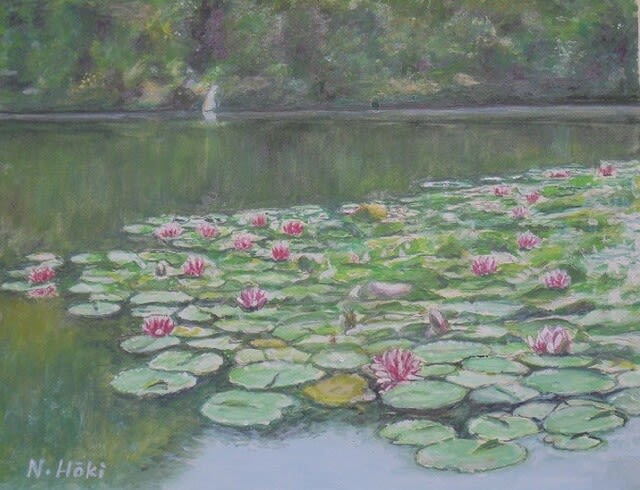賤ヶ岳の見える酒蔵(滋賀県北部) F6 水彩
霜柱
掘り出して児の掌へ霜柱 惟之
年の瀬の大混雑や二寧坂
どくろ巻く蛇は黄金や児の賀状
初暦表紙めくれば句友の名
元旦やお節に集ふ季語あまた
誌上句会 兼題「梅」
特選
めでたさや源平咲きの梅香る 正道
撫牛の目は赤赤と梅真白 惟之
熊野灘一望にして梅の丘 靖子
梅東風や坂をジグザグ杖の父 歌蓮
秀逸
梅真白巫女の立ち居の清しかな 三枝子
梅咲くや偕老集ふレストラン 珠子
晩節の言の葉おもし梅白し 畔
坂道を靴音響く梅月夜 鈴子
梅が香や花街奥の天満宮 藤子
飛び交へる鳥のあまたや梅満開 紀久子
めぐり来し友の忌日や梅白し 利里子
塀にゐる猫もあくびや梅ふふむ 博光
梅が香や菅公の歌口ずさみ 安恵
入選
梅の香を分け合ふけふのふたりかな 謙治
道真を祀りし神社梅開く 博女
咲き継ぎし妣の手植ゑの梅真白 洋子
探梅や話上手の後に就き まこと
梅の花主人の居ない車椅子 光央
あれ梅と妻の呟きローカル線 幹雄
みほとけの近江の里に梅日和 静風
梅見山中腹ほどに宴開く 秀子
寂しさに故人会ひたし梅の香 悦子
落梅も飢ゑの足しなる昭和あり 稔
堀越のしだれ梅待つ散歩道 敏子
梅が香に命の風の沁み渡る 三郎
梅の寺坊ん様直ぐに庭仕事 啓子
梅園の名札は長く香の中に 洋子
平九朗天馬で駆けて梅手折り 秀穂
梅日和十年来の友と合ふ ふみ女
ほつほつと梅の蕾のほころびて 信義
福島へ嫁ぎ十年梅便り 泰山
献梅の紅のほころぶ天満宮 美代子
梅便り今年も綴る日記帳 孝子
体操と梅見が朝の仕事かな 捨弘
やまびこ(三月号作品から)感銘・共鳴ー私の好きな一句
ちゃんちゃんこ重き昭和を生き抜いて 爽見
ニコライの鐘や攻黄落舞ふ街に 勝彦
シャツ畳む小春の匂ひ包み込み 安恵
ほんたうに卒寿となりぬ神の留守 圧知
栗むいてむいて素直になる心 千代
冬の日や稚の目ときに如来の目 清次
波音のざつぱざつぱと冬来る うみ
俳誌嵯峨野 五月号(通巻第646号)より