施餓鬼会(せがきえ)、通称、お施餓鬼(※1)とは何かについて考えたいと思います。
お施餓鬼は、日本の仏教宗派を超えておおよその寺院で行われている、年に一度の大行事です(一度にこだわらないで年間通して随時行う場合もある)。
また、古来、お盆(盂蘭盆会<うらぼんえ>)の時期に行われていたので、お盆と混同されがちですが、別の行事になります。
おそらく、由来のエピソードが少なからず似通っているために余計に混同しがちになるのでしょう。
ここで整理したいと思います。
まず、お盆は、お釈迦さまの十大弟子の一人、神通第一の「目連尊者」のお母様が餓鬼道に落ちているのを救うために行った、僧侶への供養がはじまりとされています。
目連尊者が餓鬼道に落ちている亡き母を見て、お釈迦様にどうすれば母を救えるか相談をしたところ、
「目連よ、そなたの母を救うために、七月十五日、僧たちが三ヶ月の安居を終えて遊行に出掛ける日、僧たちに供養しなさい。供養の功徳によって救われるはずだ・・・・」と教えられました。
これが、そもそもお盆の供養の由来とされています。
退屈ですか・・・
眠らないでくださいね。
さらにお施餓鬼の由来を続けます。
やはりお釈迦様の十大弟子の一人、多聞第一の阿難尊者のもとに、ある夜、餓鬼がやってきます。
その餓鬼に、お前はあと3日後に死んで、私と同じような姿になると告げられたため、お釈迦さまに相談されました。
お釈迦様は阿難尊者に陀羅尼(呪文)を授けられました。
彼がその陀羅尼を唱えたところ、一器の食物が無量の飲食に増やされて無数の餓鬼に施されました。これによって阿難尊者は事なきを得たとされます。これが施餓鬼会の由来です。
ふたつの行事の由来を整理しましょう。
・お盆=目連尊者の母を餓鬼道から救うために七月十五日に行われた供養。
・施餓鬼=阿難尊者を餓鬼道行きから救うために行われた法要。
そして、これらのエピソードが、日本古来の先祖供養信仰と結びついて、お盆、お施餓鬼ともに日本の仏教文化として定着したと言えましょう。
さて、ここで問題になるのは、以上のような、仏教説話的なエピソードを聴いて、私たち現代人がどこまで共感することができるのかという点だと私は考えます。
こうした仏教の六道輪廻に代表される神話的世界観が、現代においては方便として機能しづらくなっている現状がある。
それは科学的合理主義や物質還元主義にもよりましょう。
打ち明ければ、すでに私自身そうした素朴な神話的世界観を丸呑みに信じることはできませんし、またそれを信じ込むよう強要することもあまり意味のないことだと思っています。
こうした世界観が、前近代まで(幕末から明治頃まで)の人々に素朴に信じられていた頃は、方便として人々が安心を得るのに有効に機能していたことでしょう。
しかし、現代、刀の山とか、釜茹で地獄、閻魔様、三途の川などと言われても、なかなかリアルにイメージできなくなってしまった以上、仏教行事を新たに捉えなおすことが求められているのではないでしょうか。
もちろん、古来の説話はそれはそれとして大事にしなければいけませんが。
仏教は、いつの時代、またどのような地域にあっても、時代の価値観、社会環境、風土に応じて、柔軟に姿を変えて、苦悩する人々を導いてきました。
お釈迦さまからして、その人がおかれている状況に応じて、教えを融通無碍に変えながら説いて、悩める人々を救っていたのです。
これを仏教の言葉で、「対機説法、応病与薬(たいきせっぽう、おうびょうよやく)」と言います。
ですから、言葉で表されたものが表面的に姿を変えて説かれても、仏教の本質を見失わない限りは、なんら問題がないと言えるのです。
では次に、仏教の方便としての神話的世界観はひとまず置いて、現代の私たちが共有しやすく心の安心につながりやすい世界観は何か。
また、お盆、お施餓鬼という行事を古来の説話を踏まえつつ、現代的にどのように捉え直せばよいのか考えて行こうと思います。
(次回に続く)
お施餓鬼は、日本の仏教宗派を超えておおよその寺院で行われている、年に一度の大行事です(一度にこだわらないで年間通して随時行う場合もある)。
また、古来、お盆(盂蘭盆会<うらぼんえ>)の時期に行われていたので、お盆と混同されがちですが、別の行事になります。
おそらく、由来のエピソードが少なからず似通っているために余計に混同しがちになるのでしょう。
ここで整理したいと思います。
まず、お盆は、お釈迦さまの十大弟子の一人、神通第一の「目連尊者」のお母様が餓鬼道に落ちているのを救うために行った、僧侶への供養がはじまりとされています。
目連尊者が餓鬼道に落ちている亡き母を見て、お釈迦様にどうすれば母を救えるか相談をしたところ、
「目連よ、そなたの母を救うために、七月十五日、僧たちが三ヶ月の安居を終えて遊行に出掛ける日、僧たちに供養しなさい。供養の功徳によって救われるはずだ・・・・」と教えられました。
これが、そもそもお盆の供養の由来とされています。
退屈ですか・・・
眠らないでくださいね。
さらにお施餓鬼の由来を続けます。
やはりお釈迦様の十大弟子の一人、多聞第一の阿難尊者のもとに、ある夜、餓鬼がやってきます。
その餓鬼に、お前はあと3日後に死んで、私と同じような姿になると告げられたため、お釈迦さまに相談されました。
お釈迦様は阿難尊者に陀羅尼(呪文)を授けられました。
彼がその陀羅尼を唱えたところ、一器の食物が無量の飲食に増やされて無数の餓鬼に施されました。これによって阿難尊者は事なきを得たとされます。これが施餓鬼会の由来です。
ふたつの行事の由来を整理しましょう。
・お盆=目連尊者の母を餓鬼道から救うために七月十五日に行われた供養。
・施餓鬼=阿難尊者を餓鬼道行きから救うために行われた法要。
そして、これらのエピソードが、日本古来の先祖供養信仰と結びついて、お盆、お施餓鬼ともに日本の仏教文化として定着したと言えましょう。
さて、ここで問題になるのは、以上のような、仏教説話的なエピソードを聴いて、私たち現代人がどこまで共感することができるのかという点だと私は考えます。
こうした仏教の六道輪廻に代表される神話的世界観が、現代においては方便として機能しづらくなっている現状がある。
それは科学的合理主義や物質還元主義にもよりましょう。
打ち明ければ、すでに私自身そうした素朴な神話的世界観を丸呑みに信じることはできませんし、またそれを信じ込むよう強要することもあまり意味のないことだと思っています。
こうした世界観が、前近代まで(幕末から明治頃まで)の人々に素朴に信じられていた頃は、方便として人々が安心を得るのに有効に機能していたことでしょう。
しかし、現代、刀の山とか、釜茹で地獄、閻魔様、三途の川などと言われても、なかなかリアルにイメージできなくなってしまった以上、仏教行事を新たに捉えなおすことが求められているのではないでしょうか。
もちろん、古来の説話はそれはそれとして大事にしなければいけませんが。
仏教は、いつの時代、またどのような地域にあっても、時代の価値観、社会環境、風土に応じて、柔軟に姿を変えて、苦悩する人々を導いてきました。
お釈迦さまからして、その人がおかれている状況に応じて、教えを融通無碍に変えながら説いて、悩める人々を救っていたのです。
これを仏教の言葉で、「対機説法、応病与薬(たいきせっぽう、おうびょうよやく)」と言います。
ですから、言葉で表されたものが表面的に姿を変えて説かれても、仏教の本質を見失わない限りは、なんら問題がないと言えるのです。
では次に、仏教の方便としての神話的世界観はひとまず置いて、現代の私たちが共有しやすく心の安心につながりやすい世界観は何か。
また、お盆、お施餓鬼という行事を古来の説話を踏まえつつ、現代的にどのように捉え直せばよいのか考えて行こうと思います。
(次回に続く)










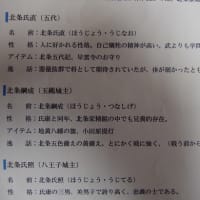
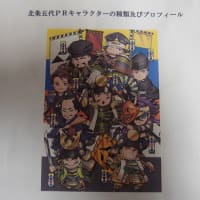




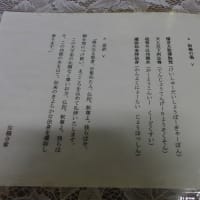



まぁ、道草もあったほうが彩り豊かになりますゆえ~
施餓鬼会のお話は興味深く拝見しました。
イエスが5つのパンと2匹の魚で5000人(聖書の数字は「たくさん」を表します)を養ったお話、りょうさんはご存知ですよね?
> お盆、お施餓鬼という行事を現代的にどのように捉え直せばよいのか
8月お盆に限定されますが、(企業はこの時期にお休みになるからいいのかな?)カトリック教会は聖母の祝いの日なのですが、教会では終戦の日でもあるので、この祝いに併せて死者のための祈りを行います。
死者の日は11月にあるのですが、お盆休みで地元に戻る人が多いことも考慮しています。
お盆は、ご供養にふさわしい時期なのですね。
ミクシィって何気に面白いですよね♪
ところで、
イエスが5つのパンと2匹の魚で5000人
の話は知りませんでした。
acquaさんには申し訳ないのですが、こういう奇跡の話については、そのまま丸呑みに受け止めるか、象徴的な話として捉えればいいのどうか・・・
いろいろと思うところがあるので判断を留保しています。
ただし、イエスの癒しの奇跡はほぼ全面的に信じていますが。。。
お釈迦様にも、やはり少なからず奇跡話があるのですが同様です。
お盆は日本全体が独特な空気に包まれるような気がしませんか。
この世とあの世との境界が薄くなっているような感覚。
一年のうちで一番、故人が私たちとともにあるという思いを強くする時期ですよね。
カトリック教会でも日本の事情を考慮しているのですね。尊いことだと思います。
さて、ご意見ごもっともと思います。
りょうさんが触れてきた福音書の解釈がどういうものだったかわかりませんが、少なくてもカトリックでは、聖書そのものの解釈にはガイドラインを設けています。でも、生活のどの場面で生かしていくか、ということは任されている。
ちょっとわかりにくいと思いますが、聖書をそのまま受け止めると奇跡物語で終わりますけれど、そこから何を受け取るかということですね。
だから、教会で「イエスは神の子」という教義があって、これを信じないと受洗できない、ということではなく、教えとして受け容れるかどうかが大事ということになります。
個人的な見解に留めますが、28年の信仰生活の中で言えるのは、聖書はとても自由な生きた書物であるということ。この奇跡のお話にしても、イエスが神なら物理的な奇跡としてこういうこともあるだろう、と捉えることもできますし、象徴的な意味合いでは分かち合いの素晴らしさ、豊かさであると解釈もできます。どちらもカトリック教会では「あり」です。
また、どちらかに決めなければならないものではなく、行間から感じ取るものが変ったとしても、それはそのときに希望が見出せるものであれば、そこに神のメッセージを受け取ることになるのだとわたしは思っています。
みんながみんな、同じ意識ではないことも申し沿えて、と(笑)
聖書が生き物のようだというお話は、とくに清美さんの信仰生活から生まれた実感なのでしょうね。
素晴らしいことと思います。
聖書はそのときそのとき、自分にいろんなメッセージを問いかけてくる。
自分の受け止め方も、時に応じて変化する。
それが自然なことだと思いますし、また、それこそ本当に神のメッセージを受け取るということなのでしょう。
ひとつの固定化した解釈を信じ込まなければならないというと、途端に教条主義的なってしまいますし、逆に神からも遠ざかってしまう気もします。
>みんながみんな、同じ意識ではないことも申し沿えて、と(笑)
そうなんですよね。そこが残念です(汗)
なぜならば、故人の生命活動のために費消された食べ物と化した多くの生物たちをも、成仏していただきたいからです。
もちろん、人間以外は成仏できませんから、
それらのイキモノはの霊は、故人の成仏のジャマをします。
だから、ジャマしないでね、と慰霊をするわけですね。
それが施餓鬼。
私は、学生時代に、肉をたべることができなくなった。
「人間が他の動物を殺して食べても罰せられないのに、
他の動物が人間を殺して食べたら、殺されるのは、なぜ?」という疑問に取り付かれたからです。
でも、この疑問の答えは、仏教説話の中にあった。
それ以後は、喜んで食しますが、でも、・・・
自分が食される側に陥ったときは、
嫌だけれども、受け容れよう。
もちろん、嫌だよ、嫌だけどね、でも、人間だって状況が変われば、他の動物の蛋白源に過ぎないってことを仏教は言っている。
ここが「バイブル」とは違うところ。
仏教を真正面から受け止めれば、自然保護をうたう今の環境問題は、一神教的な管理主義的な自然保護に見えてしまうのだが。
もちろん、これは「偏見」。
初七日に、施餓鬼・・・目からウロコでした・・・。
仰っていることにも同感です。
施餓鬼とは、懺悔滅罪にも結びつくわけですね・・・
これは早速、導入を検討してみます。
肉食については、やはりいろいろ考えさせられますね。
私も、もちろん肉は好きなのですが、日本人はもともと肉を食べなくても健康に生活していたわけですし。
できれば、われわれと同じグループを食べることは生理的に避けたい気もする。。。
もっともこれも分別知、差別なのかもしれませんね・・・。
老師の仰ることもよくわかるのですが、まだ自分の中でしっかりと納得するには時間がかかりそうです・・・。
ちなみに私も永平寺時代を除いて、自主的に学生時代に肉を食べなかった時期がありました。