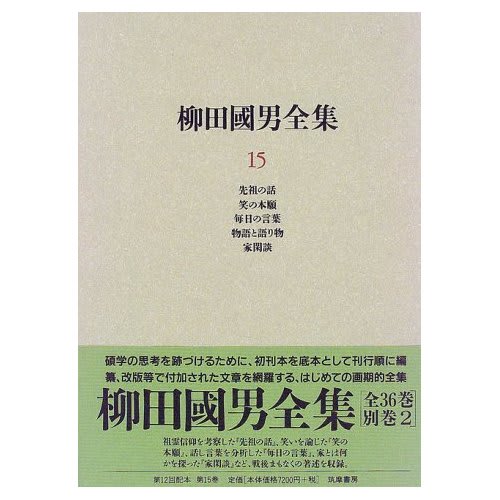本来の神なり仏なりが、別の仏や神に姿を変えているということを本地垂迹という。
仏教が伝来した時の日本では、仏を「他国神」とか「蕃神」(あたしくにのかみ)と呼んでいたと、末木氏の本には紹介されているが、仏を他所からきた神として、積極的にそうした「客人神」(まれびとがみ)として、日本に幸せをもたらすものと理解する崇仏派の蘇我氏と、厄災をもたらすものと嫌悪した排仏派の物部氏が争ったのであろう。
この頃は、神が仏の姿をとっているという意味での本地垂迹であった。
仏教側から見れば、これと反対のことが本地垂迹である。仏が日本では神の姿をとっているというのである。本が神から仏に移行することは立場の差であって当然の事情ではある。しかし、本地が人間になると宗教は革命的な変化を遂げたことになる。
熊野伝説は人が本地の典型例である。登場人物は4人いる。そのすべてが熊野では仏になった。登場人物はすべてインド人である。
4人の1人目は、善財王(ぜんざいおう)という大王、2人目が大王の千人目の后で「五衰殿」(ごすいでん)に住んでいた「せんかう女御(にょうご)」、3人目が女御が生んだ王子を助け出した「地けん聖(ひじり)」、最後の4人目が王子である。熊野権現(ごんげん)の証誠殿(しょうじょうでん)の阿弥陀如来は大王である。
両所権現は観音であり女御のことである。
那智権現は薬師如来で「地けん聖」である。若王子(にゃくおうじ)は十一面観音で王子である。インドから逃れてきた大王は殺された女御の首を本尊として仏道に励んだとされている。
物語はこうである。
大国を治めていた大王は999人の后をもったが子供ができなかった。そこで1000人目の后が懐妊した。嫉妬した999人の后たちは、1000人目の女御を山中の岩屋に幽閉し、武士たちに命じて首をはねさせた。首をはねられるときに、女御から王子が生まれた。首を切られて死んだ女御は乳を出し続けた。王子は虎や狼に守られて成長していた。この王子を「地けん聖」が見つけ、大王の元に連れてきた。ことの次第を知った大王は世をはかなみ、王子を連れ、女御の首を抱いて、飛ぶ車にのって日本の熊野にやってきた。
首を切られても乳を出し続けて子供を育てた偉大な母性、后の苦難を知って仏性に目覚めた大王、彼らが仏の力を借りて神となる。人が神になったのである。確かに、後の熊野三山の本宮という「熊野坐神社」にいる神が阿弥陀、新宮という「熊野速玉神社」にいる神が薬師、那智という「熊野夫須美神社」にいる神が観音を本地とする。しかし、そもそもがインドの人間が日本の神になったというのが原型でである。
こうした物語は中世の日本でよく語られていた。これを「本地物」(ほんじもの)という。森鴎外の『山椒大夫』もその一つである。
末木氏によれば、本地垂迹は大転換を遂げた。
まず、インドの王様のような大権力者が日本で神になった。つぎに菅原道真のような怨霊が神になった。そして、「さんせう太夫」のような凡夫が神(ここでは仏)になった。これは、安寿と厨子王を助ける金焼(かねやき)地蔵が、じつは実父を本地とするものであるという垂迹である。このような転換を経ると、人を本地とする神は、厄災をもたらすものではなく、恩恵をもたらすものとなった。神も仏も人間も同一のレベルに並べるという、世界で稀な精神風土が日本に生み出されたのである。日本の神道の隆盛はこうした宗教界における大転換を契機としたのではないだろうか。
日本の神社の多くは寺院(神宮寺)を併設していた。
霊亀(715~717年)の頃、藤原武智麻呂(ふじわらのむちまろ)が神託によって気比(けひ)神宮に神宮寺を建てたという『藤原家伝』がある。神が藤原武智麻呂の夢枕に現れ、自分は仏教に帰依したいので、この神社に寺を建ててくれと懇願したという。
養老年中(717~724年)には若狭比古(ひこ)神宮寺が建てられている。これも、神が仏法に帰依したいのに寺がないばかりにその恨みで厄災を与えたというので、寺を建てたという。
つまり、この段階では、神は迷える存在であり、仏の救済を必要とするとされていた。日本の神々は外来の仏の膝下に入っていた。
こうした神道にとっての屈辱を跳ね返すには、民衆に愛され、民衆に世俗的利益をもたらすように神の役割をより具体化させなければならなかったのである。その際、人を本地とするようになった本地垂迹の大転換は、神道にとって最大のチャンスであっただろう。
仏教が伝来した時の日本では、仏を「他国神」とか「蕃神」(あたしくにのかみ)と呼んでいたと、末木氏の本には紹介されているが、仏を他所からきた神として、積極的にそうした「客人神」(まれびとがみ)として、日本に幸せをもたらすものと理解する崇仏派の蘇我氏と、厄災をもたらすものと嫌悪した排仏派の物部氏が争ったのであろう。
この頃は、神が仏の姿をとっているという意味での本地垂迹であった。
仏教側から見れば、これと反対のことが本地垂迹である。仏が日本では神の姿をとっているというのである。本が神から仏に移行することは立場の差であって当然の事情ではある。しかし、本地が人間になると宗教は革命的な変化を遂げたことになる。
熊野伝説は人が本地の典型例である。登場人物は4人いる。そのすべてが熊野では仏になった。登場人物はすべてインド人である。
4人の1人目は、善財王(ぜんざいおう)という大王、2人目が大王の千人目の后で「五衰殿」(ごすいでん)に住んでいた「せんかう女御(にょうご)」、3人目が女御が生んだ王子を助け出した「地けん聖(ひじり)」、最後の4人目が王子である。熊野権現(ごんげん)の証誠殿(しょうじょうでん)の阿弥陀如来は大王である。
両所権現は観音であり女御のことである。
那智権現は薬師如来で「地けん聖」である。若王子(にゃくおうじ)は十一面観音で王子である。インドから逃れてきた大王は殺された女御の首を本尊として仏道に励んだとされている。
物語はこうである。
大国を治めていた大王は999人の后をもったが子供ができなかった。そこで1000人目の后が懐妊した。嫉妬した999人の后たちは、1000人目の女御を山中の岩屋に幽閉し、武士たちに命じて首をはねさせた。首をはねられるときに、女御から王子が生まれた。首を切られて死んだ女御は乳を出し続けた。王子は虎や狼に守られて成長していた。この王子を「地けん聖」が見つけ、大王の元に連れてきた。ことの次第を知った大王は世をはかなみ、王子を連れ、女御の首を抱いて、飛ぶ車にのって日本の熊野にやってきた。
首を切られても乳を出し続けて子供を育てた偉大な母性、后の苦難を知って仏性に目覚めた大王、彼らが仏の力を借りて神となる。人が神になったのである。確かに、後の熊野三山の本宮という「熊野坐神社」にいる神が阿弥陀、新宮という「熊野速玉神社」にいる神が薬師、那智という「熊野夫須美神社」にいる神が観音を本地とする。しかし、そもそもがインドの人間が日本の神になったというのが原型でである。
こうした物語は中世の日本でよく語られていた。これを「本地物」(ほんじもの)という。森鴎外の『山椒大夫』もその一つである。
末木氏によれば、本地垂迹は大転換を遂げた。
まず、インドの王様のような大権力者が日本で神になった。つぎに菅原道真のような怨霊が神になった。そして、「さんせう太夫」のような凡夫が神(ここでは仏)になった。これは、安寿と厨子王を助ける金焼(かねやき)地蔵が、じつは実父を本地とするものであるという垂迹である。このような転換を経ると、人を本地とする神は、厄災をもたらすものではなく、恩恵をもたらすものとなった。神も仏も人間も同一のレベルに並べるという、世界で稀な精神風土が日本に生み出されたのである。日本の神道の隆盛はこうした宗教界における大転換を契機としたのではないだろうか。
日本の神社の多くは寺院(神宮寺)を併設していた。
霊亀(715~717年)の頃、藤原武智麻呂(ふじわらのむちまろ)が神託によって気比(けひ)神宮に神宮寺を建てたという『藤原家伝』がある。神が藤原武智麻呂の夢枕に現れ、自分は仏教に帰依したいので、この神社に寺を建ててくれと懇願したという。
養老年中(717~724年)には若狭比古(ひこ)神宮寺が建てられている。これも、神が仏法に帰依したいのに寺がないばかりにその恨みで厄災を与えたというので、寺を建てたという。
つまり、この段階では、神は迷える存在であり、仏の救済を必要とするとされていた。日本の神々は外来の仏の膝下に入っていた。
こうした神道にとっての屈辱を跳ね返すには、民衆に愛され、民衆に世俗的利益をもたらすように神の役割をより具体化させなければならなかったのである。その際、人を本地とするようになった本地垂迹の大転換は、神道にとって最大のチャンスであっただろう。