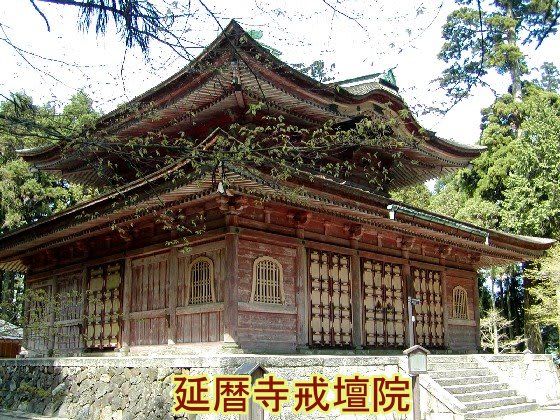
「山門」とは、ここでは、天台宗延暦寺を指す。前回、荘園の請負を寺院が地方豪族から預かったと表現したが、これは、間違いであることに気づいた。申し訳ない。事実は逆である。寺院が武家に管理を預けることを言う。越前・若狭においては、平氏が支配権を確立した後、こうした荘園が激増した。それは、山門(延暦寺)系の所領が中心となっている。例えば、若狭の大田文で「山門沙汰」「園城寺沙汰」などと分類されている14か所、面積にして2991町152歩、この地域の荘園全体の面積に占める比率で21.4%にも及ぶ大荘園が、そうした請負の具体例である。この荘園は、平経盛家の国守が、延暦寺・園城寺などに対して請け負っていた所領らしい。
後白河院は、厖大な家領荘園を統轄していた。平家は、後白河院と政治連合を形成した上で、延暦寺勢力と同盟関係を維持することを戦略としていた。越前・若狭において天皇家や山門が荘園を立てようとしたとき、それらを平氏が容認し、後押ししていた。
牛原荘は、白河院の中宮賢子のために京都醍醐寺内に建てられた円光院の荘園である(『醍醐雑事記』巻十三)。一度、この荘園は縮小されたが、それを元の大きさにまで回復させたのは、国守の平忠盛であった。こうしたことに見られるように、院政時代には、天皇家と平氏は不可分の関係にあった。
山門領については、日吉神人という日吉神社に抱えられた商人たちの活躍が目につく。保延年間(1130年代)大津の日吉神人たちは、日吉社が収納した神物である上分米(年貢米)を預かり、諸国に高利を取って貸し付けていた。貸付先は、公卿、諸国の受領、中央官衙の官人層、諸国の武士、荘園の住人、田堵(有力農民)層、京都の四条町の商人に至る広い範囲に及ぶ(壬生家文書)。借米を返済できなければ、荘園主の場合、抵当に取られていた田地を、神人を介して本所である山門の所領や荘園化に組み込まれる。越前・若狭の山門領は、そのようにして大きくなって行った。
大津に本拠を置く日吉神人のほか、北陸道諸国の日吉神人もいた。彼らは海辺の津・泊・浦・浜に分布し、日本海ならびに琵琶湖・北陸間の交通路を担う廻船人たちであった。こうした船乗り兼商人たちは、遠隔地所領支配としての荘園制が円滑に機能するためには、不可欠の存在であった。私が、この日記で、各地に点在する日吉神社は、延暦寺に参拝する人々の安全を守る神であると言った。各地に点在していたのは、それだけではない。要するに、こうした商人たちが、貸金取り立て任務を果たす出張所であった可能性が強い。
そして、彼ら神人たちが、取り立てたものを本所の延暦寺に運び、日吉神社は、荷物の倉庫の役割を果たしていたと想われる。これは想われるというよりも断定したい。日吉神社には、きまって、堅牢な倉が敷設されている。神人たちが延暦寺に運ぶ荷物を保管し、旅の宿舎として使ったのが日吉神社である。だからこそ、日吉神社は各地に点在させられなければならなかったし、そうした日吉神社を線で結んで行けば、比叡山に到着するのである。そういうことだったのかと、私は独り合点している。ここでも、宗教組織と金の収奪組織の見事な絡み合いが見受けられる。
若狭では平家が山門に請け負う荘園は多かったが、平安時代になって改めて増やされた直轄荘園はそれほど多くはなかったと言われている。越前でも、足羽郡足羽御厨、吉田郡藤島荘、丹生郡大蔵荘が知られているに過ぎない。多年にわたり知行国として確保している以上、改めて荘園を立てる必要がなかったからかもしれない。

足羽御厨は、承安元年(1171年)に建てられた(立荘)(「伊勢大神宮神領注文」)、源平争乱後、平氏が滅ぼされてからは、平家没官領となり、他の19か所の荘園とともに一条能保の妻(源頼朝の妹)に与えられた(『吾妻鏡』建久三年十二月十四日条)。
藤島荘は、平家没官領として頼朝が支配(領知)していたが、白山権現の神膳に充てるため大野郡平泉寺に寄進された。本家に延暦寺を戴くこの荘園は、平氏段階ではまだ多くの未開地を抱えていたらしい(「門葉記」二など)。
大蔵荘も、元、平清盛領で、永万年間(1165~66年)の頃、摂津国山田荘(神戸市)との交換で京都最勝寺に寄進され、調庸租税以下臨時雑事が免除され不輸の地となった(東大寺文書)。山田荘とは、酒米として有名な山田錦の産地であり、日本一面積の広い村であり、箱木千年屋や農村舞台がいまでも残っている豊かな田園地帯である。
ちなみに、越前の酒はそれこそ絶妙の味であるが、残念ながら、使用されている米は、ご当地自慢の「こしひかり」(越の光、つまり、越前の希望の星)ではなく、神戸の山田錦を使うことが多い。たんなる偶然なのか、平氏の本家が神戸の福原にあったことの名残なのか、調べて見ようと思う(清盛のときに山田錦があったとは思われないが、その祖先はあったはずである)。

若狭では、遠敷郡玉置郷があった。玉置郷は、元暦元年(1184年)、平家没官領として頼朝より園城寺に寄進されている(『吾妻鏡』同年十二月一日条)。

加賀・越前・美濃三方の白山馬場(登拝口)のうち、越前馬場の中心は、前回の日記で説明したように、白山中宮の大野郡平泉寺である。鳥羽院政期に平泉寺を支配していたのは、園城寺の僧である覚宗であった。覚宗は、『寺門伝記補録』十三に「北越白山検校」と記載されている。彼は、加賀白山宮も合わせ統轄していた可能性がある。つまり、一向一揆が主要な敵としたのは、戦国大名だけではなかった。荘園領主であった延暦寺系の寺院も最大の攻撃目標だったのである。事実、北陸の天台宗系寺院のことごとくが一向一揆によって焼き払われた。
覚宗は、鳥羽院および待賢門院の熊野詣の先達の功で律師に補され、京都の法勝寺(炎上して今はない)・最勝寺・尊勝寺の別当職を務めたといわれるなど、院と密接なつながりのある人物である。彼の在職によって当時、平泉寺が、園城寺の末寺であったようにも見えるが、実際には、彼個人が上皇の命を受け手、平泉寺を支配していたに過ぎない。
ところが、久安3年(1147年)、延暦寺の僧綱・已講らが院の御所に群参し、園城寺長吏・覚宗の平泉寺社務執行を停止して平泉寺を山門(延暦寺)の末寺にするよう訴える事件が起こる。その背景には、覚宗の独裁的な統制への住僧らの反発があったとされている(『本朝世紀』久安三年四月十三日条)。院は、覚宗没後に末寺化の宣下を行なうことを約束し(『台記』同年六月二十三日条)、仁平2年(1152年)9月の彼の死とともに、平泉寺は延暦寺の末寺に入った。
平泉寺の組織についてはよく分かっていない。しかし、同じく延暦寺末となった加賀白山宮では、内部は寺家と社家からなり、両者を統轄し白山宮全体の運営を図る機関として政所があった。それを構成していたのが惣・院主・大勧進・大先達・修理別当・上座・寺主・都維那・神主・大宮司であった。惣から大先達までが貫主とよばれる。惣は加賀馬場全体の形式上の統轄者で、白山宮のがこれを兼ねた。(惣)・大先達はほぼ世襲化されており、の一族中より延暦寺が補任した。
修理別当から都維那までは寺家の代表者で、彼らは白山宮政所の構成員であるとともに寺家の政所を構成していた。寺家政所は構成員から見ると延暦寺の政所と同一の形態を取っている。平泉寺も同じ内部構成であったのだろう。
重要なことは、この組織形態は、宗教的論理に基づくものではなく、あくまでも荘園を支配し、管理するための純然たる行政組織であったということである。当時の本所・末寺関係は宗派としてのそれではなく、荘園制的な支配関係であった。延暦寺から別当が派遣され、以下を補任し、寺家政所を配下に収めて所定の上納物も収取していたのである。 一向一揆に参加した人たちの憎悪のすさまじさをこの一点に垣間見ることができよう。繰り返し言うが、天台宗系寺院のことごとくが、この越前で焼き払われた。
単純に加賀の一向一揆として、加賀がその本拠であったように言われているが、私にはそうは思われない。荘園制度の苛酷な支配下にあった越前、そして、平氏なき後の延暦寺の強権支配がひどかった分だけ、一揆は、越前を、むしろ、本拠としていたのではなかったのか。一揆衆は、加賀では生き残ったが、越前では完膚無きまで叩きのめされた。この点もきちんと調べておきたい。少なくとも今までの叙述で明らかになったように、一向一揆は、「百姓の国」を作るべく戦国大名と戦ったのではない。既成宗教とも戦った。しかし、これも、最上層部の権力欲の犠牲になった。苦しいから宗教にすがり、そして、採取的には、命を捧げながら、宗教からボロ雑巾のごとく棄てられる貧困な民衆の古今、繰り返される悲劇に胸が塞ぐ。
『福井県史』通史編2 第一章「武家政権の成立と荘園・国衙領・第一節 院政期の越前・若狭」を参照した。
後白河院は、厖大な家領荘園を統轄していた。平家は、後白河院と政治連合を形成した上で、延暦寺勢力と同盟関係を維持することを戦略としていた。越前・若狭において天皇家や山門が荘園を立てようとしたとき、それらを平氏が容認し、後押ししていた。
牛原荘は、白河院の中宮賢子のために京都醍醐寺内に建てられた円光院の荘園である(『醍醐雑事記』巻十三)。一度、この荘園は縮小されたが、それを元の大きさにまで回復させたのは、国守の平忠盛であった。こうしたことに見られるように、院政時代には、天皇家と平氏は不可分の関係にあった。
山門領については、日吉神人という日吉神社に抱えられた商人たちの活躍が目につく。保延年間(1130年代)大津の日吉神人たちは、日吉社が収納した神物である上分米(年貢米)を預かり、諸国に高利を取って貸し付けていた。貸付先は、公卿、諸国の受領、中央官衙の官人層、諸国の武士、荘園の住人、田堵(有力農民)層、京都の四条町の商人に至る広い範囲に及ぶ(壬生家文書)。借米を返済できなければ、荘園主の場合、抵当に取られていた田地を、神人を介して本所である山門の所領や荘園化に組み込まれる。越前・若狭の山門領は、そのようにして大きくなって行った。
大津に本拠を置く日吉神人のほか、北陸道諸国の日吉神人もいた。彼らは海辺の津・泊・浦・浜に分布し、日本海ならびに琵琶湖・北陸間の交通路を担う廻船人たちであった。こうした船乗り兼商人たちは、遠隔地所領支配としての荘園制が円滑に機能するためには、不可欠の存在であった。私が、この日記で、各地に点在する日吉神社は、延暦寺に参拝する人々の安全を守る神であると言った。各地に点在していたのは、それだけではない。要するに、こうした商人たちが、貸金取り立て任務を果たす出張所であった可能性が強い。
そして、彼ら神人たちが、取り立てたものを本所の延暦寺に運び、日吉神社は、荷物の倉庫の役割を果たしていたと想われる。これは想われるというよりも断定したい。日吉神社には、きまって、堅牢な倉が敷設されている。神人たちが延暦寺に運ぶ荷物を保管し、旅の宿舎として使ったのが日吉神社である。だからこそ、日吉神社は各地に点在させられなければならなかったし、そうした日吉神社を線で結んで行けば、比叡山に到着するのである。そういうことだったのかと、私は独り合点している。ここでも、宗教組織と金の収奪組織の見事な絡み合いが見受けられる。
若狭では平家が山門に請け負う荘園は多かったが、平安時代になって改めて増やされた直轄荘園はそれほど多くはなかったと言われている。越前でも、足羽郡足羽御厨、吉田郡藤島荘、丹生郡大蔵荘が知られているに過ぎない。多年にわたり知行国として確保している以上、改めて荘園を立てる必要がなかったからかもしれない。

足羽御厨は、承安元年(1171年)に建てられた(立荘)(「伊勢大神宮神領注文」)、源平争乱後、平氏が滅ぼされてからは、平家没官領となり、他の19か所の荘園とともに一条能保の妻(源頼朝の妹)に与えられた(『吾妻鏡』建久三年十二月十四日条)。
藤島荘は、平家没官領として頼朝が支配(領知)していたが、白山権現の神膳に充てるため大野郡平泉寺に寄進された。本家に延暦寺を戴くこの荘園は、平氏段階ではまだ多くの未開地を抱えていたらしい(「門葉記」二など)。
大蔵荘も、元、平清盛領で、永万年間(1165~66年)の頃、摂津国山田荘(神戸市)との交換で京都最勝寺に寄進され、調庸租税以下臨時雑事が免除され不輸の地となった(東大寺文書)。山田荘とは、酒米として有名な山田錦の産地であり、日本一面積の広い村であり、箱木千年屋や農村舞台がいまでも残っている豊かな田園地帯である。
ちなみに、越前の酒はそれこそ絶妙の味であるが、残念ながら、使用されている米は、ご当地自慢の「こしひかり」(越の光、つまり、越前の希望の星)ではなく、神戸の山田錦を使うことが多い。たんなる偶然なのか、平氏の本家が神戸の福原にあったことの名残なのか、調べて見ようと思う(清盛のときに山田錦があったとは思われないが、その祖先はあったはずである)。

若狭では、遠敷郡玉置郷があった。玉置郷は、元暦元年(1184年)、平家没官領として頼朝より園城寺に寄進されている(『吾妻鏡』同年十二月一日条)。

加賀・越前・美濃三方の白山馬場(登拝口)のうち、越前馬場の中心は、前回の日記で説明したように、白山中宮の大野郡平泉寺である。鳥羽院政期に平泉寺を支配していたのは、園城寺の僧である覚宗であった。覚宗は、『寺門伝記補録』十三に「北越白山検校」と記載されている。彼は、加賀白山宮も合わせ統轄していた可能性がある。つまり、一向一揆が主要な敵としたのは、戦国大名だけではなかった。荘園領主であった延暦寺系の寺院も最大の攻撃目標だったのである。事実、北陸の天台宗系寺院のことごとくが一向一揆によって焼き払われた。
覚宗は、鳥羽院および待賢門院の熊野詣の先達の功で律師に補され、京都の法勝寺(炎上して今はない)・最勝寺・尊勝寺の別当職を務めたといわれるなど、院と密接なつながりのある人物である。彼の在職によって当時、平泉寺が、園城寺の末寺であったようにも見えるが、実際には、彼個人が上皇の命を受け手、平泉寺を支配していたに過ぎない。
ところが、久安3年(1147年)、延暦寺の僧綱・已講らが院の御所に群参し、園城寺長吏・覚宗の平泉寺社務執行を停止して平泉寺を山門(延暦寺)の末寺にするよう訴える事件が起こる。その背景には、覚宗の独裁的な統制への住僧らの反発があったとされている(『本朝世紀』久安三年四月十三日条)。院は、覚宗没後に末寺化の宣下を行なうことを約束し(『台記』同年六月二十三日条)、仁平2年(1152年)9月の彼の死とともに、平泉寺は延暦寺の末寺に入った。
平泉寺の組織についてはよく分かっていない。しかし、同じく延暦寺末となった加賀白山宮では、内部は寺家と社家からなり、両者を統轄し白山宮全体の運営を図る機関として政所があった。それを構成していたのが惣・院主・大勧進・大先達・修理別当・上座・寺主・都維那・神主・大宮司であった。惣から大先達までが貫主とよばれる。惣は加賀馬場全体の形式上の統轄者で、白山宮のがこれを兼ねた。(惣)・大先達はほぼ世襲化されており、の一族中より延暦寺が補任した。
修理別当から都維那までは寺家の代表者で、彼らは白山宮政所の構成員であるとともに寺家の政所を構成していた。寺家政所は構成員から見ると延暦寺の政所と同一の形態を取っている。平泉寺も同じ内部構成であったのだろう。
重要なことは、この組織形態は、宗教的論理に基づくものではなく、あくまでも荘園を支配し、管理するための純然たる行政組織であったということである。当時の本所・末寺関係は宗派としてのそれではなく、荘園制的な支配関係であった。延暦寺から別当が派遣され、以下を補任し、寺家政所を配下に収めて所定の上納物も収取していたのである。 一向一揆に参加した人たちの憎悪のすさまじさをこの一点に垣間見ることができよう。繰り返し言うが、天台宗系寺院のことごとくが、この越前で焼き払われた。
単純に加賀の一向一揆として、加賀がその本拠であったように言われているが、私にはそうは思われない。荘園制度の苛酷な支配下にあった越前、そして、平氏なき後の延暦寺の強権支配がひどかった分だけ、一揆は、越前を、むしろ、本拠としていたのではなかったのか。一揆衆は、加賀では生き残ったが、越前では完膚無きまで叩きのめされた。この点もきちんと調べておきたい。少なくとも今までの叙述で明らかになったように、一向一揆は、「百姓の国」を作るべく戦国大名と戦ったのではない。既成宗教とも戦った。しかし、これも、最上層部の権力欲の犠牲になった。苦しいから宗教にすがり、そして、採取的には、命を捧げながら、宗教からボロ雑巾のごとく棄てられる貧困な民衆の古今、繰り返される悲劇に胸が塞ぐ。
『福井県史』通史編2 第一章「武家政権の成立と荘園・国衙領・第一節 院政期の越前・若狭」を参照した。



















