3月10日、皆さんにお渡しした当日のプログラムノートをアップ、
その下にコメントしてみます。
プログラムノート ―――――――――――――― 河野美砂子
前回までの「モーツァルトに会いたい」シリーズでは、演奏の合間に、その曲の成り立ちやエピソード、あるいは演奏の裏話などをお話していましたが、今回は、谷川俊太郎さんが来てくださいましたので、その朗読やお話をお聞きすることにしたいと思います。曲目に関しては、以下をご覧ください。
シリーズ第3回目の今回は、「モーツァルト・マニアック」と副題を付けましたとおり、演奏されることの少ない作品を中心にプログラムを組みました。
最初に演奏します「前奏曲KV284a」は、以前は1778年にパリで書かれた「カプリチォ」と考えられていましたが、その後、手紙の内容や、自筆譜の紙質の科学的な研究などにより、1777年作曲とされるようになりました。姉のナンネルが、弟のモーツァルト宛の手紙の追伸に「c(ハ長調)からb(変ロ長調)進むプレアンブル(前奏曲)を送ってね。」と書いたものがこの曲だろうと推測されています。
当時の前奏曲には二つの目的がありました。一つは、次の曲への導入。もう一つは、クラヴィア(当時のピアノ)の性能を試す、ということです。鍵盤のタッチの加減、調律の具合、各音域での響きなどを試すのに、こんな曲が弾かれたと想像するだけで楽しいものです。
曲は、アレグレットから始まり、すぐに、小節線のない(拍子がない)パッセージが延々と続きます。めまぐるしくテンポや曲想が変化し、最後は4/4拍子のカプリチォ。曲は唐突に終わります。よし、この楽器の具合がわかったぞ、とでもいう感じでしょうか。
・・・以下コメントです。
この曲はインパクトがけっこう強かったらしく、
・・つまり、いわゆるモーツァルト的ではない、という意味で・・
お客さんの反応が大きかったです。
特に前半、小節線がない(拍子がない)のを延々と弾くっていうのは
練習時に意外に苦労しました。
バロック的な(拍の最初が重くて、その音から渦を巻くようにリズムが生まれる)リズムの感じ方が身につくと問題ないのですが。
モーツァルトって、やっぱバッハなのね。
その下にコメントしてみます。
プログラムノート ―――――――――――――― 河野美砂子
前回までの「モーツァルトに会いたい」シリーズでは、演奏の合間に、その曲の成り立ちやエピソード、あるいは演奏の裏話などをお話していましたが、今回は、谷川俊太郎さんが来てくださいましたので、その朗読やお話をお聞きすることにしたいと思います。曲目に関しては、以下をご覧ください。
シリーズ第3回目の今回は、「モーツァルト・マニアック」と副題を付けましたとおり、演奏されることの少ない作品を中心にプログラムを組みました。
最初に演奏します「前奏曲KV284a」は、以前は1778年にパリで書かれた「カプリチォ」と考えられていましたが、その後、手紙の内容や、自筆譜の紙質の科学的な研究などにより、1777年作曲とされるようになりました。姉のナンネルが、弟のモーツァルト宛の手紙の追伸に「c(ハ長調)からb(変ロ長調)進むプレアンブル(前奏曲)を送ってね。」と書いたものがこの曲だろうと推測されています。
当時の前奏曲には二つの目的がありました。一つは、次の曲への導入。もう一つは、クラヴィア(当時のピアノ)の性能を試す、ということです。鍵盤のタッチの加減、調律の具合、各音域での響きなどを試すのに、こんな曲が弾かれたと想像するだけで楽しいものです。
曲は、アレグレットから始まり、すぐに、小節線のない(拍子がない)パッセージが延々と続きます。めまぐるしくテンポや曲想が変化し、最後は4/4拍子のカプリチォ。曲は唐突に終わります。よし、この楽器の具合がわかったぞ、とでもいう感じでしょうか。
・・・以下コメントです。
この曲はインパクトがけっこう強かったらしく、
・・つまり、いわゆるモーツァルト的ではない、という意味で・・
お客さんの反応が大きかったです。
特に前半、小節線がない(拍子がない)のを延々と弾くっていうのは
練習時に意外に苦労しました。
バロック的な(拍の最初が重くて、その音から渦を巻くようにリズムが生まれる)リズムの感じ方が身につくと問題ないのですが。
モーツァルトって、やっぱバッハなのね。













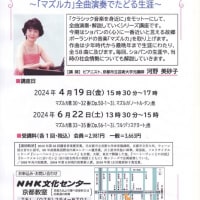
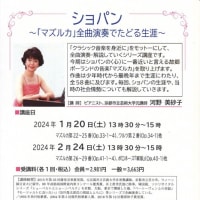
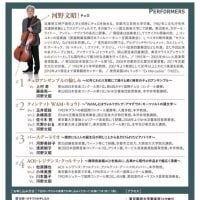
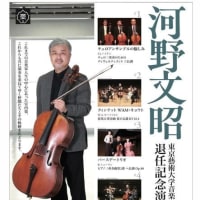
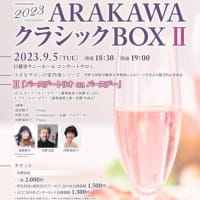








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます