しばらくサボってましたが、引き続き看護学校の学生さんからいただいた質問に答えていきましょう。
今回の質問は正確には次のように2問から成っていました。
「Q-1.考え方に人それぞれ癖というのはあるのか?
Q-2.あるとしたらどうすればよいのか?」
これもどうお答えするか難しい質問ですね。
どうしましょうか。
では、先日ご紹介したあの本を使ってお答えしてみることにしましょう。
あの本というのはこの本です。

この本では人間の強みを34個に分類していました。
本のなかでは触れられていないのですが、その34個は大きく4つのカテゴリーに分類できるようです。
実行力、影響力、人間関係構築力、思考パターンの4つです。
(正確には4番目のカテゴリーは 「戦略的思考力」 と名づけられていますが、
34の強みのなかに 「戦略性」 というのがあるので、
それとの混同を避けるためにここでは思考パターンと名づけておきます。)
今回のご質問には、この4番目の思考パターンのことをご紹介してみるのがいいかと思います。
思考パターンに分類される強みは8つあります。
内省、分析思考、戦略性、着想、学習欲、収集心、原点思考、未来志向の8つです。
ひとつひとつ簡単に説明してみましょう。
内省・・・理論的に理解を深め考え続けられる。物事を1人で深く概念的に考え続ける。
分析思考・・・複雑さの中にシンプルな原理を見つけ出せる。事実を基に冷静に物事の原因・理由を明らかにする。
戦略性・・・先を予測し、適切な最善策を見出せる。状況に応じた最善策を考え出す。
着想・・・まったく新しい何かを思いつく。リスクや既成概念に囚われずに考える。
学習欲・・・アンテナを張り関心の持てることをキャッチする。興味関心の惹かれるものを学習するプロセスを楽しむ。
収集心・・・役立ちそうなものや情報を集め、必要に応じて提供できる。周囲の役に立ちそうなものをとことん集める。
原点思考・・・出来事を正確に記憶、記録している。先人や過去の出来事を大切にする。
未来志向・・・未来のビジョンを創造する。未来のビジョンを描き、周囲に語る。
この中では最初の 「内省」 が一番ざっくりしていて、
とにかく考えるのが好きな人はだいたいみんな内省をもっています。
で、内省という強みを持っている人はそれだけでは終わらないで、
では具体的にどんな考え方をするかということで、
残り7つのうちのいくつかをさらに持っている場合が多いようです。
「分析思考」 というのは理系的な、データに基づき原因や法則性を突き止めていく考え方です。
「戦略性」 は現実の複雑な場面のなかでどう最適解を導き出すかという応用型の思考法です。
「着想」 はもうとにかくアイディア勝負です。
これらは互いに重なり合っているようでいて、
実は全然ベクトルの異なる異質な考え方だというのはご理解いただけるでしょうか。
同じく考えるのが好きといってもそれぞれまったく考え方の癖が違うわけです。
「学習欲」 と 「収集心」 というのは今の3つとはまた方向性がだいぶ違います。
「学習欲」 の人はとにかく勉強するのが好きです。
誰に強制されたわけでもないのに何カ国語もマスターしちゃうような人はこれを持っていたりします。
「収集心」 は思考パターンに分類していいのか若干悩ましいところで、
物の収集に走る場合は思考パターンというわけではないかもしれませんが、
情報の収集が好きという場合はたしかにこれも思考パターンのひとつと言えるでしょう。
こういう人は図書館に行くのとか大好きだったりしますね。
「原点思考」 は原語が 「Context」 なので 「文脈」 と訳したほうがいい気がしますが、
とにかく前後のつながりというか、過去が気になる人です。
どういう歴史的経緯を踏まえて現在に至ったのかということをものすごく大事にします。
歴史好きな人はほぼ間違いなくこれを持っています。
「未来志向」 の人はそれとは逆に未来のほうを向いています。
将来こうなりたい、こうなるべきだという方向に頭を使う人です。
こうやって並べてみると、同じ考えるのが好きといっても、
考え方は人それぞれまったく違うということがおわかりいただけるでしょうか。
私は上位5つのなかに内省、着想、戦略性が入っていました。
そして、ちょっとよけいにお金を出して1位から34位まで全部調べたことがあるのですが、
なんと最下位5つのなかに学習欲と原点思考が入っていました。
考えるのが好きといっても、アイディアや戦略を自由に考えているのが好きなだけで、
きちんと勉強したり、歴史的経緯を調べた上で考えるというのは大の苦手なんですね。
というわけで、一番目の質問には次のようにお答えしておきましょう。
A-1.考え方には人それぞれ癖があります。
同じ考えるのが好きにしても、得意な考え方、苦手な考え方は人によって千差万別です。
考え方に癖があるとしたらどうしたらいいのか、というのが2番目の質問でしたが、
以前にも書いたように、『さあ、才能に目覚めよう』 という本だったら以下のように答えるでしょう。
A-2.自分の得意な考え方をガンガン伸ばせばいいです。
自分の苦手な考え方は自分で何とかムリしてやってみようなんて思わずに、
それが得意な人にやってもらえばいいのです。
苦手なところを補ってみんなと同じようにやっていけるようにする、
というのが日本的な教育観かもしれませんが、
私はストレングス・ファインダーの考え方のほうが好きです。
強みというのは、特に意識しなくてもできてしまうことだし、本人やっていて楽しいことなので、
それを発揮している分にはまったく苦労もストレスもありませんし、
それでいてそこから生み出されるパフォーマンスはハイレベルなわけですから、
強みを活かして貢献したほうが自分にとっても周りにとっても幸せなはずです。
自分の苦手なところを克服するのではなく、強みをとことん伸ばしたほうがいい結果を残せるでしょう。
そのために大事なのは、まずは同じ考えるといってもいろいろな思考パターンがあることを知ること、
そのうち自分の得意な思考パターンが何であるのかを知ること、
他の人は自分と同じ思考パターンを持っているわけではないということを肝に銘ずること、
チームを組んだときに自分と違う思考パターンの人がいるとストレスがかかるので、
ついつい自分と同じ思考パターンの人ばかりを選びがちになってしまいますが、
たんなる友だち関係ならそれでもいいけれど、
何か仕事をしなきゃいけない、結果を出さなきゃいけないという場合には、
意図的にそれぞれ異なる思考パターンの人を集めるようにすること、等々です。
自分の苦手な部分は人に任せられるという状況を作っておいたほうが、
自分の得意なところを思う存分発揮できるはずです。
学生のうちはまだよくわからないかもしれませんが、
社会に出たときにはぜひ意識して実践してみてください!
今回の質問は正確には次のように2問から成っていました。
「Q-1.考え方に人それぞれ癖というのはあるのか?
Q-2.あるとしたらどうすればよいのか?」
これもどうお答えするか難しい質問ですね。
どうしましょうか。
では、先日ご紹介したあの本を使ってお答えしてみることにしましょう。
あの本というのはこの本です。

この本では人間の強みを34個に分類していました。
本のなかでは触れられていないのですが、その34個は大きく4つのカテゴリーに分類できるようです。
実行力、影響力、人間関係構築力、思考パターンの4つです。
(正確には4番目のカテゴリーは 「戦略的思考力」 と名づけられていますが、
34の強みのなかに 「戦略性」 というのがあるので、
それとの混同を避けるためにここでは思考パターンと名づけておきます。)
今回のご質問には、この4番目の思考パターンのことをご紹介してみるのがいいかと思います。
思考パターンに分類される強みは8つあります。
内省、分析思考、戦略性、着想、学習欲、収集心、原点思考、未来志向の8つです。
ひとつひとつ簡単に説明してみましょう。
内省・・・理論的に理解を深め考え続けられる。物事を1人で深く概念的に考え続ける。
分析思考・・・複雑さの中にシンプルな原理を見つけ出せる。事実を基に冷静に物事の原因・理由を明らかにする。
戦略性・・・先を予測し、適切な最善策を見出せる。状況に応じた最善策を考え出す。
着想・・・まったく新しい何かを思いつく。リスクや既成概念に囚われずに考える。
学習欲・・・アンテナを張り関心の持てることをキャッチする。興味関心の惹かれるものを学習するプロセスを楽しむ。
収集心・・・役立ちそうなものや情報を集め、必要に応じて提供できる。周囲の役に立ちそうなものをとことん集める。
原点思考・・・出来事を正確に記憶、記録している。先人や過去の出来事を大切にする。
未来志向・・・未来のビジョンを創造する。未来のビジョンを描き、周囲に語る。
この中では最初の 「内省」 が一番ざっくりしていて、
とにかく考えるのが好きな人はだいたいみんな内省をもっています。
で、内省という強みを持っている人はそれだけでは終わらないで、
では具体的にどんな考え方をするかということで、
残り7つのうちのいくつかをさらに持っている場合が多いようです。
「分析思考」 というのは理系的な、データに基づき原因や法則性を突き止めていく考え方です。
「戦略性」 は現実の複雑な場面のなかでどう最適解を導き出すかという応用型の思考法です。
「着想」 はもうとにかくアイディア勝負です。
これらは互いに重なり合っているようでいて、
実は全然ベクトルの異なる異質な考え方だというのはご理解いただけるでしょうか。
同じく考えるのが好きといってもそれぞれまったく考え方の癖が違うわけです。
「学習欲」 と 「収集心」 というのは今の3つとはまた方向性がだいぶ違います。
「学習欲」 の人はとにかく勉強するのが好きです。
誰に強制されたわけでもないのに何カ国語もマスターしちゃうような人はこれを持っていたりします。
「収集心」 は思考パターンに分類していいのか若干悩ましいところで、
物の収集に走る場合は思考パターンというわけではないかもしれませんが、
情報の収集が好きという場合はたしかにこれも思考パターンのひとつと言えるでしょう。
こういう人は図書館に行くのとか大好きだったりしますね。
「原点思考」 は原語が 「Context」 なので 「文脈」 と訳したほうがいい気がしますが、
とにかく前後のつながりというか、過去が気になる人です。
どういう歴史的経緯を踏まえて現在に至ったのかということをものすごく大事にします。
歴史好きな人はほぼ間違いなくこれを持っています。
「未来志向」 の人はそれとは逆に未来のほうを向いています。
将来こうなりたい、こうなるべきだという方向に頭を使う人です。
こうやって並べてみると、同じ考えるのが好きといっても、
考え方は人それぞれまったく違うということがおわかりいただけるでしょうか。
私は上位5つのなかに内省、着想、戦略性が入っていました。
そして、ちょっとよけいにお金を出して1位から34位まで全部調べたことがあるのですが、
なんと最下位5つのなかに学習欲と原点思考が入っていました。
考えるのが好きといっても、アイディアや戦略を自由に考えているのが好きなだけで、
きちんと勉強したり、歴史的経緯を調べた上で考えるというのは大の苦手なんですね。
というわけで、一番目の質問には次のようにお答えしておきましょう。
A-1.考え方には人それぞれ癖があります。
同じ考えるのが好きにしても、得意な考え方、苦手な考え方は人によって千差万別です。
考え方に癖があるとしたらどうしたらいいのか、というのが2番目の質問でしたが、
以前にも書いたように、『さあ、才能に目覚めよう』 という本だったら以下のように答えるでしょう。
A-2.自分の得意な考え方をガンガン伸ばせばいいです。
自分の苦手な考え方は自分で何とかムリしてやってみようなんて思わずに、
それが得意な人にやってもらえばいいのです。
苦手なところを補ってみんなと同じようにやっていけるようにする、
というのが日本的な教育観かもしれませんが、
私はストレングス・ファインダーの考え方のほうが好きです。
強みというのは、特に意識しなくてもできてしまうことだし、本人やっていて楽しいことなので、
それを発揮している分にはまったく苦労もストレスもありませんし、
それでいてそこから生み出されるパフォーマンスはハイレベルなわけですから、
強みを活かして貢献したほうが自分にとっても周りにとっても幸せなはずです。
自分の苦手なところを克服するのではなく、強みをとことん伸ばしたほうがいい結果を残せるでしょう。
そのために大事なのは、まずは同じ考えるといってもいろいろな思考パターンがあることを知ること、
そのうち自分の得意な思考パターンが何であるのかを知ること、
他の人は自分と同じ思考パターンを持っているわけではないということを肝に銘ずること、
チームを組んだときに自分と違う思考パターンの人がいるとストレスがかかるので、
ついつい自分と同じ思考パターンの人ばかりを選びがちになってしまいますが、
たんなる友だち関係ならそれでもいいけれど、
何か仕事をしなきゃいけない、結果を出さなきゃいけないという場合には、
意図的にそれぞれ異なる思考パターンの人を集めるようにすること、等々です。
自分の苦手な部分は人に任せられるという状況を作っておいたほうが、
自分の得意なところを思う存分発揮できるはずです。
学生のうちはまだよくわからないかもしれませんが、
社会に出たときにはぜひ意識して実践してみてください!










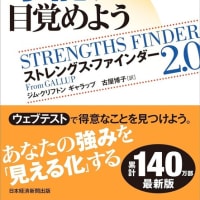















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます