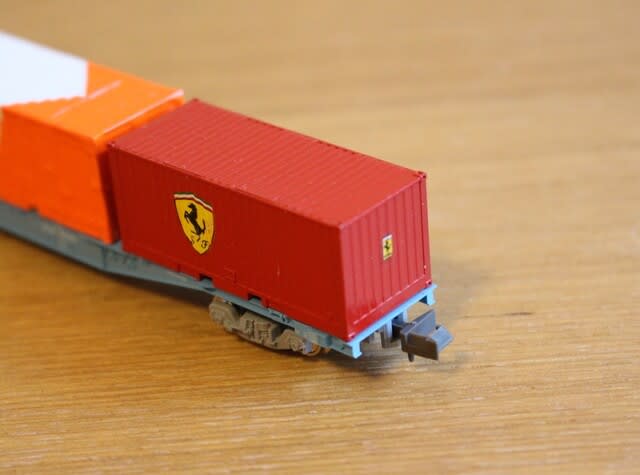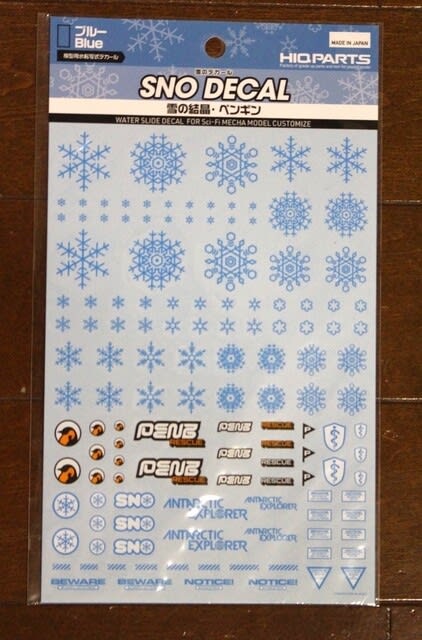TOMIXからかつて青森県を走っていた南部縦貫鉄道の車輌たちがNゲージでリリースされたほか、16番でもレールバス再販のアナウンスが出ています。もともと青森の車輌は興味がありますし、南部縦貫もかつて乗ったことがあります。そんなわけでこの鉄道のレールバスキハ101,102のセットと、先に発売されたキハ104を買いました。

(後ろのサボについては稿を改めてご紹介します)
まずはキハ101、102です。昭和37(1962)年、野辺地~七戸間の開業当初から平成9(1997)年の休止まで働き続けたレールバスで、この2輌が主力でありました。この時代のバスボディーをそのまま鉄道車輛にかぶせたようなスタイルが特徴でした。2輌とも動力つき、ライト点灯ということで、この小さな車体でライトまでついてしまうというのが、今のNゲージ車輌の進化ですね。昔、TOMIXからキハ02という国鉄のレールバスが発売されていて、こちらは45年前、我が家の最初の車輌群の一つでしたが、当然ライトもつきませんでしたし、入門用という感がありました。
さて製品の方ですが、せっかく2輌入っていますので片方は製品そのままで、もう片方はウェザリングをしてみました。
製品そのままの状態です。


こちらはウェザリングをしたもう一両、キハ102です。
片側側面から煙突のように屋根に出ている排気管を黒く塗りました。車体は全体に黒ずんだような汚れですが、ひどい汚れというわけでもありませんので、タミヤカラーのジャーマングレーを薄く溶いて窓回りなどに塗り、綿棒でふき取っています。床下はやはりタミヤカラーアクリルの「陸上自衛隊茶色」を薄く溶いて塗り、綿棒でふき取っています。土ほこりの汚れなどはやはり日本の土地に根差した迷彩色が一番近いと思い、この色をよく使っています。


前面です。

側面です。排気管だけでも黒く塗った方がリアルかなと思います。

一輌で運転する際は必要ありませんが、重連や牽引のためにウエイトも入っています。実際にはレールバスは単行での運用が基本でしたから、私もウエイトは乗せていません。かわいらしい小さな小さな車輌は、東北本線の列車を横目に、我が家でゆっくり走ってくれることでしょう。
続いて先に発売になったキハ104です。南部縦貫鉄道ではレールバスの他にラッシュ時(小学生の児童もスクールバスのように使っていたようです)、多客時用に国鉄からキハ10を昭和55(1980)年に1輌譲り受けています。その前に常総筑波鉄道のキハ103という車輌がおり、こちらはキハ101より一回り大きい程度の車輌だったようです。
トミーでは以前からキハ10を製品化していて、本品も基本的なつくりは変わりないようです。塗装も美しく再現されていますので、後は別付けの部品を取り付け、軽く汚しをかけた程度です。もともと酷使されていたわけでもないので、割ときれいな状態で最後までいたようです。




キハ104については「とれいん」平成3(1991)年10月号で写真が紹介されていて、これによると毎年2月に沿線の七戸の商店街の売り出し日、通称「まける日」があり、そういった時がこの車輛の出番だったようです。ちなみに「まける日」の列車は無料で運行がされていたということです。冬ともなれば雪で閉じ込められてしまう一帯ですので、特売日を設けて買い物客を呼び込もうという努力がうかがえる話ではあります。このエピソードを覚えていたこともあって、トミーがキハ104をリリースすると聞いて「ぜひ」となったわけです。確かにレールバスと比較すると大きさが段違いですね。
レールバスの方に戻しますが、16番でもその昔トミックスからキハ101は製品が出ており、私も持っておりますが、改造の種と言う不埒な理由での購入でした。さらにそれ以前に、ムサシノモデルからもこの形式は製品が出ており、こちらをお目にかけたいと思います。

同社の「田園の唄」というシリーズでローカル私鉄の車輌が次々リリースされていたことがあり、そのうちの一両として我が家にやってきました。20代だった私はまずNでは出ないだろうと思っていた車輌でしたし、ムサシノモデルさんの再現度ならとても素晴らしい製品だろう、ということでその分価格も張りましたが、独身貴族でイケイケだった私は購入したわけです。Nでは再現できないミラーなど、ちゃんとついています。

運転席に乗務員を座らせました。

前面の反対側です。ケーディーカプラーも同梱されていますが、実物も模型も連結等を前提としているわけではありませんので、そのままになっています。

車内にもう一人、乗務員が立っています。窓越しにネクタイ姿が見えますか?

側面です。


模型の話はここまで、次回は南部縦貫鉄道の実物の方の話をしましょう。

(後ろのサボについては稿を改めてご紹介します)
まずはキハ101、102です。昭和37(1962)年、野辺地~七戸間の開業当初から平成9(1997)年の休止まで働き続けたレールバスで、この2輌が主力でありました。この時代のバスボディーをそのまま鉄道車輛にかぶせたようなスタイルが特徴でした。2輌とも動力つき、ライト点灯ということで、この小さな車体でライトまでついてしまうというのが、今のNゲージ車輌の進化ですね。昔、TOMIXからキハ02という国鉄のレールバスが発売されていて、こちらは45年前、我が家の最初の車輌群の一つでしたが、当然ライトもつきませんでしたし、入門用という感がありました。
さて製品の方ですが、せっかく2輌入っていますので片方は製品そのままで、もう片方はウェザリングをしてみました。
製品そのままの状態です。


こちらはウェザリングをしたもう一両、キハ102です。
片側側面から煙突のように屋根に出ている排気管を黒く塗りました。車体は全体に黒ずんだような汚れですが、ひどい汚れというわけでもありませんので、タミヤカラーのジャーマングレーを薄く溶いて窓回りなどに塗り、綿棒でふき取っています。床下はやはりタミヤカラーアクリルの「陸上自衛隊茶色」を薄く溶いて塗り、綿棒でふき取っています。土ほこりの汚れなどはやはり日本の土地に根差した迷彩色が一番近いと思い、この色をよく使っています。


前面です。

側面です。排気管だけでも黒く塗った方がリアルかなと思います。

一輌で運転する際は必要ありませんが、重連や牽引のためにウエイトも入っています。実際にはレールバスは単行での運用が基本でしたから、私もウエイトは乗せていません。かわいらしい小さな小さな車輌は、東北本線の列車を横目に、我が家でゆっくり走ってくれることでしょう。
続いて先に発売になったキハ104です。南部縦貫鉄道ではレールバスの他にラッシュ時(小学生の児童もスクールバスのように使っていたようです)、多客時用に国鉄からキハ10を昭和55(1980)年に1輌譲り受けています。その前に常総筑波鉄道のキハ103という車輌がおり、こちらはキハ101より一回り大きい程度の車輌だったようです。
トミーでは以前からキハ10を製品化していて、本品も基本的なつくりは変わりないようです。塗装も美しく再現されていますので、後は別付けの部品を取り付け、軽く汚しをかけた程度です。もともと酷使されていたわけでもないので、割ときれいな状態で最後までいたようです。




キハ104については「とれいん」平成3(1991)年10月号で写真が紹介されていて、これによると毎年2月に沿線の七戸の商店街の売り出し日、通称「まける日」があり、そういった時がこの車輛の出番だったようです。ちなみに「まける日」の列車は無料で運行がされていたということです。冬ともなれば雪で閉じ込められてしまう一帯ですので、特売日を設けて買い物客を呼び込もうという努力がうかがえる話ではあります。このエピソードを覚えていたこともあって、トミーがキハ104をリリースすると聞いて「ぜひ」となったわけです。確かにレールバスと比較すると大きさが段違いですね。
レールバスの方に戻しますが、16番でもその昔トミックスからキハ101は製品が出ており、私も持っておりますが、改造の種と言う不埒な理由での購入でした。さらにそれ以前に、ムサシノモデルからもこの形式は製品が出ており、こちらをお目にかけたいと思います。

同社の「田園の唄」というシリーズでローカル私鉄の車輌が次々リリースされていたことがあり、そのうちの一両として我が家にやってきました。20代だった私はまずNでは出ないだろうと思っていた車輌でしたし、ムサシノモデルさんの再現度ならとても素晴らしい製品だろう、ということでその分価格も張りましたが、独身貴族でイケイケだった私は購入したわけです。Nでは再現できないミラーなど、ちゃんとついています。

運転席に乗務員を座らせました。

前面の反対側です。ケーディーカプラーも同梱されていますが、実物も模型も連結等を前提としているわけではありませんので、そのままになっています。

車内にもう一人、乗務員が立っています。窓越しにネクタイ姿が見えますか?

側面です。


模型の話はここまで、次回は南部縦貫鉄道の実物の方の話をしましょう。