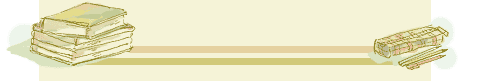昨日、一昨日とはちょっと違う朝。
昨日、一昨日とはちょっと違う朝。再び暑い夏が戻って来ました。
一気に秋・・とは、
なかなか行かないようですね。
いずれにしても、
もう少しの辛抱・・でしょうか。
気が付けば、9月もそろそろ半ば・・
この調子で行けば、いつの間にか
年末、なんて事になり兼ねません。
地に足を着けて
暮さねばなりませんね。
さて、冒頭の写真。
昨日に続き、今日もハモンドオルガン。
昨日のものよりは大分新しいですが、
それでもトーン・ホイル式です。
(鉄の歯車を回転させながら、
コイルを近付けて電流を作り、音に変換させる仕組み)
 今では貴重な楽器と
今では貴重な楽器となっています。
楽器もそうですが、
音もそうですね。
デジタル音の溢れている今は、
余計にそう思います。
電源を入れた時のジ~ッと
いう独特の音、そこからして
手作りの匂いが感じられますもの。

こちらも昨日の続きです。
今、改めてレコードを眺めてみますと、ジャケットが何と楽しいのでしょう。
演奏者の顔写真がほとんどですが、中にはこんな風に絵画や版画があったりします。
(写真左はパウムガルトの版画、右はベラスケスの 「8歳のマルガリータ」)
探すのがめんどうですので、手直にあるものを写したのですが、
涼しくなりましたら、他のものも探してみるつもりです。
ところで、今読んでいる三島由紀夫作 『豊饒の海Ⅱ「奔馬」』 に、
こんな記述を見つけました。
時代は昭和の初め。
世相は、少しずつ不穏になって来つつありますが、
まだまだ時間は、ゆっくり流れているようです。

| (中略)食事がすむと、 「レコード を聴きましょうか」 と言った。 部屋の一隅にマホガニー色に塗った 箱型の蓄音器がある。 電気蓄音機が流行っているのに、 この家では舶来のゼンマイ式を頑固に使っていた。 井筒が引き受けてハンドルを一杯に回した。(中略) 槇子は12インチの赤盤を選って、 ショパンのノクターン をコルトーが弾いたのを 器械にかけたが、 それは少年達の教養の外にあったのに、 しかも知ったかぶりをするではなく、 彼らは与えられた曲に素直に耳を傾けた。 すると馴染まぬ音楽の、 冷たい水に肌を沈めて泳ぐ快さに似たものが、 気持ちに沁み入った。(中略) 【三島由紀夫作 『豊饒の海Ⅱ「奔馬」より』】 |