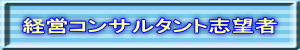■■【心de経営】 社風は会社の心 6 人事管理体制

新シリーズの【心de経営】は、「経営は心deするもの」という意味になります。それとともにフランス語の前置詞であります「de(英語のof)」を活かしますと、「経営の心」すなわち、経営管理として、あるいは経営コンサルタントとして、企業経営をどの様にすべきか、経営の真髄を、筆者の体験を通じて、毎月第二金曜日21時に発信いたします。
当面は、毎週金曜日21時にお届けします。
【筆者紹介】 特定非営利活動法人日本経営士協会 藤原 久子
北海道札幌市出身、20年間の専業主婦を経て、会計事務所に約4年半勤務。その後平成元年7月に財務の記帳代行業務並びに経理事務員の人材派遣業の会社を設立し、代表取締役として現在に至る。従業員満足・顧客満足・地域貢献企業を目指し、企業の永続的発展を願う。
平成22年には横浜型地域貢献企業の最上位を受賞、続いてグッドバランスの受賞により、新聞、雑誌の掲載をはじめ、ラジオやWebTV(日本の社長100・神奈川県社長t v)に出演したりして、各種メディアで紹介されている。

■ はじめに
自社の経営に当たりまして、何かと忙しい経営者に安心して事業に専念してほしいとの想いと、そして忙しい経営者に、私たちからは「もっと心の通いあうサービス提供を」という原点を忘れてはならないと常に考えております。また、「顧客第一主義」と「企業は人なり」の精神を揺るぎないものとして持ち続けることも大切です。
その信念に「学び」をプラスして更なる人間的魅力を形成してはじめて、従業員やお客様から信頼されるのです。そのためにも、まず自分自身を磨くことが大切です。
人にはそれぞれ自分なりの生き方があります。このメールマガジンを通して、当メールマガジンの購読者であります経営者様をはじめ、これから経営者として歩み始めるみなさまや日本経営士協会会員の気づきや学ぶ機会になれば、これほどに嬉しいことはございません。
 6 人事管理体制
6 人事管理体制
「心で経営」をテーマにお届けして参りましたが、それを実践している経営者様の考え方、自社の状況、社員の労働意欲について、また経営者様はご自身のことをよく理解しているでしょうか、等々を項目毎の評価をして、企業の総合力評価をすることで、何らかの気付きが生まれ、事業運営の参考にしていただければ幸甚です。
◇社内のコミュニケーション
経営理念は社内の隅々にまで行き渡っていますか、経営方針や経営政策を現場まで徹底させなければなりません。良好なコミュニケーションとは、上意下達(経営者の考えが速やかに組織の末端まで届く)、下意上達(組織の末端の意見が速やかに経営者に届く)が風通し良く行われることと、その上に情報の共有が必要不可欠といえます。
◇社内の整理整頓
ここでは、経営者ならびに社員のモラルが問われます。社員が仕事に遣り甲斐を感じ、職場環境も明るく、何と言っても会社内には活気ある職場環境が必要です。当然、業績にも反映し、おのずと社内の整理整頓もきちんと出来ているものです。
◇社員教育
長期的にみて社員の資質の向上をはかり、その道のプロ集団にしなければいけません。その為には日頃の研鑚の積み重ねが大きな力を発揮するのです。何と言っても社内に活気をつくる社員に、多くを委ねられる様な社員教育が必要です。
◇社内の労働環境
社内の労働環境とは、執務環境のほか、社員のやる気の向上に寄与する制度の整備を含みます。結果的に社員が自主的に仕事に対し創意工夫を重ね、発展持続させる基となっているのです。
これから暫くの間、「心で経営の実践」をテーマにして、お届けして参りたいと思います。これからもご愛読くださるようお願い致します。

■■ 経営コンサルタントを目指す人の60%が覧るホームページ ←クリック