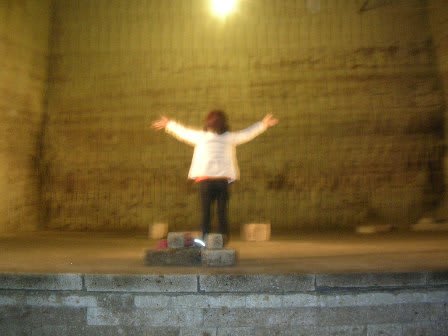11月2日(晴)
8時。上野からJR東北線にて、前回歩き終わった宇都宮まで行く。
1時間半ほどで宇都宮着。
道中を歩きだす前に、大谷資料館を見物しようと駅前から6番バス乗り場に行き、10:05分発の立岩行きバスに乗り込む。
大谷石採石場は、中学の頃学校の社会科見学で行った記憶あり。
昭和61年に採掘中止になったから、その頃はまだ石を切り出していたわけである。
その採掘場が、今は暗く冷たく静謐な地下神殿のように岩山の中に広がっている。
切り出し機械の跡も鮮やかに残り、まるで幾何学模様のように美しい。
たくまずしてステージのように切られた台状のところで指揮ポーズ(暗いのでボケボケ~ )
)
実際にコンサートは時々開催されているらしい。アカペラの合唱などはさぞよい響きになるだろう。
地下神殿から外に出ると明るい太陽光がまぶしい。
ここからまたバスで宇都宮に折り返し、日光道中を歩き出す。
奥州街道と日光街道の追分の標識。もう薄くなって読めない。こういう標識が鮮明だとありがたいのだけど。
↓ 読みにくい(><)
もう12時を過ぎていたので、町のお総菜屋さんでおにぎりを買って県立体育館の前庭のベンチに座りお昼とする。
しばらく歩くと細谷新道、賑やかな街並みが途絶え、並木が見え始める。このあたりは桜の並木。
日光杉並木はおよそ37キロメートルにわたって続くそうなので、このあたりからがちょうど杉並木になると思われるが、サクラであったりエノキであったりときどき杉がちらほらである。
左にみごとな竹林が見え始める。右側は栃木県農業試験場。
あちこちに柿の実り。
↓ 道の右側にほとんど一里塚と同じくらいの間隔で見られる古めかしい建物は今市から宇都宮に水を通すための接合井。
そろそろ徳次郎の宿場に入る。
徳次郎は「とくじら」と地元の人々は読むが、道路標示の読み仮名は「とくじろう」である。
「徳次郎」の名の由来については諸説紛々の感あり。
さて、この徳次郎宿場に入ったあたりの右側、豊かな畑の広がる道の奥に徳次郎城跡の案内板あり。
江戸時代以前の築城で平城。入ってみる。
は~~、ここはちょっと空気が違う。
しばし呆然。
外界と遮断された別次元の世界。ひとりで歩くには怖いくらいの古城の跡。
乱立する木々に巻きつけられた簡単な「内堀」「外堀」「本丸」といった紙がいっそう荒廃感を強くしている。
倒木がちょうどあちら側の下界とこちら側の城跡空間との結界のようでもある。
下界へ戻るとのどかな田園風景。ほっとする。
写真右側寄りにぽっかりとあいた黒い空間が冥界(城跡)への入り口である。
中徳次郎あたりの途中にある神社の説明板。徳次郎が「外鯨」と表記されていて、たいへん興味深い。
ちなみに日光植物園の近くでみた案内図には「久次良」という地名があり、ここから外(日光をはずれた村)の「久次良」、つまり「外久次良」になったという説もある。
ここから上徳次郎まで歩く予定だったが、もう時刻は4時、暗くなりはじめたので「大網」のバス停から宇都宮に戻ることにする。
徳次郎か次宿の大沢には宿がないのでしかたがない。(昔は宿場だったのに)
宇都宮での夕食はご存じ、宇都宮餃子。味は普通の餃子だけど、これだけ知名度をあげたにも理由があるそうだ。
宇都宮は、餃子のほかにジャズとクラシックと、そしてなんといっても大谷石の町である。
駅歩道橋下に鎮座まします餃子像。一見なんだかわからなかった(^^)
本日の歩行距離:約11㎞。
日光鉢石まで約26㎞。