減り始めた埼玉都民
「埼玉都民」、「東京県民」という言葉がある。同じ言葉を埼玉県から見たのと、東京都から見たのとの違いである。
70過ぎになって東京都への通勤を止めて、“24時間サイタマン”になるまで、まさしくその一人だったので、その実態はよく分かる。
朝早く(これは仕事の都合で、朝早い時もあれば、午後になることもある)家を出て、大混雑の電車に飛び乗る。時間が不規則な仕事だったため、帰宅時には酒が入り、ほとんどが午前様。家では寝るだけで、睡眠不足は出先の職場のソファーで補った。
土、日、休日は疲れがたまっているので、ひたする眠り、小さな子供へのサービスはほとんど出来なかった。
家では「パパはお休み中」で、近所や町内会との付き合いはまずない。だから、住んでいる地域のことは知らないし、関心もない。
地方選挙で誰が知事をやろうが、市長をやろうが無関心で、名前もうろ覚え。投票にもほとんど行かない。
衛星都市とかベッドタウンという言葉がある。私には文字どおりベッドタウンだった。
私ほど極端な例はそれほど多くないだろうが、程度の差があるだけだろう。
5年ごとの国勢調査に、「昼夜間人口比率」(夜間人口100人当たりの昼間の人口)、他市町村への通勤・通学比率があると知ったのは、東京通いを終えた後だった。
他市町村への通勤・通学が多いと、昼間の人口が少なくなるので、昼夜間人口比率が低くなるわけである。
最新の10年の国勢調査によると、昼夜間人口比率で埼玉県は88.6%と全国で最も低かった。東京都や大阪府周辺の県が低く、埼玉に続いて、千葉、奈良、神奈川、兵庫の順だった。
人口の1割以上が昼間は埼玉県を空にしているわけで、昼夜間人口の全国最低は、1990年の国勢調査から5回連続で続いている。
県内総人口(10年当時約719万人)に対する県外への通勤・通学者の比率は17%で、前回調査についで全国で最高だった。
比率ではなく実数では、県外に通勤・通学する15歳以上の県民は約106万人で、神奈川に次いで全国2位だった。比率では神奈川より高いのは、神奈川の方が人口が多いからだ。
県外への通勤・通学者のうち東京都への流出者は約94万人(就業84万人、通学10万人)だった。前回05年の国勢調査では、100万人超だったので、1990年から続いていた大台を割り込んだ。
1985年には約86万人だったが。90年に約109万人と大台を突破、95年に115万人のピークを迎えた後も、減少傾向ながら大台を維持していた。
もっとも混雑率が高いとされる山手線と京浜東北線は、首都圏トップクラスの200%を超していたが、16年には160~170% と「広げて楽に新聞を読める」150%に近づいたというから、うらやましい限りだ。
前回と比べると、就業者が5万人余減っている。高齢化で定年を迎え、退職し始めたのものとみられる。
今後も減少すると見られるものの、94万人は大げさに言えば、“民族移動”とも言える。これだけの数の人が毎日、東京との間を往復しているわけである。
この民族移動が埼玉県に与える影響は大きい。

















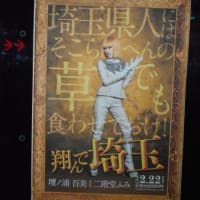


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます