戦後、激増した県人口 16年がピークに
現役時代、人口問題の勉強会に入っていたこともあって、人口動態には非常に興味がある。
人口は汐の満ち干と同じで、ひたひたと確実にやってくる。大騒ぎを始めている高齢化、人口減少もとうの昔から予測されていたことだ。
国勢調査は1920(大正9)年に始まり、5年ごと10月1日に行われる。以来、ひたすら右肩上がりを続け、人口増加率が日本一を誇ったこともある本県も、下降に転じそうだ。
人口を棒グラフ、増加率を折れ線グラフでまとめた県統計課の表を眺めていると、感慨深いものがある。
始まった20年にはわずか132万人(全国で16番目)だった。さいたま市の15年の人口が126万人(国勢調査)だから、県全体で現在のさいたま市程度の人口しかなかったことになる。
増加率を見ると、40(昭和15)から45(同20)年。60(同35)年から85(同60)年の25年間の伸びが目立つ。いずれも増加率が日本一だったころである。
40~45年は、敗戦間近な44~45年の1年間の伸びがめざましい。多くの軍需工場が京浜工業地帯から県内へ避難、学童や縁故者などの疎開者がどっと流入したからだ。
人口は40万人以上増え、45年には200万人を突破した。増加率は24%にも達した。
60~85年は、住宅団地や工業団地が一斉に造られ、本県が東京のベッドタウン化し、農業県から工業県に変貌した時期である。
35年に243万人(全国10位)だったのが、65年301万、75年482万、85年586万とうなぎのぼり。
85年には北海道を抜いて全国5位になり、この25年間に人口は2.4倍に増え、全国一の増加県になった。90年には640万人。
ついでながら、県人口が500万になったのは1977年、600万は87年、700万人は2002年だった。
都心から30km圏内の草加、八潮、越谷、新座などの人口は5倍以上に激増した。
北葛飾郡三郷村は、団地のおかげで、村になったのが56年なのに、64年には町、72年には市へと三段跳びをした。
その昔、10世紀初頭、武蔵国ができた頃には、埼玉県域の人口は約9万人と推定している歴史書もある。
1876(明治9)年、埼玉の現在の県域がほぼ確定したころは、ざっと90万人だったという。
県人口は2016年がピークで約730万(全国で5番目)。伸び率は前回比0・9%で過去最低だった。20年には713~724万、25年には700万、40年には630万人(人口問題研究所)に減少するという予測もある。
15年の国勢調査の結果では、63市町村で23市町村が人口増、40市町村が減を記録した。最も増えたのはさいたま市で126万人に。増加率では戸田市が10・6%と最大、吉川市が6.8%でこれに次いだ。減少数の最多は所沢市の6049人。人口は33万5000と越谷市を下回り5位になった。
減少数が大きいのは熊谷、本庄、行田市といった群馬県よりの県北部で、減少率が最大だったのは東秩父村の12・2%、次いで小鹿野町の9・9%だった。
超高齢化の進行とともに気になる数字である。
14年1月1日時点の総務省の人口動態調査では、外国人の流入は、中国人、ベトナム人が主で川口市(1370人)が最も多かった。県内への外国人の増加人数は約3978人で、47都道府県で一番多かった。
川口市の外国人人口は2万2958人で、さいたま市を上回り県内で最も多かった。埼玉県の日本人の人口の伸びは9007人だったので、外国人の流入で支えられている割合が高い。

















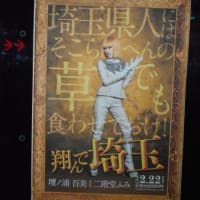


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます