
さいたま市から戸田市にかけての荒川左岸の河川敷にある「彩湖」は、洪水防止と東京都の飲料水確保を目指した人工的な大きな湖だ。
人工的といえ、その周囲は水と緑と鳥のすばらしい自然の宝庫に変わった。天気のいい日にママチャリで出かける散歩には最高のコースである。
その戸田市側はかつて、「戸田ヶ原」と呼ばれ、荒川の水が自由に出入りする広い湿原だった。この近くに「美女木」という地名がある。国道17号線を車で走った人なら覚えておられよう。
「風流な地名だな」と思っていた。江戸の文化・文政の頃に書かれた「新編武蔵風土記稿」に「京都から美しい官女数人が来て住んだ」ことから「美女来」が「美女木」になったと書いてあるとかで、それが定説になっているようだ。
異説もある。濡れて「びしょびしょ」を意味する日本語には豊富な擬態語「びじょびじょ」が語源だというのだ。「びじょびじょ木」が「美女木」になったというわけ。これでは夢もぶち壊し。現実とはいつもこうだ。
実際、荒川を挟んで、対岸の埼玉県朝霞市田島の美女地区には、「美女神社」という小さな祠(ほこら)があるそうだ。三方を川に挟まれた湿地帯で、水害に悩まされたところだったというから、こんど探しに行ってみよう。
全国的にも「美女」と言う地名は、じめついた湿地帯に多いというから、ロマンこそないが説得力はある。
「戸田ヶ原」は、そのような湿地を好むサクラソウの名所で、春には一面に赤い敷物を敷いたようだったと伝えられる。
江戸から花見に来るほどで、
春先は戸田も吉野の桜草
などといった句も残されている。
しかし、明治時代に採りつくされ、大正末には見る影もなくなった。第二次大戦後の開発や開墾で草原自体が姿を消した。国の特別天然記念物に指定され、さいたま市桜区に「田島ヶ原サクラソウ自生地」として柵に囲まれて保護されている。
サクラソウと同様、びしょびしょしたところが好きで、同じ運命をたどった戸田ヶ原の草に「トダスゲ」がある。
「トダシバ」という戸田ヶ原にちなむシバもあるので、最近まで混同していた。彩湖の「幸魂大橋」近くにある「彩湖自然学習センター」を何度か訪れるうちに、戸田市が「戸田ヶ原自然再生エリア」を設け、保護に乗り出しているという話を知った。「トダスゲ保存地」もあると聞いた。
いつか見に行こうと思いながら、無精者だから行きそびれて、やっと11年のゴールデンウイークに探しに出かけた。
戸田市の彩湖周辺に「彩湖・道満グリーンパーク」がある。荒川の旧河川の一部を利用した道満河岸釣り場があり、ヘラブナ釣りで知られる。その彩湖側に「自然再生エリア」があり、トダスゲが保存されている。
漢字で書けば「戸田菅」。スゲについて知っていることと言えば、菅笠や蓑細工の素材ということぐらいだ。
カヤツリグサ科スゲ属。属の下に世界で2千種、日本で二百以上の種がある。もっとも多くの種を含む属だとスゲの解説にあった。
1916(大正5)年、牧野富太郎博士が発見、1950年には絶滅したと思われていたのに、1992年に対岸の朝霞市の新河岸川で、「朝霞の自然を観る会」によって再発見された。
自生地も株も大変少なくなっているため、もっとも絶滅の惧れが強い「環境省絶滅危惧ⅠA類」に指定されている。
サクラソウのように花が咲くわけではないが、季節がピッタリだったので、穂も膨らんで、けなげに生きているのがいとおしかった。(写真)
このエリアには、昔、湿地に生えるハンノキの葉を食べて育つ、緑色に輝く美しく小さいチョウ「ミドリシジミ」(県のチョウに指定されている)やトウキョウダルマガエル(トノサマガエル)などが生息していた。トダスゲの間をミドリシジミが飛び交い、トノサマガエルがうごめく日を期待したい。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングが16年12月に公表した調査によると、戸田市は生物多様性を保全する取り組みで全国1位だった。

















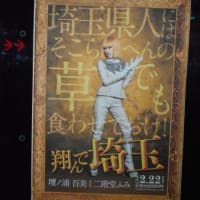


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます