
武蔵武士 畠山重忠
「武蔵武士」と言われて、思い出すのは、畠山重忠、熊谷次郎直実、それに、いくぶん時代が下がって太田道潅の三人であろう。
私にとっては、「坂東武士の鑑(かがみ)」と称えられた畠山重忠である。源義経の鵯(ひよどり)越えの逆(さか)落としで、椎の木を杖に愛馬「三日月」を背負って坂を下りる重忠の印象が強烈だからである。
日本の馬は、土壌や草にカルシウム分が少ないので、体躯が小さい。このため、後の日露戦争でロシアのコサック騎兵に対抗するため、秋山好古が苦労する話は、司馬遼太郎の「阪の上の雲」に詳しい。
実際、日本の野生馬を見ると、なるほど小さいので、「さもありなん」と思っていた。ところが、重忠の怪力ぶりは、事実ながら、重忠が逆落としに加わった史実はなく、後世の作り話と考えられるという。
それがなくとも、重忠の勇猛さは、源頼朝が武蔵から相模の国に入った際や奥州平泉攻めでも先陣を務め、義仲討伐では義仲との一騎打ちなどと戦功を挙げたことなどから明らかだ。頼朝の信頼も厚かった。
畠山重忠、熊谷次郎直実らの武蔵武士は、一の谷の戦では源氏の軍勢の重要な部分を占めた。一の谷の戦の後、武蔵国は頼朝の知行国となった。頼朝時代には、武歳武士は幕府の要職を占め、その体制を支えた。頼朝時代は武蔵武士の全盛時代だった。
重忠は音曲にも堪能で、鶴岡八幡宮で静御前が舞を披露した際、現在のシンバルに似た銅拍子で伴奏したことでも知られる。
ところが、北条時政の時代になって、武蔵武士の運命は暗転する。時政は頼朝に近く、現在の比企郡を支配していた比企能員(よしかず)を、自邸に招いて謀殺、比企氏一族を皆殺しにした。能員は、頼朝の後を継いだ頼家の庇護者だった。頼家は修善寺に幽閉され殺された。
能員は、頼朝の乳母の一人だった比企尼(ひきのあま)の甥で養子だった縁で、頼朝に重用された。比企尼は頼朝が旗揚げするまで、生活を支援した。能員の妻も頼家の乳母だった。能員の娘は頼家の長男を生み、能員は外祖父として権勢を振るった。
このような関係で、比企氏は北条氏を上回る権力を持つようになり、時政が危機感を持ったのが、比企氏の滅亡につながった。
畠山重忠も時政による頼朝派の御家人つぶしの犠牲者だった。きっかけはささいなことだった。時政の後妻牧の方の女婿だった平賀朝雅(ともまさ)の邸で開かれた酒宴で、重忠の子重保(しげやす)が朝雅と喧嘩したのである。
朝雅はこれを根に持って、「重忠父子が謀反を企てている」と牧の方を通じて時政に讒言、時政はまず重保を謀殺、ついで何も知らず鎌倉に向かっていた小人数の重忠一行に、大軍を派遣して滅ぼした。重忠42歳の時だった。
大軍を率いたのは、時政の後継者の義時。義時は後に重忠の無実を知るが、すでに後の祭り。武家政治というと聞こえはいいが、武士とは人殺し集団だということがよく分かる。
熊谷直実は出家、太田道潅は55歳で主家の家臣に入浴中に謀殺されるなど武蔵武士の典型たちの末路はいずれも哀れである。
埼玉県嵐山町には、畠山重忠が住んでいたと伝えられる館が残っている。はっきりとした証拠物は見つかっていないものの、近くの寺院から重忠の曾祖父秩父重綱の名前を書いた経筒が発見されており、この地が畠山氏の拠点だったとされている。
嵐山町の菅谷館と呼ばれるこの平山城は、総面積約13万平方mの広大さで、都幾川と槻川の合流地点を望む台地上にある。「比企城館跡群菅谷館」という名で国の史跡に指定されていて、重忠の銅像がある。
一方、畠山氏は深谷市畠山にも住んでいたとされる。同地には重忠が生まれたという畠山館跡もあり、畠山重忠公史跡公園になっていて、重忠の墓、産湯の井戸なども残り、銅像も立っている。
畠山氏は桓武平家につながる「坂東八平氏」の一つ秩父氏の一族。本来は平家なので、重忠らは頼朝の旗揚げの際に、当初は敵対した後、頼朝に帰順、忠臣となった。
「武蔵武士」と言われて、思い出すのは、畠山重忠、熊谷次郎直実、それに、いくぶん時代が下がって太田道潅の三人であろう。
私にとっては、「坂東武士の鑑(かがみ)」と称えられた畠山重忠である。源義経の鵯(ひよどり)越えの逆(さか)落としで、椎の木を杖に愛馬「三日月」を背負って坂を下りる重忠の印象が強烈だからである。
日本の馬は、土壌や草にカルシウム分が少ないので、体躯が小さい。このため、後の日露戦争でロシアのコサック騎兵に対抗するため、秋山好古が苦労する話は、司馬遼太郎の「阪の上の雲」に詳しい。
実際、日本の野生馬を見ると、なるほど小さいので、「さもありなん」と思っていた。ところが、重忠の怪力ぶりは、事実ながら、重忠が逆落としに加わった史実はなく、後世の作り話と考えられるという。
それがなくとも、重忠の勇猛さは、源頼朝が武蔵から相模の国に入った際や奥州平泉攻めでも先陣を務め、義仲討伐では義仲との一騎打ちなどと戦功を挙げたことなどから明らかだ。頼朝の信頼も厚かった。
畠山重忠、熊谷次郎直実らの武蔵武士は、一の谷の戦では源氏の軍勢の重要な部分を占めた。一の谷の戦の後、武蔵国は頼朝の知行国となった。頼朝時代には、武歳武士は幕府の要職を占め、その体制を支えた。頼朝時代は武蔵武士の全盛時代だった。
重忠は音曲にも堪能で、鶴岡八幡宮で静御前が舞を披露した際、現在のシンバルに似た銅拍子で伴奏したことでも知られる。
ところが、北条時政の時代になって、武蔵武士の運命は暗転する。時政は頼朝に近く、現在の比企郡を支配していた比企能員(よしかず)を、自邸に招いて謀殺、比企氏一族を皆殺しにした。能員は、頼朝の後を継いだ頼家の庇護者だった。頼家は修善寺に幽閉され殺された。
能員は、頼朝の乳母の一人だった比企尼(ひきのあま)の甥で養子だった縁で、頼朝に重用された。比企尼は頼朝が旗揚げするまで、生活を支援した。能員の妻も頼家の乳母だった。能員の娘は頼家の長男を生み、能員は外祖父として権勢を振るった。
このような関係で、比企氏は北条氏を上回る権力を持つようになり、時政が危機感を持ったのが、比企氏の滅亡につながった。
畠山重忠も時政による頼朝派の御家人つぶしの犠牲者だった。きっかけはささいなことだった。時政の後妻牧の方の女婿だった平賀朝雅(ともまさ)の邸で開かれた酒宴で、重忠の子重保(しげやす)が朝雅と喧嘩したのである。
朝雅はこれを根に持って、「重忠父子が謀反を企てている」と牧の方を通じて時政に讒言、時政はまず重保を謀殺、ついで何も知らず鎌倉に向かっていた小人数の重忠一行に、大軍を派遣して滅ぼした。重忠42歳の時だった。
大軍を率いたのは、時政の後継者の義時。義時は後に重忠の無実を知るが、すでに後の祭り。武家政治というと聞こえはいいが、武士とは人殺し集団だということがよく分かる。
熊谷直実は出家、太田道潅は55歳で主家の家臣に入浴中に謀殺されるなど武蔵武士の典型たちの末路はいずれも哀れである。
埼玉県嵐山町には、畠山重忠が住んでいたと伝えられる館が残っている。はっきりとした証拠物は見つかっていないものの、近くの寺院から重忠の曾祖父秩父重綱の名前を書いた経筒が発見されており、この地が畠山氏の拠点だったとされている。
嵐山町の菅谷館と呼ばれるこの平山城は、総面積約13万平方mの広大さで、都幾川と槻川の合流地点を望む台地上にある。「比企城館跡群菅谷館」という名で国の史跡に指定されていて、重忠の銅像がある。
一方、畠山氏は深谷市畠山にも住んでいたとされる。同地には重忠が生まれたという畠山館跡もあり、畠山重忠公史跡公園になっていて、重忠の墓、産湯の井戸なども残り、銅像も立っている。
畠山氏は桓武平家につながる「坂東八平氏」の一つ秩父氏の一族。本来は平家なので、重忠らは頼朝の旗揚げの際に、当初は敵対した後、頼朝に帰順、忠臣となった。

















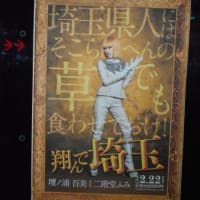


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます