
大宮盆栽村 さいたま市盆栽町
さいたま市北区の盆栽町で毎年開かれる「大盆栽まつり」(5月3~5日)が、13年に30回を迎えた。
市民盆栽展やセリ市、盆栽、盆器、山谷草の即売会などが開かれ、愛好者でにぎわった。
「大宮盆栽村」と呼ばれるこの町の中には現在、開村当時からあり、国後島で手に入れたえぞ松で知られる「蔓青園」、著名人の来訪が多く、皇居の盆栽管理責任者を務める「九霞園」、ケヤキやカエデなどの「雑木盆栽」が多くそろっている「芙蓉園」、種類の違う植物や花木も使う「彩花盆栽」の「清香園」、庶民的な「藤樹園」、鉢の品揃えが豊富な「松涛園」の6園がある。
最盛期の1930年代には盆栽園は約30あった
江戸時代から現在の東京都文京区千駄木の団子坂、同区駒込の神明町などには、植木屋の盆栽業者が多かった。
ところが、1923(大正12)年の関東大震災で大打撃を受け、より広い土地と適した土壌(水はけのいい関東ローム層の赤土)、豊富な地下水を求めて、当時、「源太郎山」と呼ばれていたこの雑木林に白羽の矢を立て、集団移住、盆栽作りの理想郷建設を目指した。
1925(大正14)年に盆栽村が誕生した。「蔓青園」が開園したのは、この年である。白い幹が大きくうねる、推定樹齢2千年を超す真柏(しんぱく)の盆栽があるので有名。当初の盆栽園約20園のうち唯一今も続いている。
1928(昭和3)年には、盆栽業者と盆栽愛好家のための町を作るため,盆栽村組合(組合員20人)は、盆栽村に住む条件として、「盆栽を十鉢以上持つ」「二階家は建てない」「垣は生垣とする」「門戸を開放する」などの規約を決めた。
盆栽愛好家のほとんどは都内に本宅があり、盆栽村の家は別荘で、贅を凝らした造りだった。その中には、森鴎外の長男・於兎(おと)のしゃれた洋館もあった。
移住組ではなく、1929(昭和4)年開園したのが「九霞園(きゅうかえん)」。趣味が高じて盆栽師になった初代園主・村田久造は、1931(昭和6)年から,宮内庁・大道(おおみち)庭園の盆栽仕立場を手伝った。
終戦直後には,宮内省(宮内庁)の要請で,枯死寸前だった皇居内の盆栽の救済に当たった。二代目の村田勇さんも、皇居の盆栽管理の責任者を務めている。
初代は吉田茂元首相ら政界要人や,皇族・秩父宮家などの盆栽の管理・育成にも当たった。
1965(昭和40)年、「日本盆栽協会」発足で初代会長になる吉田首相は1955(昭和30)年、九霞園を訪ねたこともある。
国内で最も有名な盆栽の一つとされる吉田首相遺愛の欅(けやき)や池田首相の蝦夷松(えぞまつ)などの名品が園内に残っている。
初代は1937(昭和12)年のパリ万国博覧会に盆栽を出品、会場の最高の人気を呼んで、金大賞を受賞した。
1950(昭和27)年には日本盆栽組合(日本盆栽協同組合の前身)の組合長に就任した。
国際的にBONSAIの人気は高まり、1963(昭和38)年、西ドイツのハインリッヒ・リュプケ大統領が九霞園を訪問している。

















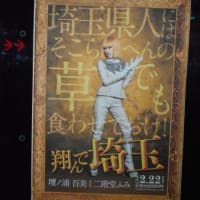


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます