平和な生活が一瞬にして崩れ去る。
2011年3月 11日 14時 46分、三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東 130Km付近で、深さ約 24Kmを震源とするマグニチュード 9.0 の地震が発生しました。

東北地方は過去に幾度となく地震や津波の被害を受けた歴史があり、先人より津波警報が出たら直ぐ高台へ避難するようにとの聞き伝えがあり、地域の人々全員が助かった地区があります。
自然災害は、いつどこで何がどの様に起こるか? 図り知ることは出来ません。
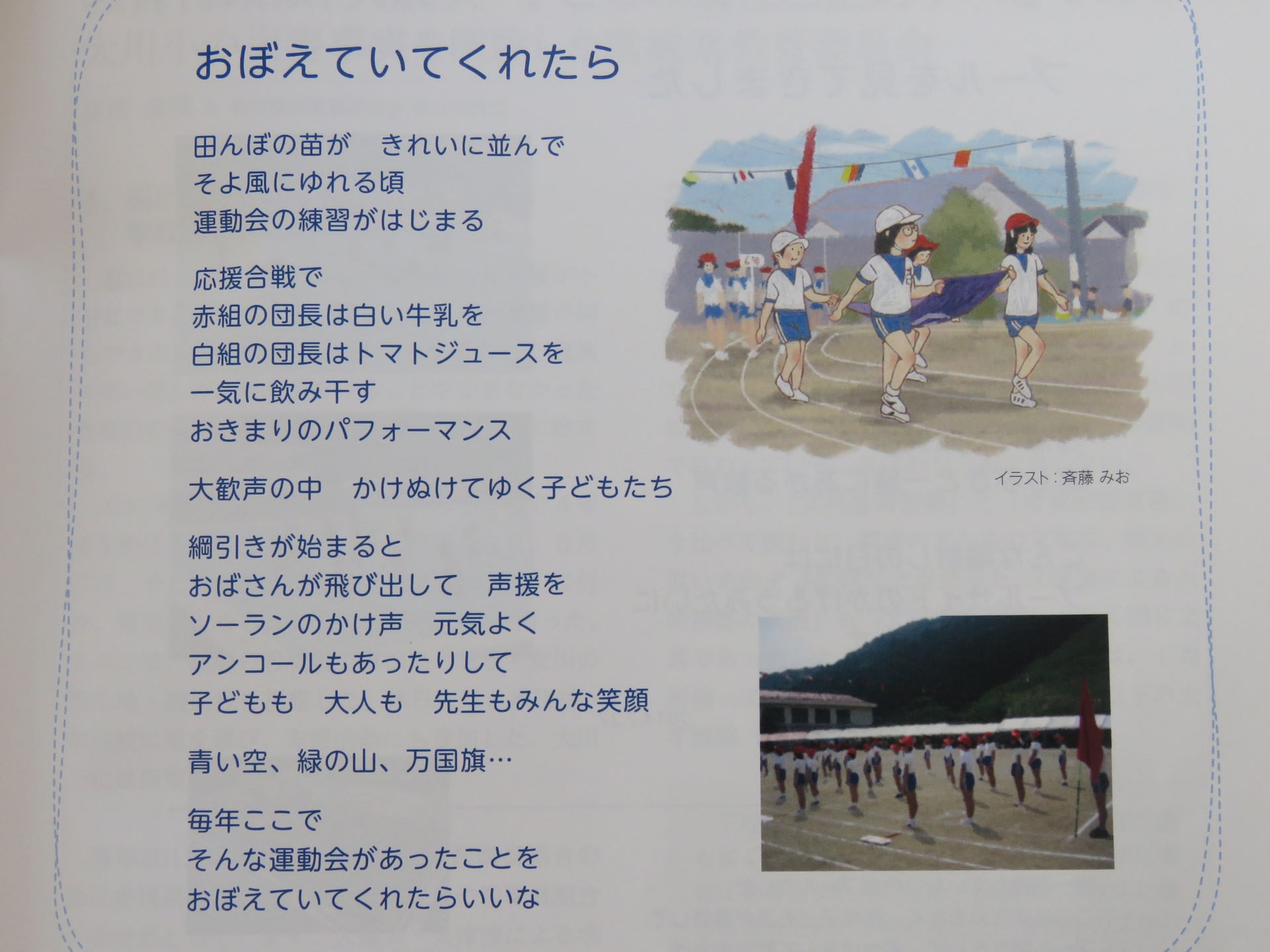
でも、過去に発生した事例の対処法は前記の「聞き伝え」を含め色々研究されています。
その地震による津波の影響で東京電力福島第一原子力発電所が水素爆発を起こし、強制避難を強いられた被災者の皆さんが国に対して損害賠償を求めた集団訴訟をし、11年越しの被災者皆さんの願いは届いたのでしょうか?

2022年6月17日、福島第一原発事故で被害を受けた住民の方々が国に損害賠償を求めた『避難者集団訴訟』で最高裁の判決が出されました。
🌟 国の責任は認めず 🌟
原子力発電所事業は『国策民営』で過酷事故など一切起こらない ❝安全神話❞ のみが強調され進められてきました。
確かに既存の原発の発電費用は比較的安い、温室効果ガスが出ないといった利点はあるが、ひとたび事故が起きた時の被害や原発から出る『核のゴミ』の処理方法で、それぞれ原発を抱えた地域ともめています。
 四国の愛媛県西宇和郡伊方町にある伊方原発は中央構造線という大きな断層の上にあり、1992年、四国電力伊方原発は、非常用発電機が動かなかったり、燃料切れが起これば、福島と同様の事故となるため、最高裁では「深刻な災害が万が一にも起こらない様に」と 2002年に判決を出し、現在は操業停止中の様であります。
四国の愛媛県西宇和郡伊方町にある伊方原発は中央構造線という大きな断層の上にあり、1992年、四国電力伊方原発は、非常用発電機が動かなかったり、燃料切れが起これば、福島と同様の事故となるため、最高裁では「深刻な災害が万が一にも起こらない様に」と 2002年に判決を出し、現在は操業停止中の様であります。
その判決が出されてから、9年もの時間があったにもかかわらず①津波が弱点であること。②炉心溶融になる可能性がある。ことが議論されていたにもかかわらず、東京電力も国も動かなかった。
 1999年9月 茨城県東海村にあった核燃料会社のウラン加工工場で起きた臨界死亡事故でも、国の初動対応は遅く、非常に適切な避難要請は、村長の判断で行われたとのことです。
1999年9月 茨城県東海村にあった核燃料会社のウラン加工工場で起きた臨界死亡事故でも、国の初動対応は遅く、非常に適切な避難要請は、村長の判断で行われたとのことです。








































2011年に福島第一原発から5Kmの場所に現地対策本部が設置され、経済産業省や自衛隊、東電などから150人が集められたそうです。それでも、深刻な原発事故は想定しなかった。
その後、原発が水素爆発すると、対策本部のセンター内の放射線量が急上昇し、事故の4日後に全員が撤退を始めたとのことです。
近くの双葉病院にいた患者さんは置き去りにされ、1ヶ月で約50名の患者さんが亡くなられています。
強制避難を命じられた10万人近い住民の誘導も行わず、自治体任せであったとのことです。

事故が起きたのも、事故後の被害が拡大し長引いたのも、安全への配慮、責任が放棄されたためではないのか?
人の生命・身体は勿論、環境にも取り返しのつかない危害を及ぼす原発災害を、万が一にも起こしてはならない。
この様な思いがあればこそ、今回の様な結論(判決)には至らなかったように思います。

現在は音頭をとる人間はアチコチに居るようですが、全てのことに対して曖昧さを前面に出し責任者不在の状態。
東京五輪の経費の問題、森友・加計問題、桜を見る会、コロナ感染防止対策、財務省の公文書改ざんなど、責任の曖昧さが大手を振って歩き回る時代、何か可笑しいですね。
この原発事故の『避難者集団訴訟』の最高裁判決なんですが、裁判官4人のうち3人の多数意見で決まった。 裁判官は国家公務員で司法も国の関連会社化し、一般の会社ではありえないと思います。
この判決で政府も電力不足を理由に原発再稼働を堂々と進めるべく、政策運営の柱となる骨太の方針に『原発の最大限活用』を加えたようです。
ただ1人、反対意見を主張して下さった三浦 守裁判官がいました。 ❝ 水密化措置は十分可能であったと述べられ、実効ある対策をとらない東電を容認した国の責任を厳しく指摘した。津波予測をもとに国と東電が法令に従って真摯な検討を行っていれば、事故は回避できた可能性が高いとし、「想定外」という言葉で免責することは許されないとの立場をとられた。❞
御立派な裁判官でありエールを送りますが、国に逆らう人はきっと日向から消されてしまうのでしょうね。

この様に国は被災者に対して『起きてしまったことは仕方ない。後は自らで対応して下さい。』と言っています。
現在、国内で稼働中の原子力発電所は 54基あるようです。建設中もあるそうです。 その地域の自治体は国からアメをもらっているので仕方ないのかもしれませんが、地震大国であり、異常気象による被害の想定外が増加しています。
今回の最高裁の判決を見ると、今後どんな大きな事故が発生するのか分からない仮定のことについては一切考えないことを基本とした国で、今後はどこの地域の人々が泣くのかな? なんて余計なことを考えてしまいます。

もう直ぐ参議院議員選挙の投票日です。
以前国会で 118回も虚偽答弁をした人がいますが、普通の人間であれば恥ずかしくて人前に出られないと思いますが、平然として今回の参議院選挙の応援演説をしている。
きっと、応援演説も口から出まかせなんでしょうね。 どうせ国民なんか、すぐ忘れるから・・・・・。
皆さん、7月10日は参議院議員選挙です。忘れずに投票に行きましょう!
※ ご覧頂き、ありがとうございます。

 周回マップ。
周回マップ。

 写真撮影のみで通過、11 時05分。
写真撮影のみで通過、11 時05分。

 自然歩道は長者ヶ岳から南下し、山梨県側の南西方向へと下って行く。
自然歩道は長者ヶ岳から南下し、山梨県側の南西方向へと下って行く。

 2座をつなぐ尾根上には先日の日向山ほどではなかったが、綺麗なキノコが目に付いた。
2座をつなぐ尾根上には先日の日向山ほどではなかったが、綺麗なキノコが目に付いた。







 何故かタヌキの置物が迎えてくれた。
何故かタヌキの置物が迎えてくれた。


 上部が、雲の上に少し見えた。
上部が、雲の上に少し見えた。 北西側には南アルプスが遠望出来るはずであったが、残念なことに雲の中だった。
北西側には南アルプスが遠望出来るはずであったが、残念なことに雲の中だった。





 自分の車を停めた所が確認できた。
自分の車を停めた所が確認できた。

 冷えて来た。 12時 15分、下山開始。 先程通過してきた上佐野分岐から、この先の休暇村富士への分岐まで
冷えて来た。 12時 15分、下山開始。 先程通過してきた上佐野分岐から、この先の休暇村富士への分岐まで 東海自然歩道
東海自然歩道 を下る。
を下る。


 ここからの下りは樹林帯の中で展望なし。
ここからの下りは樹林帯の中で展望なし。














![[ザノースフェイス] カットソー L/S WARM CREW ロングスリーブウォームクルー レディース NUW66135 ブラ...](https://m.media-amazon.com/images/I/31U7US8l8zL._SL160_.jpg)
![[ミレー] アンダーウェア ドライナミックメッシュノースリーブクルー メンズ Black-Noir EU L/XL (日本...](https://m.media-amazon.com/images/I/617+R0YMEXL._SL160_.jpg)



 の真西にある天子
の真西にある天子 山塊を歩く。
山塊を歩く。
 前線や台風
前線や台風 の影響で中々天気が安定せず、コロナを気にせず安心して歩ける山にも行き難い。
の影響で中々天気が安定せず、コロナを気にせず安心して歩ける山にも行き難い。






 に登録した登山アプリが何度も
に登録した登山アプリが何度も

 さっきの分岐を右に行くのか
さっきの分岐を右に行くのか  と引き返し、分岐で付近を確認したら「天子ヶ岳」への標示板が草むらに隠れていた。
と引き返し、分岐で付近を確認したら「天子ヶ岳」への標示板が草むらに隠れていた。

 分岐から未舗装の林道を進み、以後コンパスでも確認しながら前進した。それからスマホは静かになった。
分岐から未舗装の林道を進み、以後コンパスでも確認しながら前進した。それからスマホは静かになった。




 をキョロキョロ探しながら進む。 先日、花の先生に同行して頂いた時に見た花らしいものを発見、撮影したものの名前は不明。
をキョロキョロ探しながら進む。 先日、花の先生に同行して頂いた時に見た花らしいものを発見、撮影したものの名前は不明。


 頭を雲の上に出した富士山を発見。下界では見えないものが見えた。
頭を雲の上に出した富士山を発見。下界では見えないものが見えた。

 登山道に変身、岩や木の根に摑まりながら体を引き上げる。厳しかったが登り続けることは出来た。
登山道に変身、岩や木の根に摑まりながら体を引き上げる。厳しかったが登り続けることは出来た。












 前から花の会という仲間の皆さんと共に山歩きをするようになり、サポート役を務めさせて頂き、皆さんには自然の花を楽しんで頂きました。
前から花の会という仲間の皆さんと共に山歩きをするようになり、サポート役を務めさせて頂き、皆さんには自然の花を楽しんで頂きました。
 必須で、各種の運動を続けながら単独で山歩きを継続しています。
必須で、各種の運動を続けながら単独で山歩きを継続しています。













 写真は蕾の状態。 細い柄の先に紅紫色でやや細長い花(頭花)を付け、花の付け根(総苞)は筒状で粘らず、細いトゲの部分が強く反り返るのが特徴のようです。 花のつく枝が長く細いことから、こう呼ばれています。
写真は蕾の状態。 細い柄の先に紅紫色でやや細長い花(頭花)を付け、花の付け根(総苞)は筒状で粘らず、細いトゲの部分が強く反り返るのが特徴のようです。 花のつく枝が長く細いことから、こう呼ばれています。











 、赤や白、紫など沢山のキノコ、それに蛇のお出迎えまで受けました。
、赤や白、紫など沢山のキノコ、それに蛇のお出迎えまで受けました。









![夏の花 セイロンライティアの鉢植え [イイハナ・ドットコム] フラワーギフト 花ギフト プレゼント 誕生...](https://m.media-amazon.com/images/I/51VKRYnIioL._SL160_.jpg)

 文化財保護法で指定されている植物の場合は、この法律および施行規則で罰せられます。 また、各種公園指定を受けている山地での採集は禁止されています。
文化財保護法で指定されている植物の場合は、この法律および施行規則で罰せられます。 また、各種公園指定を受けている山地での採集は禁止されています。













 不安定で、豪雨・雷雨はテレビで良く目にします。 なので防雨対策は万全にして、8時出発。道路の反対側に見える階段から登り始めます。
不安定で、豪雨・雷雨はテレビで良く目にします。 なので防雨対策は万全にして、8時出発。道路の反対側に見える階段から登り始めます。









 流れた瞬間に川上村の高原野菜畑が見えたり、一部青空が見えたり、何とも忙しい景色でした。
流れた瞬間に川上村の高原野菜畑が見えたり、一部青空が見えたり、何とも忙しい景色でした。



 であれば瑞牆山、金峰山などが間近に見えるようです。 曇天につき下界よりは
であれば瑞牆山、金峰山などが間近に見えるようです。 曇天につき下界よりは  涼しく、20分ほどノンビリ休憩した。山でのミカンは美味しい。
涼しく、20分ほどノンビリ休憩した。山でのミカンは美味しい。
 開始。 午後も早い時間なので、高速道路は空いており快適に走り 16時前に帰宅できた。 下界は
開始。 午後も早い時間なので、高速道路は空いており快適に走り 16時前に帰宅できた。 下界は

 『山を想えば人恋し、人を想えば山恋し』
『山を想えば人恋し、人を想えば山恋し』
















 と感じた瞬間でした。
と感じた瞬間でした。
















 山道を歩くのも、また一味違った心地よさが味わえます。
山道を歩くのも、また一味違った心地よさが味わえます。






















 続いています。涼しい雪渓の上を歩いて下さい。
続いています。涼しい雪渓の上を歩いて下さい。
 の様に列をなして登る光景は、白馬岳(標高 2932m)の夏の風物詩となっています。
の様に列をなして登る光景は、白馬岳(標高 2932m)の夏の風物詩となっています。

 お花畑
お花畑 が現れ、綺麗な高山植物に癒されながら疲れを忘れ頑張る。 何度も山仲間を案内したが、不思議と大雪渓は快晴で皆さんが喜んでくれた。
が現れ、綺麗な高山植物に癒されながら疲れを忘れ頑張る。 何度も山仲間を案内したが、不思議と大雪渓は快晴で皆さんが喜んでくれた。

 音を立てずに落ちて来るので、足元ばかり見ての登山は大変危険なので回りを見たり、特に左手には注意が必要です。
音を立てずに落ちて来るので、足元ばかり見ての登山は大変危険なので回りを見たり、特に左手には注意が必要です。






















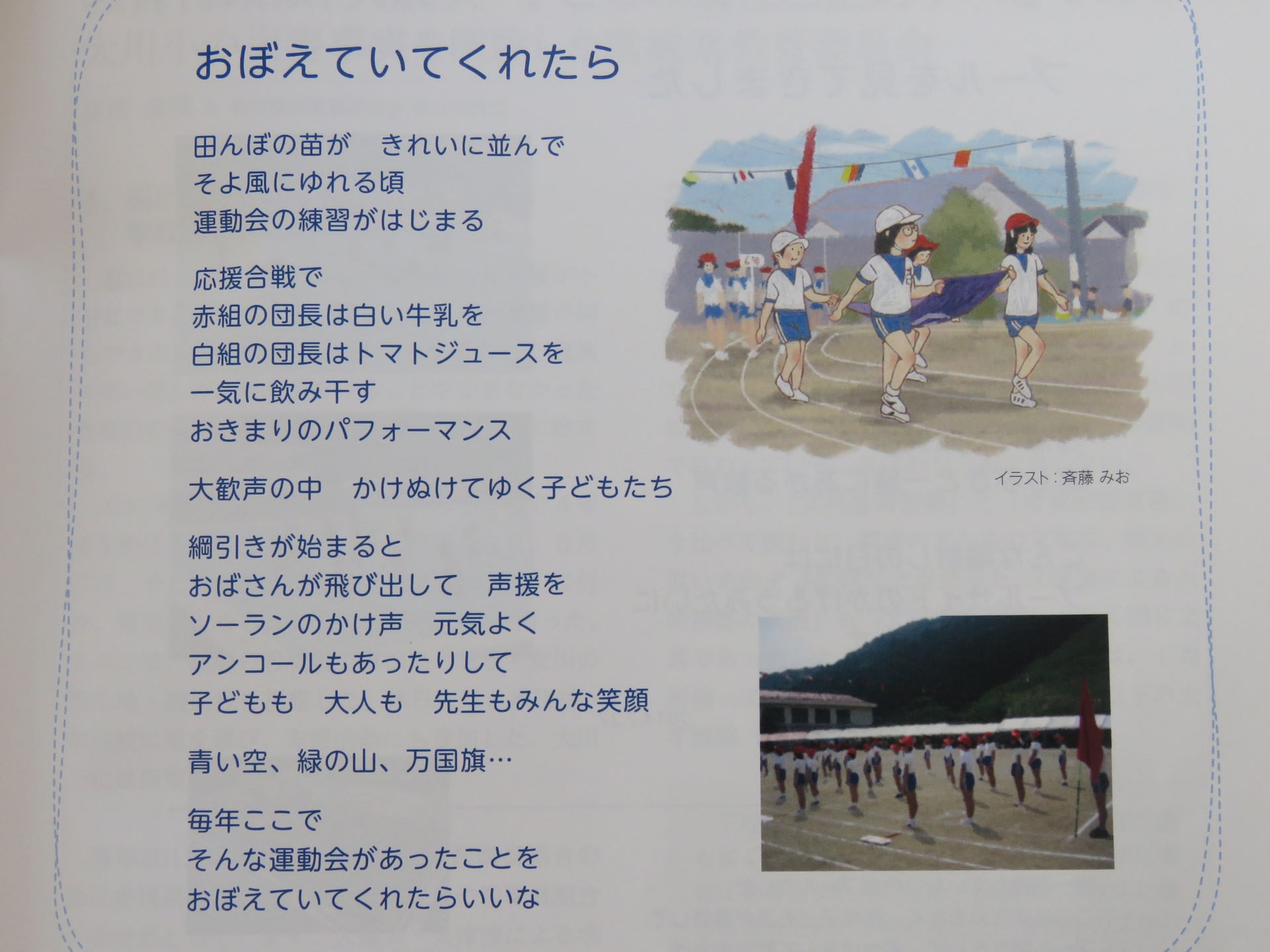

 四国の愛媛県西宇和郡伊方町にある伊方原発は中央構造線という大きな断層の上にあり、1992年、四国電力伊方原発は、非常用発電機が動かなかったり、燃料切れが起これば、福島と同様の事故となるため、最高裁では「深刻な災害が万が一にも起こらない様に」と 2002年に判決を出し、現在は操業停止中の様であります。
四国の愛媛県西宇和郡伊方町にある伊方原発は中央構造線という大きな断層の上にあり、1992年、四国電力伊方原発は、非常用発電機が動かなかったり、燃料切れが起これば、福島と同様の事故となるため、最高裁では「深刻な災害が万が一にも起こらない様に」と 2002年に判決を出し、現在は操業停止中の様であります。 1999年9月 茨城県東海村にあった核燃料会社のウラン加工工場で起きた臨界死亡事故でも、国の初動対応は遅く、非常に適切な避難要請は、村長の判断で行われたとのことです。
1999年9月 茨城県東海村にあった核燃料会社のウラン加工工場で起きた臨界死亡事故でも、国の初動対応は遅く、非常に適切な避難要請は、村長の判断で行われたとのことです。




![[おひとり様2点限り]富士山天然水バナジウム含有 2L×6本(1ケース) [ヘルスケア&ケア用品]](https://m.media-amazon.com/images/I/513q9B9f0KL._SL160_.jpg)
 20分で登山準備を済ませ
20分で登山準備を済ませ










































 桜
桜

















 『幸福を呼ぶ花』
『幸福を呼ぶ花』















