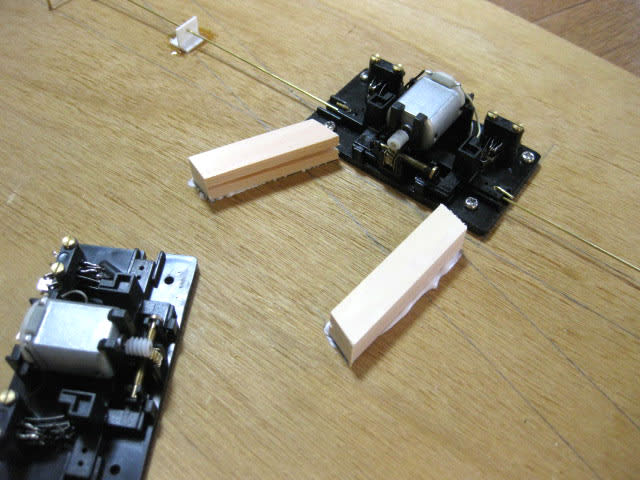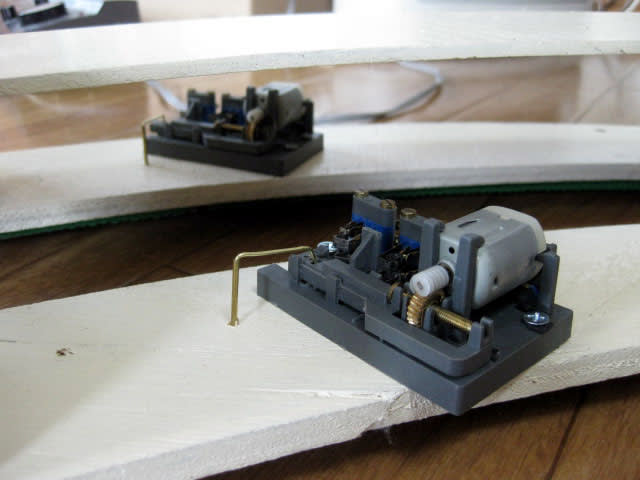こんばんは。
引き続き萬来軒を製作しています。
正面には引戸のまわりにフチをつけ、その左右に1個ずつ料理サンプルケースの外枠だけを作りつけました。
プリンタで作った仮看板は外しました。

裏側からみたところです。当初のデザインでは右から勝手口、便所、調理場という順番にしてあったのですが、実際は裏口はなく、右横の出入口が実質勝手口になっているようでしたので、便所と調理場だけにしました。その調理場も実際は窓がないようでしたが、あまりに何もないとつまらないので、内側に開く高窓を設けました。寸法的には上の写真の正面側の天窓をそっくりコピーした位置に開けてあります。

さすがに1/80の食品サンプルをガチで作るのは厳しいので、「らしく」作るか、写真でも貼ろうかと思っています(^^;
よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村
引き続き萬来軒を製作しています。
正面には引戸のまわりにフチをつけ、その左右に1個ずつ料理サンプルケースの外枠だけを作りつけました。
プリンタで作った仮看板は外しました。

裏側からみたところです。当初のデザインでは右から勝手口、便所、調理場という順番にしてあったのですが、実際は裏口はなく、右横の出入口が実質勝手口になっているようでしたので、便所と調理場だけにしました。その調理場も実際は窓がないようでしたが、あまりに何もないとつまらないので、内側に開く高窓を設けました。寸法的には上の写真の正面側の天窓をそっくりコピーした位置に開けてあります。

さすがに1/80の食品サンプルをガチで作るのは厳しいので、「らしく」作るか、写真でも貼ろうかと思っています(^^;
よろしければ1クリックお願いします。
にほんブログ村