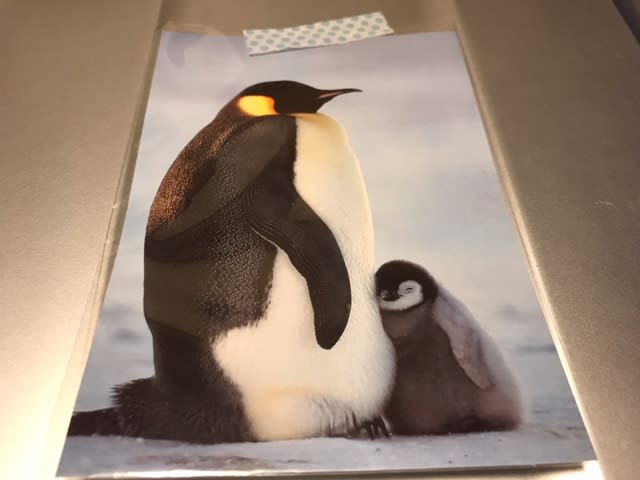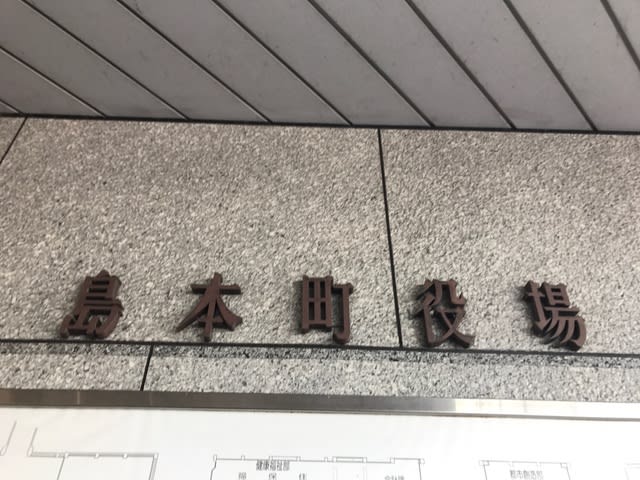新型コロナウイルス感染症の感染を懸念して突然学校が臨時休業となった去年の春、働く親とその子どもたちを支えたのは保育所と学童保育室でした。
国からの原則開所の要請を受けたものですが「密集」「密接」を避けることが極めて困難ななか、未知の感染症に向き合いながら子どもたちと過ごされたのは保育士、学童指導員。その多くが女性、あるいは若者です。
9月定例会議の一般質問では、このことを踏まえて、第4学童保育室を具体事例にして保育の環境、雇用の環境の改善を求めたいと思います。
子どもと家庭を支える学童保育室 ~ 第4学童室の課題と将来像 ~
第4学童保育室が現在の姿になるまでにはさまざまな経緯がありました。保護者OBのひとりとして、また議席を預かる者としてわたしなりに関心を寄せてきました。
今回の質問では、第4学童室の現在の課題を明らかにし、5年、10年先の将来像を描くことを求めます。
令和3年4月の入所登録数
第4学童室は1室増、合計5室となりました。まず、それぞれのクラスの登録人数を問います。*第4学童保育室は町内で最も大規模
施設規模と室長の配置
各学童室の登録人数を問い、第4学童室の規模で室長が一人というのは、かなり厳しい状況かと思い、どうお考えかと認識を問います。
指導員は、子どもの育ち、人権、守秘義務、保護者対応、あるいは休みがちな児童とその家族への心の寄せ方、万が一児童が怪我をしたときの対応など、実に、さまざまな知識やスキルを要します。
室長となればこれに組織管理能力も求められます。第4学童室の規模から考えて、室長という重責を担う次世代の人材が果たして確保できるのか、懸念しています。
将来利用者数の見込みと実態
今年度、学童室一クラスを増やさなければならなかったことを考えると、学童棟設置当時の将来利用者数の見込みと実際の数字の間には乖離があったと思えます。学童棟設置当時、数年後の200人を超える利用者数はわたし自身もまったく想定できていませんでした。
現状との乖離の要因が子育て世代の人口増なのか、女性の労働人口増なのか、そのあたりを分析して、迫りくる3小校区の課題(大型開発による児童数増)に向き合う必要があります。
保育基盤整備加速化方針に基づき、保育所の待機児童問題はまだまだ課題があるとはいえ飛躍的に改善しました。必然的に次は学童保育室に目を向けていかなければなりません。
さて、第4学童室は、5年、10年先の将来像を思うに、学童保育室をひとつに集約した保育環境が必要ではないかとも考えています。それには次のような理由があります。
ひとつは保健衛生上の課題を解決すること。新型コロナウイルス感染症を経験して、保健衛生上の課題があると思えてならないからです。
もうひとつは学校教育の35人学級に対応できる環境をつくること。すなわち校舎と学童棟のグランドデザインを描く必要はないかと考えました。*国は今年度から5年をかけて1学級あたりの上限人数を35人に引き下げることを決定
ヒアリングによると1もしくは2教室がさらに必要とのこと、学童保育室棟の設置を迫られるような事態にはならないようですが、引き続き、第4学童保育室の課題に心を寄せていきたいと思います。
*ご意見をお寄せください。
*匿名にてコメント欄へ←公表
画像
信楽焼のカエル親子です
阪急水無瀬駅前民藝のお店とらやまで
9月1日まで中高生の俳句募集中
こども俳句つくってみました
もこもこと綿あめみたい夏の雲
サンダルで川に入った冷たいな
暑すぎて昼寝してみた犬みたい
夏帽子姉とおそろい嬉しいな
かき氷シロップの色虹の色
ガリガリくん急いで食べる溶けそうだ
ほうし蝉宿題したかと鳴いている
どこからか聞こえてくるよ虫の声 靖子
国からの原則開所の要請を受けたものですが「密集」「密接」を避けることが極めて困難ななか、未知の感染症に向き合いながら子どもたちと過ごされたのは保育士、学童指導員。その多くが女性、あるいは若者です。
9月定例会議の一般質問では、このことを踏まえて、第4学童保育室を具体事例にして保育の環境、雇用の環境の改善を求めたいと思います。
子どもと家庭を支える学童保育室 ~ 第4学童室の課題と将来像 ~
第4学童保育室が現在の姿になるまでにはさまざまな経緯がありました。保護者OBのひとりとして、また議席を預かる者としてわたしなりに関心を寄せてきました。
今回の質問では、第4学童室の現在の課題を明らかにし、5年、10年先の将来像を描くことを求めます。
令和3年4月の入所登録数
第4学童室は1室増、合計5室となりました。まず、それぞれのクラスの登録人数を問います。*第4学童保育室は町内で最も大規模
施設規模と室長の配置
各学童室の登録人数を問い、第4学童室の規模で室長が一人というのは、かなり厳しい状況かと思い、どうお考えかと認識を問います。
指導員は、子どもの育ち、人権、守秘義務、保護者対応、あるいは休みがちな児童とその家族への心の寄せ方、万が一児童が怪我をしたときの対応など、実に、さまざまな知識やスキルを要します。
室長となればこれに組織管理能力も求められます。第4学童室の規模から考えて、室長という重責を担う次世代の人材が果たして確保できるのか、懸念しています。
将来利用者数の見込みと実態
今年度、学童室一クラスを増やさなければならなかったことを考えると、学童棟設置当時の将来利用者数の見込みと実際の数字の間には乖離があったと思えます。学童棟設置当時、数年後の200人を超える利用者数はわたし自身もまったく想定できていませんでした。
現状との乖離の要因が子育て世代の人口増なのか、女性の労働人口増なのか、そのあたりを分析して、迫りくる3小校区の課題(大型開発による児童数増)に向き合う必要があります。
保育基盤整備加速化方針に基づき、保育所の待機児童問題はまだまだ課題があるとはいえ飛躍的に改善しました。必然的に次は学童保育室に目を向けていかなければなりません。
さて、第4学童室は、5年、10年先の将来像を思うに、学童保育室をひとつに集約した保育環境が必要ではないかとも考えています。それには次のような理由があります。
ひとつは保健衛生上の課題を解決すること。新型コロナウイルス感染症を経験して、保健衛生上の課題があると思えてならないからです。
もうひとつは学校教育の35人学級に対応できる環境をつくること。すなわち校舎と学童棟のグランドデザインを描く必要はないかと考えました。*国は今年度から5年をかけて1学級あたりの上限人数を35人に引き下げることを決定
ヒアリングによると1もしくは2教室がさらに必要とのこと、学童保育室棟の設置を迫られるような事態にはならないようですが、引き続き、第4学童保育室の課題に心を寄せていきたいと思います。
*ご意見をお寄せください。
*匿名にてコメント欄へ←公表
画像
信楽焼のカエル親子です
阪急水無瀬駅前民藝のお店とらやまで
9月1日まで中高生の俳句募集中
こども俳句つくってみました
もこもこと綿あめみたい夏の雲
サンダルで川に入った冷たいな
暑すぎて昼寝してみた犬みたい
夏帽子姉とおそろい嬉しいな
かき氷シロップの色虹の色
ガリガリくん急いで食べる溶けそうだ
ほうし蝉宿題したかと鳴いている
どこからか聞こえてくるよ虫の声 靖子