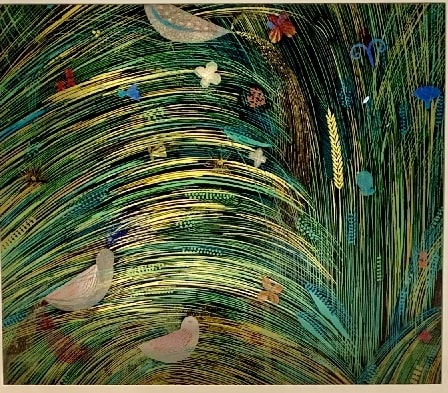20220410
ぽかぽか春庭シネマパラダイス>2022シネマ春(1)最後の決闘裁判
2021年10月に公開された英米合作映画。日米同時公開。飯田橋ギンレイホールで3月13日に鑑賞。
歴史上の出来事をもとにした映画ですが、14世紀の出来事の全容がわかる確かな資料は不足しており、歴史学者の研究でも諸説ある、といういわくつきの史実です。
監督:リドリー・スコット
脚本:ニコール・ホロフセナー、マット・デイモン、ベン・アフレック
原作:エリック・ジェイガー(『決闘裁判 世界を変えた法廷スキャンダル』)
出演:マルグリット:ジョディ・カマー
ジャン・ド・カルージュ:マット・デイモン
ジャック・ル・グリ:アダム・ドライバー
ピエール伯:ベン・アフレック
エリック・ジェイガーの原作
1386年のフランス王国のパリにおける最後の決闘裁判の顛末をエリック・ジェイガーが、ノンフィクション『決闘裁判 世界を変えた法廷スキャンダル』として執筆し、それを基に、今回の映画では、出演者でもあるベン・アフレックとマット・デイモンが脚本を執筆。ふたりに加えて、ニコール・ホロフセナーが「女性側の視点で」という第3の脚本執筆を担当しています。
3人の登場人物が同じ出来事を語る、というと、黒澤明の『羅生門』その原作の芥川龍之介『藪の中』を思い浮かべます。
実際、マットデイモンがリドリースコットに監督の依頼をしたときスコット監督は、「(デイモンは)とりつかれたように『羅生門』の話をしていたよ。私は一つの行為が登場人物3人の視点で、それぞれ描かれるというポイントに惹きつけられたんだ」と脚本本の面白さにひかれて監督を引き受けたことを述べています。
もとになった史実とは、騎士ジャン・ド・カルージュがイギリスに出征している留守の間に、ジャンの旧友従騎士ジャック・ル・グリがジャンの妻マルグリット を強姦したという事件の裁判のいきさつについて。
決闘裁判というのは、双方の言い分をさばき切れない場合、神に裁きをゆだねて、双方が決闘をする、という決着のつけ方。どちらかが死に至るまで戦い続け、勝ったほうが神に正義と認められ、負けたほうが不正義。さすがにこの決着のつけ方は問題は大きく、1386年のこの決闘を最後に、こんなやり方はなくなったのです。この裁判が「最後の決闘裁判」となりました。
監督リドリー・スコット(1937~ )80歳過ぎての作品であるというだけでも「すごい!」と見たくなるけれど、なにより脚本の「ジャン、ジャック、マルグリットの3人がひとつの出来事を語る」というのを知ると、あらら、黒澤明の『羅生門』か、芥川龍之介の『藪の中』か、と興味津々になります。
女性は「人権ゼロ。男性の所有物同然」の存在だった中世ですから、史実の記録では、マルグリット視点の記録などはどこにもありません。ニコール・ホロフセナーが女性の側から裁判を描いた、というところがこの映画のキモでしょう。
マルグリットを強姦したル・グりは「貴婦人だから嫌がるふりをしてはいたが、この行為は双方合意の上のものだった。よって自分は無罪」と主張し、ル・グりが使えている領主ピエール伯もお気に入りの臣下の味方をするし、神職をめざしていたル・グりに教会関係者も肩入れする。
どこまでもル・グりの処罰を望むカルージュは、もし自分が決闘で負けた場合、妻のマルグリットも「偽証」の罪になり生きたまま火あぶりの刑になるということを知りながら、決闘に臨みます。
同じ出来事をカルージュ視点とル・グり視点からの事実が述べられたあと、マルグリット視点の「真実その3」が語られる。
夫と、夫の友人で強姦者のル・グりのどちらも、マルグリットを尊重し愛したとは思えない。夫の行為は初夜のときから一方的で妻の身体を尊重しているようには見えないし、ル・グりが「いやがるふりをしているけれど、本当はしたがっていたはずだ」と考えて行った行為も、マルグリットを歓喜に導くようなやり方ではなかったように見えた。ベッドに追い詰めたあげくの一方的バック!
あのような一方的行為を行って「いやがっているふりをしているけれど、女はほんとはやりたがっていたのだから、自分は無実」と最後の最後まで信じているル・グりも、「神学は学んだけれど、女性についてはなにも知らない大バカ者」だと思うし、女を知らないという点では中世の男たちはみな、「本当の喜び」を知らなかったのだろうなあと思います。
マルグリットは裁判の場で、「夫との行為に喜びがあったか」と問い詰められます。中世の考え方ってよくわからないのですが、映画の中で語られていたのは「女性が絶頂に達すれば妊娠する」というのです。子を授からないでいたマルグリットは「夫との行為に喜びはあったが、絶頂に導かれてはいない」と答えています。へぇ、そうなんだ。絶頂にいかないと妊娠しないって、ほんとにみんな信じていたのかな。
もうひとつ、中世のヨーロッパ女性の人生で重要なこと。女性には法的に不動産相続権が与えられていなかった、ということ。ヨーロッパ周辺国すなわちイギリス、スペイン、スエーデンには女性の不動産相続権王権相続権があったので、エリザベス一世のような女王も存在できたけれど、フランスの女性は不動産相続権も王権相続権もなかったのです。
そのため、マルグリットは、父親が「持参金」として持たせてくれた不動産も、一部は領主のピエールに簒奪され、残りは夫が所有権を持ちました。
カルージュの母親は、ジャックの父カルージュ3世亡きあと地方長官の職を世襲できなかった息子を不憫に思い、無一文だった息子にいくぶんかの不動産を与えることになった持参金付きの嫁マルグリットをよく思っていません。息子のいるところでは露骨な嫁いびりをしませんが、嫁にあたたかい視線を寄せることはしません。
マルグリットは、夫がイギリスへ遠征している間、領地を管理し税収もきちんと確保する賢い嫁でした。武辺一方で無学なカルージュにはすぎた嫁だったわけですが、姑にとっては「まだ世継ぎも生んでいない嫁」でした。
強姦されたと夫に訴えた嫁に、姑は「私も若いころ強姦されたことがあったが、それはだれにも話さなかった」と語り、決闘することになってしまった息子を案じて嫁を責めます。おそらく、多くの女性がつらい経験をしたあと、口をつぐまざるをえなかったのだろうと思います。強姦の場にだれもおらず、真実を証明する方法は何もないのですから。
姑は、嫁が襲われる原因を作ったのは、自分自身であったことなど、かけらも反省していません。 ジャンが言い残した「マルグリットをひとりにするな、必ずメイドをそばに置け」という言いつけを守らず、自分の用足しのためにメイドをみな連れて外出したために事件が起きたことを考えずに、息子を決闘の危険にさらした嫁に冷たく当たります。
1386年のこの裁判のあと、妻を残して遠方へ出征しなければならなかった夫はどうやって妻の貞操を守ることにしたか。十字軍のころ、妻の腰に「貞操帯」をはめ込み、夫が鍵を外さない限り、排尿はできるが男との交渉はできない、という装置を考え出したのです。
マルグリットは「夫が負けたらおまえは生きながら火あぶりになる」と聞かされても、自分の主張を変えることをしませんでした。夫の勝ちを信じていたから?いいえ、夫が勝とうがル・グりが勝とうが、「女性の尊厳」を考えてくれる者がいないことを知り尽くしたうえでの主張だっただろうと思います。そうでなければ姑やその他の女性たちがしたように「口をつぐむのがいちばん賢い方法」とわかっていたでしょう。
マルグリットは、女性を「自分の所有物・奴隷や家畜と同じ存在」としか見ない男社会に敢然と「女も、男と同じ尊厳を持つ人間」という主張をしたのだと思います。
現在でもなお、レイプ事件で「女にもスキがあったのだ」「そんなに嫌だったのなら抵抗できたのではないか」などの言説が裁判でも報道でもまかり通っています。
#Metoo時代になってもまだ、女性が声をあげるには厳しい世の中です。脚本家と監督は、現代においても、女性が強姦された場合の世間の取り扱いかたを知ったうえで、この映画を作り上げたことでしょう。
153分という上映時間が「長すぎた」という感想もあったようです。3人の語る事実の同一部分をはしょれば、もう少し短くなったかもしれないけれど、同じ部分でも視点が異なれば違う見方になるのだ、ということを表現するには、この繰り返しも必要だったと思います。
興行ではリドリー・スコット監督の作品の中で最低になった、という今作を、私は高く評価したいと思います。
じゃんじゃか兵士が死んでいく戦闘シーンは、『乱』よりすごかったし、騎士と従騎士の馬上一騎討ちの決闘シーンも迫力あり、最後まで「どっちが勝つ?」とはらはらしました。
ただし、敗者の最後がどうなったか、の描写はえぐい。目をそらさず見たけど。
マルグリットの生涯を語るラストナレーション、記録が残されているのだろうか。
美術が秀逸。ちょうど電車読書で紅山雪夫『ヨーロッパものしり紀行・城と中世都市』を読んでいた最中で中世の建築に詳しくなっていたので、画面のすみずみまで、中世都市や城のようすが再現されていてその面でも楽しめました。
「映画を見る楽しみ」をおおいに味わうことができました。2021年10月公開の映画を2022年3月にもう見ることができて、飯田橋ギンレイの買い付け力、いいと思います。
<つづく>