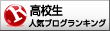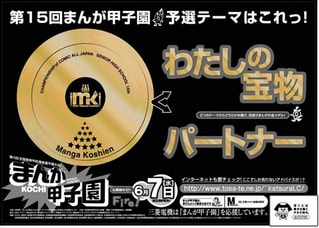高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!
みなさん、今日(4日)は、「東京・浅草の鷲(おおとり)神社」で「酉の市」が催される、「一の酉」です。

酉の市(とりのいち)は、例年11月の酉の日に行われ、各地の鷲神社(おおとりじんじゃ)の祭礼です。古くは酉の祭(とりのまち)と呼ばれ、大酉祭、お酉様とも呼ばれていました。酉の市で縁起物を買う風習は、関東地方特有の年中行事です。
今日は、酉の日である「一の酉」に開催される例祭で、 境内では様々な縁起物が売られます。その中で最も有名なのが、開運招福や商売繁盛を願った「飾り熊手」。「運をかき込む」「福をさらう」という洒落を利かせた縁起物です。
平成18年酉の市は
11月 4日(土)「一の酉」
11月16日(木)「二の酉」
11月28日(火)「三の酉」
(注)三の酉
「酉の日」は、毎日に十干十二支を当てて定める日付け法で、「酉」に当たる日のこと。これは、12日おきに巡ってくる。ひと月は30日なので、日の巡り合わせにより、11月の酉の日は2回の年と3回の年がある。初酉を「一の酉」、次を「二の酉」、3番目を「三の酉」と言う。「三の酉」まである年は火事が多いとの俗説があり、その年の11月から歳末にかけて、社会一般で火事に気をつけることがよく言われる。
飾り熊手が誕生したのは江戸時代。
それまで鷲神社の酉の市は、農作物や農具を販売する普通の市だったんですが、酉(とり)を「取り込む」にかけて参拝する人が急増し、その結果、農具として売られていた熊手が、次第に縁起物へと変身していったのです。
関東では飾り熊手=酉の市ですが、関西で飾り熊手といえば「商売繁盛で笹持って来い」の福笹で有名な十日戎(えびす)です。
関東では飾り熊手を完成品で売っているのに対し、関西では熊手も福笹も、本体と招福物(飾り物)を別々に購入して仕上げるオーダーメイドスタイルが基本です。
ところで、飾り熊手を飾る招福物のひとつに、お福(お多福、おか目)の面があります。このお福の面、2種類あるって知ってますか?
普通に見かけるのが、濃い眉に白い歯の「娘タイプお福」。で、数の少ないレアモノが、眉を剃ったお歯黒の「人妻タイプお福」です。
近くに住んでいる受験生は、是非「合格祈願」をしてきましょう・・・・・


みなさん、今日(4日)は、「東京・浅草の鷲(おおとり)神社」で「酉の市」が催される、「一の酉」です。

酉の市(とりのいち)は、例年11月の酉の日に行われ、各地の鷲神社(おおとりじんじゃ)の祭礼です。古くは酉の祭(とりのまち)と呼ばれ、大酉祭、お酉様とも呼ばれていました。酉の市で縁起物を買う風習は、関東地方特有の年中行事です。
今日は、酉の日である「一の酉」に開催される例祭で、 境内では様々な縁起物が売られます。その中で最も有名なのが、開運招福や商売繁盛を願った「飾り熊手」。「運をかき込む」「福をさらう」という洒落を利かせた縁起物です。
平成18年酉の市は
11月 4日(土)「一の酉」
11月16日(木)「二の酉」
11月28日(火)「三の酉」
(注)三の酉
「酉の日」は、毎日に十干十二支を当てて定める日付け法で、「酉」に当たる日のこと。これは、12日おきに巡ってくる。ひと月は30日なので、日の巡り合わせにより、11月の酉の日は2回の年と3回の年がある。初酉を「一の酉」、次を「二の酉」、3番目を「三の酉」と言う。「三の酉」まである年は火事が多いとの俗説があり、その年の11月から歳末にかけて、社会一般で火事に気をつけることがよく言われる。
飾り熊手が誕生したのは江戸時代。
それまで鷲神社の酉の市は、農作物や農具を販売する普通の市だったんですが、酉(とり)を「取り込む」にかけて参拝する人が急増し、その結果、農具として売られていた熊手が、次第に縁起物へと変身していったのです。
関東では飾り熊手=酉の市ですが、関西で飾り熊手といえば「商売繁盛で笹持って来い」の福笹で有名な十日戎(えびす)です。
関東では飾り熊手を完成品で売っているのに対し、関西では熊手も福笹も、本体と招福物(飾り物)を別々に購入して仕上げるオーダーメイドスタイルが基本です。
ところで、飾り熊手を飾る招福物のひとつに、お福(お多福、おか目)の面があります。このお福の面、2種類あるって知ってますか?
普通に見かけるのが、濃い眉に白い歯の「娘タイプお福」。で、数の少ないレアモノが、眉を剃ったお歯黒の「人妻タイプお福」です。
近くに住んでいる受験生は、是非「合格祈願」をしてきましょう・・・・・