7月7日、嶋田と一緒に浅間・吾妻エコツーリズム協会
http://ecotourism.or.jp/のツアーに参加し、浅間山を歩いてきました。
コースはガイドの赤木さんおすすめの黒斑山(浅間山を構成する3つの山のうちのひとつ)。
およそ2万5千年前に山が崩れ、そのときできた半円状の絶壁が、今も時々噴火する“前掛山”をとりかこんでいます。
登り始めは濃い霧が立ちこめていました。(どうか晴れますように…)

大昔の噴火で降ってきた溶岩の上に、根をのばす木々。
こういう景色を見ると「おお!火山だ~!!」とワクワクしてきます。
断層で山が崩れたために下が絶壁になっているという“トーミ断層”まで登ってきました。

しかし霧で下の景色は何も見えません。(高いところは苦手だからちょうど良いかも・笑)
赤木さんが地面に絵を描いて、どういう経過で山が崩れて現在の形になったのか、わかりやすく説明してくれます。

なるほど地面に絵を描くって方法、良いですね!浅間山は大島火山よりずっと古くて、溶岩がくだけて細かい状態になっているから絵が描けるんですよね。便利でいいな~。
登山道の所々で、薄い瓦のような割れ方をした溶岩が折り重なっています。

黒くてゴツゴツの溶岩がほとんどの大島ではこういう形の溶岩を見ることはまずないので、すごく不思議なものを見ているような気持ちになります。
「うわ~、すごい!こんなの大島では見られないですよ!」と興奮する私。
「う~ん、そうか…。」と、これまた不思議なもの(人?)を見ているような赤木さん。(笑)
登山道にはかわいい高山植物が咲いていて、ついつい足を止めてしまいます。
印象に残ったのは、葉が5枚以上にならないと花をつけないというゴゼンタチバナ。

確かに、4枚葉には花がありませんね。
「この花を見ると、夏が来たんだって思うんですよね。」と赤木さんが語っていたハクサンイチゲ。

2週間ほどが花の時期だそうですが、満開でした。
旬の花に会えて、うれしかったです。
赤い胞子をつけた地衣類。

数mmの大きさですが、暗い森の中で鮮やかな色が目を引きました。
「目を引いた」といえば、思わず足を止めてしまったのがカラマツ(たぶん)の大木です。
大きく張り出した枝が、堂々としていてすごく威厳がありました。

枝が垂れ下がっているのは、雪の重みのためらしいです。
いったい何回ぐらい、雪におおわれる冬を過ごしてきたのでしょうか?
こんなふうに様々な風景を楽しみながら、かなりゆっくりなペースで登っていきました。
斜面は時々、急になります。

ハアハア…
息を切らしながら登って、ついに山の稜線につきました!
が、霧で下まで見えません(汗)

「下まで見えたらダイナミックなんだろうな~」と想像できる景色はたくさんあるのですが…。
黒斑山山頂で休憩しながら、霧のむこうに山の姿を思い描きました。

(晴れていれば赤木さんの指差す方向に、現在活動中の前掛山が見えるはずです)
休憩後、再び出発。
木に囲まれた山の稜線は風が当たりませんが、水たまりが多い…

「このあたり、火山灰が降ったから水はけが悪いんですかね?」by私。
「いえ、たぶん踏み固めれているからだと思いますよ。」by赤木さん。
三原山火口一周コースはガラガラで、絶対水たまりなどできないのに比べて、ずいぶん様子が違います。まあ、当たり前かぁ。黒斑山は2万5千年前まで活動していた火山、25年前に噴火した大島との古さの差は“1000倍”ですものね。
さて、草地を抜け…

ガレ場を抜け、Uターン地点へ近づいてきました。

「今日はもう、霧は晴れないのかな?」とあきらめかけた、まさにその時です。
突然目の前の霧が晴れて一番底まで見渡せました!

吸い込まれるような崖の底には、鮮やかな緑の森と草原が広がっています。
浅間山の、あまりにも粋な計らいに感動しました~(涙)
見てください!この景色。

浅間山、大きすぎます!
霧が晴れたのはこの一瞬だけで、あたりはあっという間にまた真っ白になってしまいました。
でも赤木さんの説明で、十分火山の大きさを想像することができました。

「この岩に平行に走るヒビの延長に、黒斑山の火口があったと言われているんです。
何しろ浅間山は1000年で1000m成長する火山と言われているんですよ。」
そ、そんなに大量の溶岩を噴き出す火山なんですね。
計算してみたら(大島は約2万年で1000m)、大島の約20倍の溶岩を噴き出す火山ということになります。ヒエ~。
“蛇骨岳”でランチをとりながら、再び霧が晴れるのを待つことにしました。

「空は明るくなって来たんだけどね~。」byみんな。
スタッフの女性が“高原キャベツ”を持って来てくれました。
火山灰大地で育つこの地域のキャベツは、おいしいのだそうです。

軽く塩をふったパリパリキャベツ、確かにとてもおいしかったです!
心配り、ありがとうございました~。
食後もしばらく粘りましたが、ついに霧は晴れませんでした。でも赤木さんが熊と遭遇した話や民話を聞かせてくれたので、楽しい時間を過ごすことができました。

「この下の斜面から熊の親子があがって来たんですよ。むこうも稜線を超えて斜面をおりようとして降りられなくて慌てたんでしょうね。あれから必ず熊用のスプレーを持ち歩くようになりましたよ。」
実際に熊と遭遇した現場でリアルに再現される話とともに、富士山と浅間山を題材にした民話を、昔の火山の上で溶岩に座って聞く…というシチュエーションも、とても良かったです。

「ガイドの存在って偉大だわ」と思った瞬間でした!
さて、帰路は森を抜けるコースへ。
黒斑山の北側斜面には、広い範囲にシラビソの純林が存在するとのこと。
森に入ったら、まるで大島の樹海のように、木の幹だけの森が続いていました。

あまり太い木はなく、細いまま倒れて世代交代しているようです。
なぜ、他の樹木が生えないのか?とても不思議だとのこと…。
シラビソたちに「なぜ?」と、問いかけてみましたが…

無言のまま、空に向かってのびていました(笑)。
下るにつれ少しずつ、木の種類が増え明るくなってきました。

数万年前の溶岩の隙間に生きる“ヒカリゴケ”を見たり…
何重もの薄い樹皮が雪で折れた幹を支えることで再生し、標高の高い雪の多い場所で生きることができるダケカンバの皮の仕組みを観察したり

幹の匂いを嗅いだり、“森”を楽しみながら下山しました。
浅間山の全貌は結局最後まで見ることができませんでしたが、とても楽しかったです。
どんなによくできたパンフレットや看板でも、ガイドにはかなわないのではないかと思いました。
特にガイドがその土地に対して感じている“思い”や、ガイド個人のフィールドでの経験を知ることができるのは、ガイドツアーならではの楽しみです。
糸魚川でも感じたことですが、パンフレットや看板は受け身だから読まなくても良いわけで、よほど興味があるか、先へ先へと読み進みたくなる面白いストーリーがないと、なかなか頭に入りません。
でも、ガイドと言葉のキャッチボールをする中で、知ったり感じたりしたことというのは、楽しい思い出とともにずっと心に残りそうです。
こんなふうに感じるのは、今回案内してくれたのが知識も経験もある素敵なガイドさんだったからでしょうけれど。
そして今回、浅間山という火山(の一部)を歩いたことで、大島は“若くて小さな火山の島”なんだということをいっそう強く感じました。
浅間山は大きすぎて、1日歩いても同じ年代の溶岩を歩いて抜けるのは大変なのだそうで、それだけでも大島とケタが違います。
ダイナミックさでは大きな火山にかないませんが“小さい”ということは、一つの個性だとも感じました。
小さいがゆえに、年代の違う噴火がつくった様々な環境を、短時間のうちに楽しめます。
そして海の波とのせめぎ合いが作り出す景色も、楽しめます。
これからも時々他の火山を歩いて、伊豆大島火山の個性や魅力を探していきたいです。
(カナ)











































































































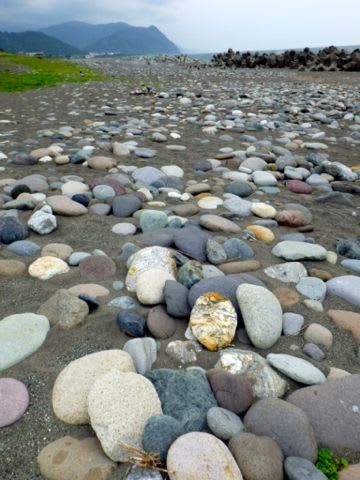

















 慰霊堂外観です
慰霊堂外観です 公園内にはこんな池もあります。
公園内にはこんな池もあります。
 公園の外では道路脇の植栽の整備をするやさしいボランティアの方を見かけました。
公園の外では道路脇の植栽の整備をするやさしいボランティアの方を見かけました。









