
今回の入院中の読書に、図書館から借りた3冊、J.K.ガルブレイスの『ガルブレイスの大恐慌』(徳間文庫)、 宇野重規の『西洋政治思想史』(有斐閣アルマ)、岡山裕の『アメリカの政党政治』(中公新書)を私は持ち込んだ。
『ガルブレイスの大恐慌』は思っていた内容と違い、結局は『西洋政治思想史』を、入院中、一番読んだ。
私は1930年代のアメリカの大恐慌の全体像とルーズヴェルト政権の対応について詳しく知りたい。ガルブレイスは株式市場の狂乱に記述を絞っている。大恐慌は株式市場のバブルの破裂だけでないはずだ。
農業市場の不況は、株の大暴落の前から始まっていたと、どこかで読んだ記憶がある。株価の暴落は確かに小市民の資産を奪ったが、それだけでなく、製造業全体が需要不足の大不況に落ち込み、失業者が町にあふれたはずだ。失業率はどれだけだったのか知りたい。失業者はどうやって餓死しないで済んだのだろうか。ルーズヴェルト政権はどのような対策を打ったのだろうか。どうして、世界の貿易は縮小していったのだろうか。政権はそれをどう考え、どう対応したのだろうか。
『ガルブレイスの大恐慌』でわかったことは、資産を失った小市民が次々と飛び降り自殺したというのは、都市伝説にすぎないということだ。エンパイア・ステート・ビルディングの屋上に飛び降り自殺の人がいると、見物客が集まったら、それは単にビルのメンテナンスだったという、エピソードが書かれている。大恐慌の中で意外とみんな逞しく生きていたようである。
日本の1991年の株不動産バブル崩壊でも資産を失ったからといっても、格別自殺者が増えたわけではない。日本のバブル崩壊はどちらかというと大企業や銀行を傷つけた。日本の大企業や銀行の経営者たちはバカの集まりだったからである。自民党は、経済刺激のため赤字国債をつぎつぎと発行し、バブル崩壊を乗り切ろうとしたが、それが適切な対応だったか、経済学者たちの本音を知りたい。
今回のトランプ大統領の「相互関税」の発動によって、世界的株の暴落が起きているが、経済が縮小再生産にならないためには、各国が関税戦争に持ちこまないことだと思う。ヨーロッパの各国の対応をみても、トランプの関税政策を口先で非難しているが、関税戦争を控えている。トランプの相互関税の値自体は恣意的である。しかし、トランプ大統領の相互関税発動をアメリカの悲鳴として捉え、新たな世界均衡に慎重にランディングすべきである。メディアの冷静な対応を望む。
以上の思いがあるので、1930年代のアメリカの大恐慌の全体像とルーズヴェルト政権の対応について私は詳しく知りたい。











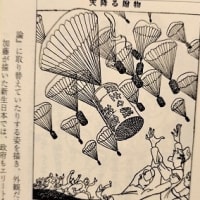

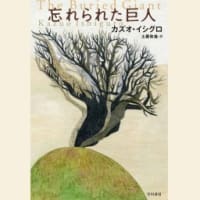






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます