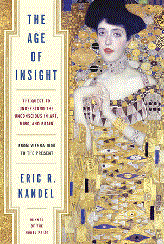
予約していたエリック・R・カンデルの『芸術・無意識・脳』(九夏社)を受け取りに、きょう図書館に行って、驚いた。分厚いのである。薄いエッセイだと思っていたのに、厚さ4センチもある。
著者は、軟体動物アメフラシを使って、記憶とは何かを明らかにした、ノーベル生理学賞受賞の神経学者である。本書を2012年3月にRandom Houseから出版したとき、すでに、82歳であった。この厚い本を書くとは、すごい気力だと思う。
原題は“The Age of Insight”、副題は“The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present”である。
日本語版の副題に「世紀末ウィーンから現代まで」とあるが、「世紀末」とまったく違う「文化的な輝かしい」ウィーンが、本書で描かれる。
著者は「謝辞」で次のように書く。
<私は、第一次世界大戦の敗北に続くハプスブルグ帝国の崩壊から11年後の1929年11月7日、ウィーンで生まれた。オーストリアの領土と政治的影響力は大きく減少したものの、私が若い時代を過ごした首都ウィーンは、まだ世界の文化の中心地の1つであった。>
これが、著者が、副題を「1900年のウィーンから」とした理由である。ただし、実際には19世紀半ばから書き始まる。
19世紀のハプスブルグ帝国は、野蛮で暴力的な「国民国家」に囲まれ、後退する中で、皇帝は中産階級とともに、文化に力をいれた、という。
1844年に、カール・フォン・ロキタンスキーがウィーン大学の医学部長に就任し、「ヒトは他の動物と同様、生物学的に理解されなければならない」と、モダニズムの考えを導入したという。
カンデルはモダニズムを「人間の合理的な行動を重視した18世紀ヨーロッパの”啓蒙思想”への反動」という。ウィーンのモダニズムの特徴は「人の精神はその多くの部分が感情・情動という新しい視点」「自己考察」「学問の融合・統一」だとする。
これが、クリムトやシーレの芸術、フロイトの精神分析を生んだとする。実際、フロイトはウィーン大学医学部に属し、神経科学を研究した。クリムトやシーレもロキタンスキーの「ヒトの生物学的理解」の影響を受けていたという。
1900年のウィーンの文化的空気のなかで、クリムト、シーレ、フロイトは、「理性的人間」の像を打ち破る、ありのままの人間を見出したのだ。日本における「世紀末のウィーン」のイメージ、「世紀末=病的」と大きく異なる。
この分厚い本書を2週間で読めるか、「ヒトのこころの生物学的理解」までたどりつけるか、とっても不安であるが、とても面白そうな本である。









