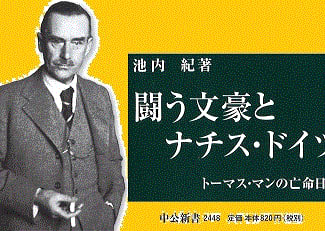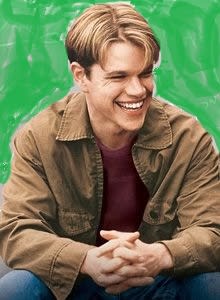
Max Weberは知の巨人ではない。クソである。単なる権威主義者であり、差別主義者であり、闘争的な保守言論人である。彼をヨイショする人がいるとは、社会学のいかがわしさを裏づける。
Weberが信じる「進歩」に誤りがある。「進歩」という幻想は、弱者が「明日はよくなる」という希望をもち、現在の苦痛に耐えつづけるために、多少は役立つかもしれない。しかし、Weberは「進歩」を「強者の台頭と弱者の退出による社会進化」ととらえる。そうすると、現在の体制を支持する言論人はつねに「進歩」的知識人となる。
時間とともに起きていることは、「進歩」ではなく、「多様化」である。言語というものを通して、過去の人の体験や思いを、人は追体験できる。したがって、人は、この多様な思想のなかから、1つ選択し、あるいは、切り貼りして自分の思想を形づくることができる。しかし、嗅覚がすぐれていなければ、多様性のなかに埋没し、自分を見失う。
Weberは「求道者」ではない。彼のいうキリスト教は捏造である。彼はカトリックやプロテスタントを貶めるために悪口を言っているだけである。彼は、母ヘレーネのように弱者に心を寄せていない。資本主義を持ち上げするために、自分のブルジョア性を無罪放免するために、厳格なカルヴァニズムのAskeseを資本主義の精神とみなしているだけである。
大塚が “Askese”を禁欲と訳したが、日本語の「禁欲」に対応するドイツ語は “Abstinenz”である。Weberは“Askese”を「自己鍛錬」という意味でもちいている。
金儲けに一心不乱になることを“Askese”と解釈するのは、Weberが「進歩」を社会的淘汰と考えるからである。これを正当化するために、“Beruf”に「職業」という意味とともに「召命」という意味があるなどと、クソみたいことを言っている。これを真に受ける大塚の信仰はなんなのか。
上級市民は資本家として一心不乱に金儲けに専念し、優秀な労働者は雇われて工場の幹部として一心不乱に働き、ベルトコンベアーについていけない劣等者は通りに捨てろ、というWeberの理想とする資本主義社会は、キリスト教徒にとって受け入れられるものではない。
キリスト教は、人々を救うことを目指していたはずである。生まれる前に救われる人と救われない人が神によって定まっている(予定説)なら、救済宗教ではないではないか。救いを求めて、キリスト教の扉をたたくことが意味なくなるのではないか。この予定説で満足するのは、ブルジョアに生まれたことを正当化できる上級市民だけでないか。
Weberは救いを求めてキリスト教の扉をたたいていない。Weberは各教派を比較して悪口を言っているだけである。
キリスト教をドグマや神学で理解することがそもそも間違っている。ドグマや神学は、ちょっと頭のまわる悪人が自己正当化のためにでっちあげたもので、多数のキリスト教徒はそれと無縁に暮らしてきた。カルヴァンもルターも極悪人である。
厳格なカルヴァン派は他の教派よりサクラメント(儀礼)を排除する、すなわち、脱呪術(Entzauberung)だから、近代的であるとWeberは言う。じつは、サクラメントをカルヴァン派より拒否する教派もあるが、Weberは熱狂的だからなどといって、劣るという。おかしくないか。
だいたい、三位一体を信じるのはまだ魔法にかかっているのではないか、神を信じるのは魔法にかかっているのではないか。Weberの母ヘレーネがチャニングの書読んでいたが、チャニングはユニテリアンである。イエス・キリストを人とするユニテリアンの方が魔法が解けているのではないか。イエスを人とし、神を否定する聖書研究者の田川建三のほうがもっと魔法が解けているのではないか。
Weberを「求道者」という大塚久雄に遠慮しすぎである。Weberは単なる権威主義者であり、差別主義者であり、闘争的な保守言論人である。