
男たちの週末。
向かい合わせ、難しげな幾何学と格闘するふたり・・・
片や、こんなやつ・・・
今一方は、こんなやつ・・・
なぞ・・・
ようかん・・・?
無言・・・
ひたすら手を動かす・・・
片方は完成したようだ。
こちらはまだまだ組み立て作業中。
うむむ・・・
なるほど・・・
女子のような「わいわい」「キャッキャ」はないが、わりと楽しいようだ。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

笠地蔵さまではなく、ほんとのお地蔵さま方です。
ありがたや・・・
仏師さまとなられた山本さんの作品です。
販売による売り上げで、ラオスに小学校を建てようという試みを進めてます。
日本各地にお出向きくだされ、お地蔵さま軍団〜。
こちらはまったく関係なく、黒田女史のフクロウ箸置き。
腕組みをして難しい顔・・・
哲学してる五賢人、って感じです。
こちらもまったく関係なしの、佐藤(直)さんの古民家。
大傑作であるこの子が、工房にお嫁入りしました。
いやー、どの角度から見てもかっこええわー。
森魚コレクションも充実してきました。
みんながワクチンを射ち終えたら、また工房展をしたいですね(来春かな?)。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

またも笠地蔵さまがきてくだすった〜。
朝早くにゴミ出しに出ると、そこには一個のおそなえものが・・・
本日はキャベツであったぞ、みなの衆〜。
きゃほーい! 
いつものやつを、と思ってズンドウに入れてみれば、収まらぬほどの見事さじゃったんだそうな。
4分の3〜。
むだにかっこいい落としブタ、出動〜。
味はほんだしと昆布醤油〜。
まるまるくたくた煮〜。
素材の美味しさまるごと、むさぼり食うたるでえ〜。
ふたりがかりだと、たちまちなくなる〜。
収穫中の畑に手を合わせ、なむなむ・・・
都心よりも、人里よりも尊い、畑の真ん中暮らしじゃ。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

ほのかちゃんです。
雲形定規を手に入れたので、これを使って模様かき。
ふむー、波打つ海のラインを引いたと思ったら、もう定規には飽きたらしく、雲はフリーハンド。
まあね、その方が生きた線がかけます。
そこにカモメを飛ばしますか、さすが。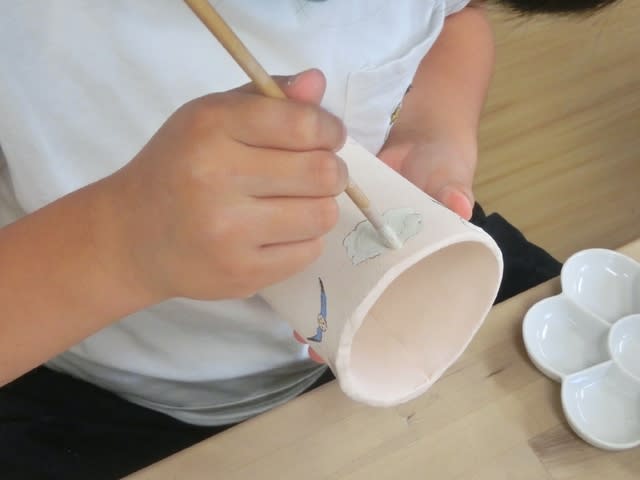
色つけは、釉薬を筆ぬり。
さすがはわかってらっしゃる。
これが熱による化学変化で空色&濃紺の風景になるんだから、不思議なもんだよねえ。
カモメのアクセントが秀逸。
しっかりとお菓子をせしめて、うっしっし。
はやく大きなマグで牛乳が飲みたいわあ。
吹奏楽部のチューバを軽々と持てるように、もっと大きくなれ〜。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園
ここんとこのいろいろ。
東京地方は梅雨入りですね。
飯田さんのマスクチャームは、レジンで一日がかりでつくった雨傘。
雨の日も楽しく過ごせます。
小雨そぼ降る中、小庭のピンク小バラが満開中。
見にきてね。
工房内にも、ナチュラル色のバラ。
潤います。
フラワーショップ「アートルーム」さんは、いいお花を置いてますよ。
こちら、テトラなんとか・・・というユーカリ。
四角い実?花?が面白くて、手に入れました。
風通しのいい場所で、ドライに。
じゃんじゃん咲いていく、デルフィニウム。
奥様たちに人気の、なごみ系。

晴れ間には、素焼き鉢を洗って乾燥。
こうして宇宙からの通信を待ちます。
晴れてるうちに、すかさずお外へゴー!
「酒は飲むな」という、小池さんのいじわる看板が出てるので、アセロラドリンクのスパークリング割り。
「このspaceは、ぼくひとりで過ごすには広すぎる」という言葉を思い出します。
カール・セーガン博士が、宇宙人はいるか?と聞かれて答えた言葉です。
地球人よ、おまえたちはひとりではない。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

心ウキウキ、本焼きの窯出しです。
こんなに楽しい仕事をさせてもらって、どうもすみません。
ご一緒にごらんくださいな。
まったくとりとめのない方向性の作風群です。
この散らかりようが、森魚工房のいいところ。
みんなの心の旅の帰結です。
いきたかった場所にたどり着けましたかどうか。
描き込みたいひとは、より華やかに、
シンプルなひとは、より洗練されたシンプルに。
やりたいことは、ひとそれぞれ。
発想が自由に飛躍します。
みんな自分の意思で、勝手に世界観をひろげていきます。
こうして「宇宙でひとつの私の作品」ができるわけです。
目がチカチカ、ぐるぐるしてきますね。
以前にこのブログでご紹介したあの作品やこの作品も、焼き上がり。
期待通りの効果が出てます?
窯を開けたこの瞬間までわかんないのが怖いところ。
そして楽しみでもあるわけですね。
これでおしまい。
最下段の左棚、撮り忘れました・・・(すまん)
こうしてひとつの季節が終わります。
そして、新たなチャレンジのシーズンがすでにはじまってます。
これからも精進して、一品入魂、いいものだけをつくっていきましょ。
窯の神様、いつもたくさんのしあわせをお恵みいただき、ありがとうございます。
祈・・・
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

あーゆーわフィッシュ?
毎年言うてますが、みなさん、お魚を食べませう。
ツマ作、鮎の塩焼き&新生姜の甘酢漬け。

しはん作、鮎の生姜煮的な。
どちらも、しはんの「陶芸教室に通ってた時代の」器で。

これらの器は、バットとしても用いられてます。
マグロのヅケに、ホタテの昆布締め。

と思ったら、昆布の下の層にはタイも。

お刺身をむさぼり食う夜。
お魚が主食のしはん家です(この夜は特別だけど)。

おみそ汁(赤だし)は、ひとり用の小土鍋で。

鍋敷きも陶製。
食卓を自作品でコーディネイトできるしあわせ。

佐藤(直)さんのお骨ツボづくりも、ついに装飾の段階です。
家で描いてきた下絵を、ボディに写し取っていきます。
桜の季節が好きな方だったのですね。
これを、いっちん技法で描いていきます。
盛るドベは、ピンクの絵の具が練り込まれた淡い桜色のもの。
これは壮観。
そこに、薄墨というのか・・・薄いドベを差していきます。
華やかになりそう。
日がな一日、こうしてます。
ついに完成。
半月をかけて乾かしましょう。
この中で眠れるひと、しあわせそう・・・
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

またしはんのパズルの時間がやってまいりました。
おつき合いください。
窯詰めは、背の高いものをおさめる最上段に差し掛かっております。
この空いたスペースに、あえて背の低いお皿を配置。
そしてその周囲三点にツク。
こちら、上と同じ画像ではありません。
二枚目の皿が置かれたことがご理解いただけてるでしょうか?
その上に、さらにステージを設置。
これが最終的な最上段。
プラチナ席なのでした。
しかもここ、「青磁マット」という特別にわがままな釉薬を掛けた作品専用の場所。
ここまで計算して知恵を絞って配置してるって、みんな知らんでしょ?
背丈もなんとかギリギリにおさまった感じ。
左サイドの芸術活動を終えて、今度はまだ空いてる右サイドへ。
ごちゃごちゃ詰め・・・
なんちゅーもんつくってくれてんねん・・・
窯詰めの最終盤は、いつも脳に汗をかきながらの作業。
作品は、触れ合っちゃダメ。
超緊密、かつ、お互いに接触し合わない距離を確保。
地震、きませんように・・・
カマボコ屋根、両サイドに注意を払いながら、ワゴンを進めます。
新幹線の車両をトレーラーで運ぶ画づらをニュース映像で観たことあるでしょ。
あれの、高架を潜ったり、最後の急カーブを曲がるとこの神経の使い方と似てるかも。
無事、車両基地に納車。
早めにスイッチポンして、窯出しは14日(月)となりました。
よい焼き上がりを祈っててください。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

素焼きが終わったら、みんないっせいに釉薬掛け。
普通はじゃぶんとズブ掛けですむこの仕事も、森魚工房では筆でのぬり分けが主流(いや、半々か?)。
古賀さんは、こちらの作業でも紫陽花を描き込みます。
絵付けに用いるゴスは「ドロ」、釉は「ガラス」という違いがありまして、要するに釉の方は重ねると溶け合います。
なので、重ならないように、釉を一層のせた部分は撥水剤でコーティング。
そいつをざんぶと、背景色の釉に沈めます。
すると、紫陽花がきれいに(?)二色めをはじいて、かぶることなく発色してくれるというわけ。
うちの連中ときたら、こんなことばっかやってます。
ハモニコさんの、お花ピアノ。
いろいろにぬった部分をコートしてからの、霧吹き掛け。
しづさんは、撥水剤で絵付けをして、その部分をはじかせる形での釉のズブ掛け。
地に用いた練り込みのピンクが、釉の間から覗くという算段。
河鍋さんは、下地の色からポイントを抜いてからの、さらにその部分に筆ぬりという、根気のいる作業。
ぬり分けの大家、カミクボくん。
いちいち別の色を欲しい部分に筆塗り。
原始的。
しかし、いちばん確実。
みんな、手間ひまをかけてます。
大沢さんのぬり分けも、手が混んでる。
ここまでやっての、人気作家さん。
どれもギャラリーやネット経由で、たちまちお嫁にいきます。
やっぱし作品づくりは、真心ですね。
その一点をどれだけ愛せるか!・・・それだけです。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園














